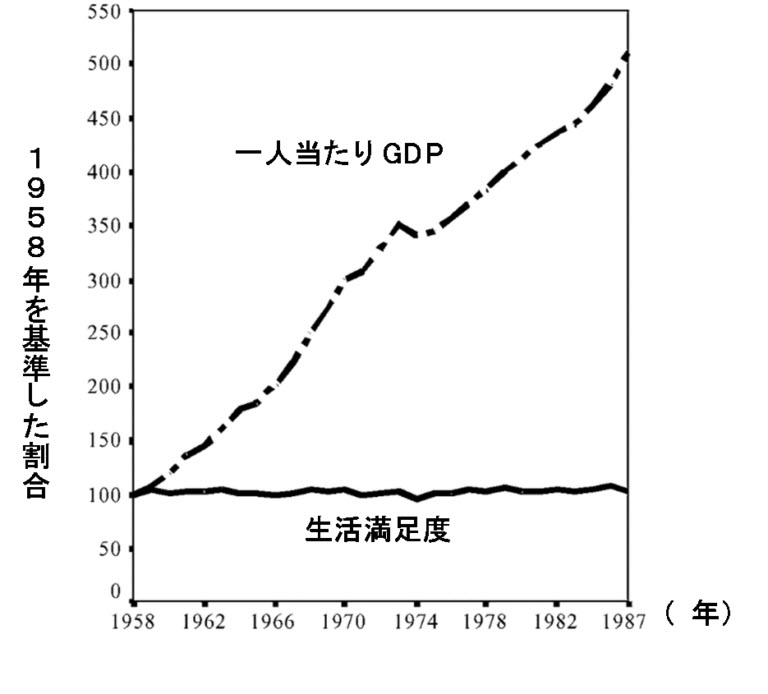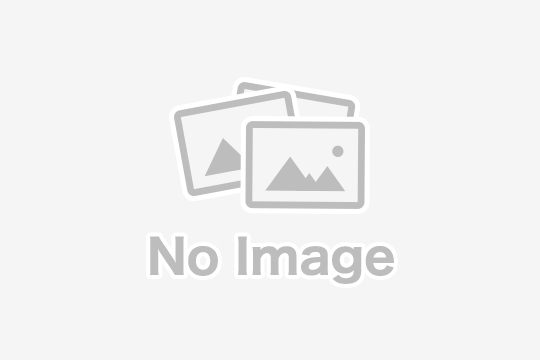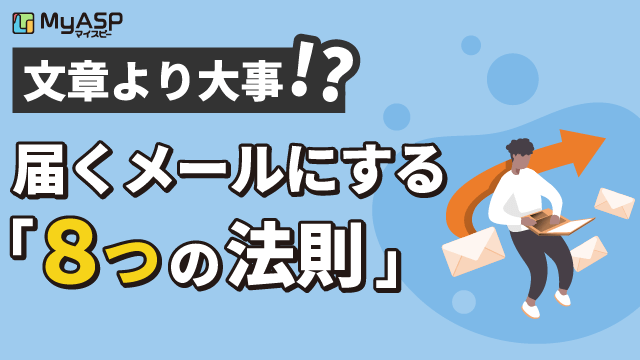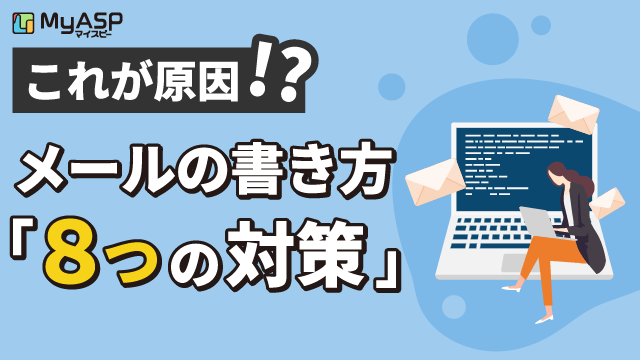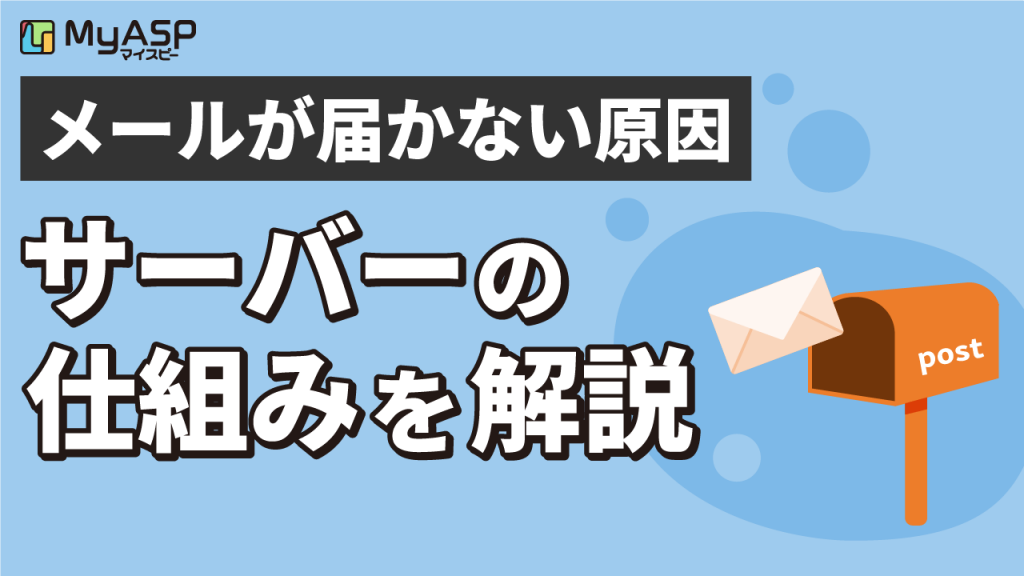こんにちは、マーケティング部のおさいです。
今回は、1兆3000億円を運用する日本最大級ファンドの投資家が語る、「ChatGPT(AI)の登場による長期志向への転換」をテーマにお話します。また、AIの登場によって短期利益志向では立ち行かなくなってきているなかで、世の中の大きな流れの変化として、長期的な価値を測る「新しい経営指標」の重要性が増していることについてもお話します。
今回の話は、投資をしている人や、これから投資をはじめる人にとって参考になるだけではありません。
起業家や経営者やマーケターのような、時代の流れを読み、未来を見据えて事業をおこなう人にとっても、参考になる話です。
たとえば、ソフトバンクグループの創業者である孫正義さんは、「投資家は事業家のように考えるべきだし、本物の事業家は投資家のように考えるべきだ」と語っています(下記参照)。
(※孫正義さんは、ソフトバンクを創業した起業家(事業家)であり、また、10兆円という巨額の資金を運用するベンチャーキャピタル「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を率いる投資家でもあります。)
孫正義さんの「投資と事業」についての考えは、次のとおりです。
よく「投資家なのか」「事業家なのか」と聞かれるのですが、僕は投資家は事業家のように考えるべきだし、本物の事業家は投資家のように考えるべきだと思います。つまり、投資家と事業家というのは相反するものではない。それぞれの真髄は、実は同じものだと思います。
ことの本質というのは、長期的にどれだけ会社の価値を増大させられるかということ。それを目指すという点において、投資家も事業そのものが生み出す長期的なキャッシュフローを見極めなければいけません。
同じく、事業家というのは単にモノを組み立てたり、販売するものではない。世の中がどのように変わるのか、その変わってゆく方向を理解して、ヒト・モノ・カネという経営資源を、投資ポートフォリオの組み換えのように再配分する仕事です。まるで投資家のように、事業家も考えないといけないと思うのです。
ですから投資家は事業家のように、事業家は投資家のように考えないといけない。
(出典:『ベンチャー・キャピタリスト : 世界を動かす最強の「キングメーカー」たち』、後藤直義 [著者]、フィル・ウィックハム [著者]、ニューズピックス、2022年。第4章内の「世界を震撼させた、孫正義「10兆円ファンド」の正体」の項目より)
上記の、孫正義さんの「投資と事業」についての考えは、下記の動画の「24:16~24:44」のところでも語られています。
▼ 24:16~24:44上で孫正義さんが語っているように、「投資も事業も、その本質は同じ」です。ですので、今回紹介する、「投資家が見据えている未来」や、「投資家が重視する経営指標やキーワード」を知ることは、起業家や経営者やマーケターにとっても参考になるでしょう。
ちなみに、今回の話のテーマは、「長期志向(未来志向)」です。そのため、「投機(短期利益志向)で儲ける」という話ではありません。(むしろ、「短期利益志向では、儲からなくなってしまう」という話です)。今回の話は、本来の意味での「投資(長期志向、未来志向)」を考えるうえで、参考になるかと思います。
この記事は、2部構成になっています。第1部では、「ChatGPT(AI)の登場による長期志向の投資への移行」についてお話します。第2部では、そういった長期志向への移行に関連して、長期的な価値を測る「新しい経営指標」の重要性が増していることについてお話します。
(※この記事では、動画内で話されていることをわかりやすく伝えるために、動画の内容を、意訳・要約したり、中略したり、補足を加えています。また、わかりやすさを優先しているため、厳密ではない説明になっているところもあります。また、参考文献の本からの引用文については、要点をわかりやすくするために、引用者が引用文の一部に文字装飾を加えています。引用文中の〔〕(亀甲括弧)内の言葉は、引用者による注記です。)
▼ 第1部
ChatGPTの登場による長期志向の投資への移行
1.3兆円を運用する藤野英人さんのプロフィール
今回紹介する「1.3兆円を運用する日本最大級ファンドの投資家」というのは、藤野英人(ふじのひでと)さんのことです。藤野さんのプロフィール紹介は、下の動画の「1:37~2:25」のところで視聴できます。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
1:37~2:25
藤野英人(レオス・キャピタルワークス代表取締役 会長 兼 社長)
運用資産残高 1.2兆円のカリスマ・ファンドマネージャー
〔※この記事の執筆時点では、1.3兆円を突破しています。〕
早稲田大学法学部卒業後、野村投資顧問や、JPモルガン、ゴールドマン・サックスにて、ファンドマネージャーを歴任。
2003年に、レオス・キャピタルワークスを創業。
投資信託「ひふみ」シリーズ最高投資責任者。
2023年4月に上場を果たす(東証グロース市場)。
自社が運営するYouTubeチャンネル「お金のまなびば!」は、金融業界ナンバーワンの登録者数22万人を突破〔現在は、登録者数 69万人を突破〕。
長期志向の投資に集中しよう(短期利益志向を捨てる)
投資家の藤野英人さんが、「ChatGPTの登場によって、短期利益志向の投資を捨てて、長期志向の投資に集中しようと考えた」という話が、下の動画の「17:41~25:50」のところで語られています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
▼ 17:41~25:50▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
「10年後を見据える投資思考法とは?」
17:54
私がすごい衝撃を受けたのは、ChatGPTなんですよ。ChatGPTが登場したことで「資産運用業界が激変する」と確信しました。
資産運用業界は、これから3~5年間で激変して淘汰が始まります。これから大きな激変期になります。
〔中略〕
18:40
ChatGPTが登場したことによって、短期予測を中心とした資産運用が崩壊します。
たとえば、ブルームバーグや、東洋経済などの金融データを、ChatGPTのプラグイン経由で利用・加工できるようになることで、短期予測の数字をほぼ当てることができるようになる。人間よりも高い精度でできるようになる。
〔中略〕
19:43
ChatGPTが登場したことで、「短期投資を見てもしょうがない」、「短期投資から付加価値が出ない」、という状況になります。
なぜなら、短期投資の調査が、AIと自動売買の普及によって〔全員がほぼ同じ行動をとることになり、〕付加価値がゼロになるからです。
〔中略〕
20:30
ChatGPTが登場したことで、〔資産運用業界が激変すると確信したので、〕予測期間を長期に伸ばして、10年後の世界を考えよう、と思いました。
1~3年ぐらいの短期予測については、もう考えない。
「10年後はどうなるのか?」という未来予測をもとに運用を考えていく方向に、思いっきり舵を切ることにしました。
〔中略〕
23:09
ものすごく大事なことは、あるべき未来を僕らが予測して〔、その未来を実現できる会社に投資して、社会を良い方向へ導いていくことです。〕
僕らには、今、126万人のお客様がいます。〔日本の人口の〕100人に1人が僕らのお客様なんですよ。
だから、もう小さい政党みたいなものなんです。それだけのパワーがあるので、いろいろできる余地がある。
〔運用資産残高は〕1兆2000億円の残高があるんですよ。
〔※この記事の執筆時点では、1兆3000億円を突破しています。〕
1兆2000億円の残高を、どうやって世の中のために使っていくのか?
どうやって、未来を指し示すのか?
あるべき未来を想像し、そこへ誘導するのが、本来あるべきアクティブファンドの姿だと思います。
〔中略〕
24:10
アクティブファンドは能動的に社会に対して影響を与えて、社会全体を導き、動かしていく存在であるべきだと思います。
24:27
もし、ChatGPTを高速回転で動かして、株式市場で利ざやを取って儲けることができたとしても、それが社会のためになったり、社会を良い方向へ導くことになるとは思えません。
お客様のお金を、本当の意味で活用できるとは思えません。
24:45
ですので、3~4年の短期的な「業績の当てっこゲーム」は、もう終わりにする。
来るべき未来の方向性を議論し、その方向性にしたがって経営者と議論し、経営者が10年後の未来を見据える目線をもっている会社を探して、お互いに共感できる会社に集中投資をする。
そうすることで、「未来を創造する」「未来へ誘導する」というかたちのアクティブファンドになることができると思います。
25:17
企業経営者や、投資家、消費者と一緒に未来を作り、未来を創造するための議論をしていきたい。
アクティブにパフォーマンスを上げていく会社から、オープンにみんなで議論し、みんなの知恵を集めて、社会を良い方向へ導いていく存在になりたいと思っています。
できないかもしれないけど、めちゃくちゃ大きい「旗」を立てたい。
時代の転換点が来ていると思います。
これから10年で起きる資産運用業界の変化
さきほどの動画と同じように、下の動画でも、投資家の藤野英人さんが、「ChatGPTの登場によって、短期利益志向の投資を捨てて、長期志向の投資に集中しようと考えた」という話が語られています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
▼ 0:00~10:01▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
「これから10年で起きる資産運用業界の変化」
0:36
生成AIのChatGPTを見て非常に驚きました。「劇的な変化が起きたな」と思いました。
1:27
〔ChatGPTのような、〕高速に分析や調査ができる機能が登場したことによって、短期的な予測(四半期決算の業績予測や、来年の業績予測)については、ChatGPTを使って予測して投資をするようになったために、予測数字がみんな同じになってしまっている。
そのため、付加価値がほとんど出なくなってしまう。短期的な視野だけで投資することは、価値が無くなってしまった。
2:12
そのため、運用のやり方を劇的に変えないと、長期的に成果が出せない時代になった。
2:28
AIにも予測できないような、5年・10年の未来を予測して、その未来にもとづいて投資をする、10年後の未来を考えながら投資をする、というやり方に振り切ったほうがいいと考えました。
こうして、投資のやり方を劇的に未来志向に変えました。
3:05
また、投資先の会社とも、未来について語り合います。「僕らはこういう未来になると思うけれども、どう思いますか?」と問う。「あなたの会社は、どのような未来を作りたいのですか?」と問う。そうしたことを、投資先の会社と常に議論していく。
3:25
10年後の未来に対して力強く進んでいる会社や、未来を作ろうとしている会社に投資していくことが大事。そうしたことが、未来を作ることになる。
未来を予測するのではなく、そうした会社と一緒に未来を作っていく。それが、僕らの運用のあり方の大きな変化です。あるべき未来に対して、資金を投入していく。
4:40
僕らは、今いる126万人のお客様や、これから集まってくださるお客様とともに未来を作っていく。あるべき未来に行く。そうしたところに、僕らのお金を投入していく。それが、僕らが考えている「ひふみ投信」の大幅なあり方の変化です。
〔中略〕
5:29
会社全体として、「僕らは未来を作る集団なんだ」というふうに思わなければいけない。
〔中略〕
6:02
「短期的な目線」は捨てよう。それは、もういらない。僕らは常に、10年後のことを語ります。
7:23
「〔長期的な目線をもった〕投資家と、10年後の話をしたい」という会社経営者は、けっこういると思います。そうした未来の話をした時に、目を輝かせる会社の人たちとともに歩んでいきたいなと思っています。
投資をするときに、長い目線で、会社とのパートナーシップを考えて、「未来をともに作っていく仲間なんだ」という旗を掲げて、僕らの存在感も高めたい。
〔中略〕
8:59
「長期的な目線をもった会社のほうが、短期的な収益も良い」
「短期投資で成功するためにも、長期的な目線をもっているほうが良い」
という仮説を立てています。
9:19
ChatGPTが登場したことで、短期投資は、ほぼ勝てなくなる。
ChatGPTのような AI を使って投資をする人が増えるので、短期的な目線で投資で勝つことは、非常にむずかしくなる。
9:35
もともと、「ひふみ投信」は、この10年間に圧倒的な成果を出していて、もともと長期的な目線があったんですが、これから、長期的な目線にすごくフォーカスした運用会社に変身していきます。
AGI(汎用人工知能)によって、この傾向がさらに加速する
ちなみに、さきほどの動画で、投資家の藤野英人さんは、「AIが登場したことで、短期投資で儲けることができなくなる」というような意味のことを語っていました。そのような現状に加えて、下の動画の「33:01~33:53」のところで、孫正義さんが語っているように、近い将来に、AGI(汎用人工知能)が登場したときは、今よりもさらに、短期投資に価値が無くなってしまうでしょう。
▼孫正義さん:ソフトバンクグループ 会長 兼 社長
33:01
数兆通りの投資のシミュレーションをしながら、投資をすべきかどうか〔を、AGI(汎用人工知能)が判断してくれる。〕
33:09
投資ファンドも、金融機関も、ありとあらゆる人々が、AGI〔汎用人工知能〕に投資の相談をするようになる。
AGI〔汎用人工知能〕に投資の運用をしてもらうようになる。
これが最も大きなキラーアプリの1つかもしれませんね。
33:27
人間は願望を言えばいいだけです。プログラミングの必要がない。
「私は、お金持ちになりたい」と一言言えば、AGI〔汎用人工知能〕が「かしこまりました」と言って、口座を開いて、取引をして、成果を届けてくれる。
人々の知的能力の差が無くなる
さきほどの投資家の藤野英人さんの動画で、「ChatGPTの登場によって、短期投資は誰がやっても同じになってしまって、利益が出せなくなる」という話が語られていました。そのような、「人々の知的能力の差が無くなることで、差別化ができなくなる」ということについては、下の動画の「6:41~8:06」のところでも語られています。
下の動画では、東大の松尾豊研究室所属のAI研究者である今井翔太さんと、藤野英人さんが、「投資とAI」というテーマで対談しています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
下の動画で語られている話が示唆していることは、「知的能力を AI(ChatGPT)にサポートしてもらえるようになると、個々の人間の知的能力の差が無くなる」ということです。また、一方で、「他の人とは異なる、極端なおもしろいことをすることの価値が高まる」ということも示唆しています。このように、これからの時代は、「他の人と同じことをする」という、「横並び」意識や、パクリ志向、コピペ志向などが、ますます役に立たなくなっていきます。
▼ 5:23~8:065:21
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
多くの証券アナリストやファンドマネージャーは、「企業業績が、予想よりも上に行くか下に行くか」という、「当てっこゲーム」をしている。
これは、ChatGPTに置き換えられてしまう可能性が高い。
〔中略〕
6:06
〔いろいろなデータを〕ChatGPTに全部読み込ませれば、3ヶ月後や半年後の企業業績が上に出るか下に出るかを、リアルタイムで確率的に予想することが瞬時にできる。
そうすると僕らがやるべきことは、5年とか10年の長期のところをどれだけ見るかではないかと考えたんです。
6:40
▼今井翔太さん:東京大学 松尾豊研究室所属のAI研究者
AIが普及すると何が起きるのかというと、個人の能力差に意味が無くなる。
なので、変な考えを持った人に全力投資・全力投球すれば、これからは、仮に、ものすごいことやってる人が失敗するようなことがあったとしても、それが物語として消費されるので、それはそれでお金になるでしょう。
極端なことをやってる人に賭けるっていうのが、投資でもありなのではないかと思っています。
7:10
▼藤野英人さん
日本人には、バランスを取ることを重要視したり、平均というものを中心にした価値観がある。
生成AIが普及していくと、「極端であることを尊ぶ文化」を持っているところと、「平均値であることを尊ぶ文化」を比べたときに、目立つことや、おもしろいことや、異なることをやってみることを尊ぶ社会のほうが、世の中の進化が高くなる。
日本とアメリカを比べると、アメリカのほうが「突出した才能を尊ぶ文化」があって、日本は平均値に寄せるところがある。
なので、僕らのあり方を変えないと、アメリカとの差はもっとついちゃうんじゃないかという危機感を持っています。
「賢いアリ」のたとえ話
上の動画に出演している、東大のAI研究者である今井翔太さんは、「個人の能力差に意味が無くなる」ということについて、「賢いアリのたとえ話」で説明しています。(下記の『生成AIで世界はこう変わる』の本からの引用文をご参照ください)。
下記の引用文で今井さんが語っていることは、かんたんに言うと、次のようなことです。「人間から見ると、個々のアリの賢さには違いが無いように見える。それと同じように、とても賢いAIから見ると、個々の人間の賢さには違いが無いように見える。(圧倒的に知能が高いAIにとっては、たとえアインシュタインの知能であっても、「アリ」ぐらいの知能しかないように見える。そのため、AIから見ると、アインシュタインと普通の人とのあいだに、知能の差が無いように見える)。」
下の引用文で今井さんが語っていることは、上の動画で語られていた、「知的能力を AI(ChatGPT)にサポートしてもらえるようになると、個々の人間の賢さの差が無くなる」という現象を、別の視点から説明しているものだと言えるでしょう。
この世界で最も賢いアリを考えてみてください。アリには失礼かもしれませんが、賢いと言っても大したことはできません。エサの発見がうまいとか、敵から逃げるのがうまいとか、アリの社会では意味を持つ差があるかもしれませんが、あくまで「人間の視点」から見れば、アリのなかで最も頭が悪いアリと最も賢いアリに大した違いはありません。それはアリが魚になっても、魚が犬になっても同じことです。
ここで言いたいのは、人以外の生物が賢くないということではなく、知能というものが相対的な概念だということです。人間からは先ほどの生物の知能には大きな違いがないように見えますが、それぞれの生物間では、その知能の差には大きな意味があります。
普通の人間とアインシュタインには、「人間の基準では」その知的能力には圧倒的な差があります。そして、アインシュタインの偉業を考えれば、その差には大きな意味があることは「人間の基準」では疑いようがありません。
それでは、先ほどのアリと同じ議論で、将来出てくるであろう人を超えた機械の知能から見て、この差に意味はあるのか。ましてや、この機械の知能はタンパク質由来でもない、生命にも意識にも縛られない。「質」からしてまったく異なるものです。
知能は相対的なものであるとすれば、機械の知能が人間を超えた場合、その知能が超えるのは人間一般であり、その「超知能の基準では」一般人とアインシュタインの間にも大した差はないはずです。
(出典:『生成AIで世界はこう変わる』、今井翔太、SBクリエイティブ、2024年。「第5章 生成AIとともに歩む人類の未来」の章内の、「「超知能」の前では、凡人とアインシュタインの差すらも無意味に?」の節より)
上記の「アリのたとえ話」については、今井さん本人が説明している様子を、下の動画の「45:26~47:55」のところで見ることができます。
▼ 45:26~47:55▼今井翔太さん:東京大学 松尾豊研究室所属のAI研究者
45:27
汎用人工知能や、スーパーインテリジェンス(超知能)というのは、人間と同程度の知能で、運動もできるし、クリエイティブなこともできる。これが、いわゆる、ドラえもんとか、アトムみたいな感じですね。それが、人工知能の研究者の1つの到達点。
45:50
これのさらに先にあるのが、超AIや、超知能(スーパーインテリジェンス)と呼ばれるもの。これは、人間よりもはるかに賢い知能。〔中略〕
46:50
「1番賢いアリ」を考えてみてください。「超賢いアリ」。多分大したことはできない。「エサを探すのがめちゃくちゃうまい」とか、「敵から逃げるのが超うまい」という程度〔人間から見たら大したことはない〕。
魚でも同じ。一番賢い魚でも、「泳ぐのがすごく速い」とか、「超すばらしいコースで泳げる」という程度〔人間から見たら大したことはない〕。
47:21
それを人間の話にもどすと、人間の中で1番賢い人として、アインシュタインがいます。ですが、機械〔すごく賢いAI〕から見ると、アインシュタインと僕は、差が無いように見える。
さっきの、「人間から見ると、最上位のアリと最下位のアリには違いが無い」という話と同じ。魚の場合も同じ。
人間の場合は、人間の知能を超えた機械〔すごく賢いAI〕から見ると、幼稚園児とアインシュタインは、差が無いように見える。
上位の人と下位の人の能力差が無くなる
さきほど、AI研究者の今井翔太さんの本のなかで語られている話として、「人間には、個々のアリの違いがわからないように、知的生産活動をAIにサポートしてもらえるようになると、個々の人間の賢さの差が無くなる」というような話を紹介しました。
それに関連する話として、AIの登場によって、「上位の人と下位の人の能力差が無くなる」という話もあります。
たとえば、梶谷健人さんは、『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』という本のなかで、下記のように語っています。
最後に「これから人の在り方自体がどう変わっていくか?」という問いについて考えていこう。
現代は「個体の能力」というものに価値がある最後の世代だと私は考えている。古代から現在に至るまで、社会が成熟するにつれて人類にとって重要な中核能力は「本能/筋肉/戦闘能力」から「理性/知能/社会的地位」へと比重がシフトしていった。
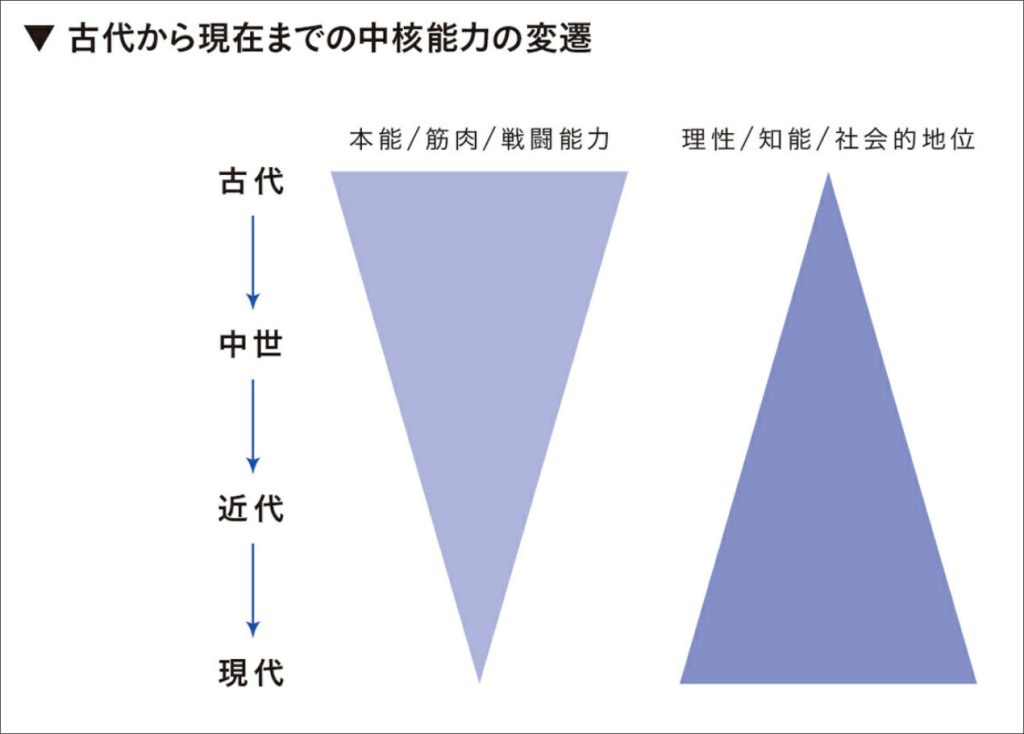
同様に、先述したように今後AIに接続した脳とそうでない脳の間に1000倍の能力差がついてくると、現代において重要な「個体の能力」は重要性が下がり、「AIとの接続数/スペック/速度」などが中核的な能力にシフトしていくだろう。
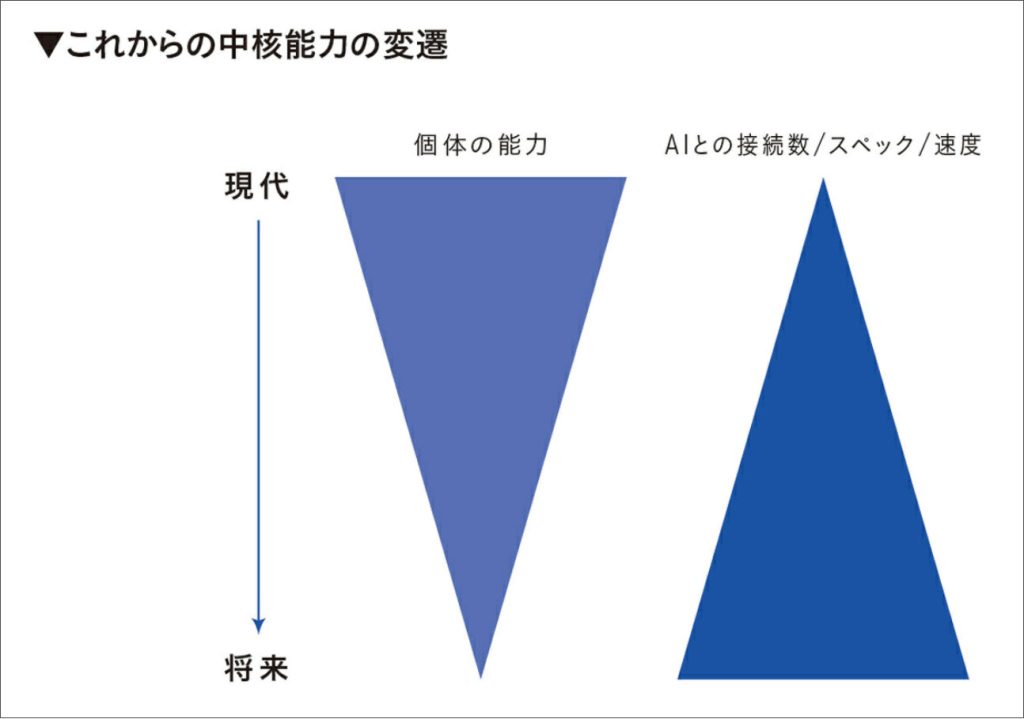
これは現代の価値観からすると一見悲観的に思えるが、それはあたかも筋肉や武力が必要とされなくなる変化に寂しさを感じるのと構造的には同じだ。我々は郷愁は感じつつも、この不可避な変化にしっかりと向き合う必要がある。
つまり、人類史的な転換点として、我々の“思想OS”をアップデートしていくことが求められているのだ。
(文書と図の出典:『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方 : 経営戦略をアップデートするためのフレームワークと未来予測』、梶谷健人、日経BP、2024年。第3章の第1節内の「現代は「個体の能力」というものに価値がある最後の世代」の項目より)
また、上記の梶谷健人さんの本のなかでは、下記のような実験結果も紹介されています。この実験結果も、AIを利用することで「上位の人と下位の人の能力差が無くなる」ということを示しています。
AIが頭脳労働に与える影響について調査したハーバード・ビジネス・スクールに掲載された論文(Fabrizio Dell’Acqua et al., 2023)によると、世界的コンサルティング企業の米ボストンコンサルティンググループ(BCG)のコンサルタント758人を対象に行った実験で、AI を使用したコンサルは非使用コンサルに比べて平均で12%多くのタスクを完了し、25%早くタスクを完了し、40%高い品質のアウトプットを出したという結果が出ている。
特に注目なのは「ローパフォーマー」を含め全体的に底上げがなされたことだ。下図の上側のグラフがGPT-4を用いずに業務を行った際のパフォーマンス分布。平均以上のパフォーマンスを出す従業員をハイパフォーマー、それ以下をローパフォーマーとし、GPT-4を使用した状態でのパフォーマンス分布を表したのが下側のグラフだ。これを見てもらうと、全体的なパフォーマンスが底上げされてグラフの分布全体が右側にシフトしている。組織のボトムアップは経営レイヤーにとって重要なイシューであるため、組織経営視点でこの研究が示す生成AIの可能性は大きいといえる。また、個人観点でも、たとえ特定の業務領域でパフォーマンスが平均以下であっても、適切に生成AIの手を借りればパフォーマンスを大幅に高められる可能性があることを意味する。
※参照:Fabrizio Dell’Acqua et al. (2023), 「Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality」, Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper No. 24-013
(出典:『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方 : 経営戦略をアップデートするためのフレームワークと未来予測』、梶谷健人、日経BP、2024年。第1章内の「生成AIの影響範囲は高度な頭脳労働にも及ぶ」の項目より)
上記の梶谷健人さんの本のなかで紹介されている実験結果については、ボストン・コンサルティング・グループのレポートのなかで、下記のように説明されています。
人間の才能が発揮される新たな機会
これまでに述べてきた集団レベルで見られる影響は、必ずしも生成AIが個人に与える影響を示しているわけではない。平均値ではなく個々の成績を見てみると、GPT-4の使用は個人の成績分布に異なる2つの影響を与えることがわかる(図表4)。第一に、分布全体が右(より高い成績)へシフトしている。これは、前述した約40%もの成績向上が、「ポジティブな外れ値」(標準よりも大幅に高い成績を出した人)のせいではないことをはっきりと示唆している。製品開発におけるアイデア創出・企画の課題にGPT-4を使用した場合、基本的習熟度に関係なく、ほぼすべての参加者(約90%)がより質の高い解答を出した。第二に、成績のばらつきが劇的に減少した。平均的な成績を収めた参加者の割合が、GPT-4を使用した場合の方が高かった。
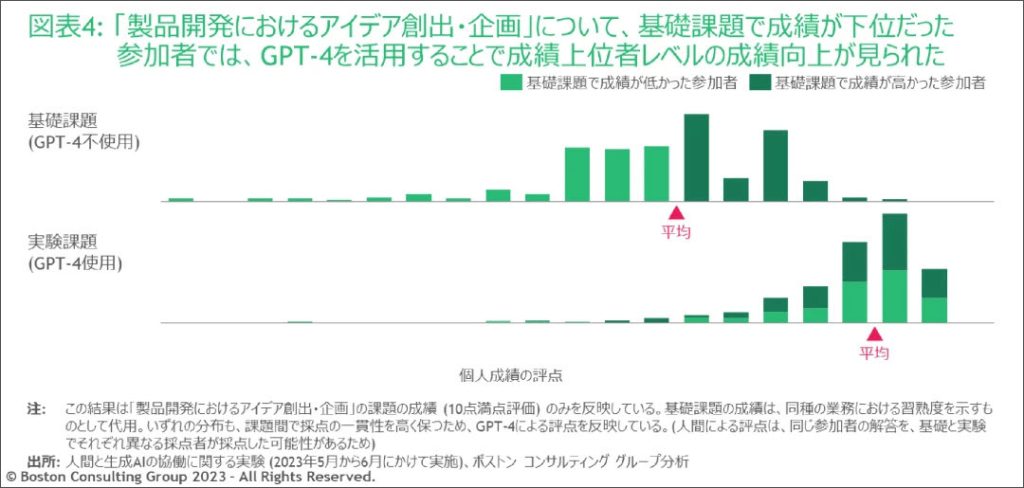
言い換えれば、基本的習熟度の低い参加者が生成AIを使用した場合、習熟度の高い参加者とほぼ同じ結果になったということである。製品開発におけるアイデア創出・企画の業務で誰もがGPT-4を使えば、テクノロジーの助けなしに能力の高い人であっても、それほど優位には立てない(図表5)。高学歴で成績優秀な実験参加者の間でこの影響が観察されたということは、より習熟度に幅があって不均質な状況では、この影響がさらに顕著になる可能性がある。
(文書と図の出典:ボストン コンサルティング グループ(BCG)の記事「生成AIで価値を創出するとき、破壊するとき――実験結果からの考察」のページ内の「人間の才能が発揮される新たな機会」の項目より)
また、「未熟練の人(熟練度の低い人)のほうが、AIを利用することで得られる恩恵が大きい」というような話が、下の動画の「25:25~26:27」のところで紹介されています。その話は、日本の内閣府が発表している「世界経済の潮流 : 2024年 I : AIで変わる労働市場」というレポートのデータにもとづいて語られているものです。この話も、「上位の人と下位の人の能力差が無くなる」ということの一例かと思います。
▼ 25:25~26:27医師の能力の差が無くなる
世界的なAI研究の権威で投資家の李開復(カイフー・リー)さんは、『AI世界秩序』という本のなかで、「医師の能力の差が無くなる」ということについて、下記のように語っています。下記の話も、「AIの登場によって、人々の知的能力の差が無くなることで、差別化ができなくなる」ということのあらわれのひとつだと言えるでしょう。
(※李開復(カイフー・リー)さんの略歴:コンピュータ・サイエンスの分野で世界トップクラスのカーネギー・メロン大学でコンピュータ・サイエンスの博士号を取得。Apple、Microsoftに勤務した後、Google中国法人の社長を務めました。彼が創業したベンチャーキャピタルの投資先のなかには、企業価値10億ドル以上(約1000億円以上)の評価を受けている会社が 17社あり、企業価値1億ドル以上(約100億円以上)は 70社あります。)
医師の診断の核心にあるのは、データ(症状、病歴、環境など)を集めることとそれらと関連する現象(病気)を推測することだ。相関関係を推測するという行為は、まさにディープラーニングの得意分野だ。正確なカルテという学習用データが十分にあれば、AI診断ツールは、いかなる医者も診断のスペシャリストにしてしまう。数万の症例を見てきた経験と、隠された相関関係を見抜く超人的能力と、完璧な記憶力を持つ医師に。
〔中略〕AI診断アプリで医師を補佐する。つまり、“地図アプリ”のようなものだ。持てる知識を総動員して一番よいルートを勧めるが、車の運転は人にまかせる。
アルゴリズムは入力された患者の情報から病気を絞り込んでいく。そして診断を下すために必要な情報を要求する。十分な情報を得たアルゴリズムは、可能性のある複数の病名とその確率を出す。
最終決定権はアプリでなく医師にあり、アプリが勧める選択肢をいつでも拒絶できる。だが、アプリは、4億を超えるカルテを参考にし、最新の医学論文を絶えずスキャンして選択肢を提示する。きわめて不平等な社会に、世界的医療知識が平等に普及するのだ。そして、医師と看護師は、機械にはできない人間的作業に専念できるようになる。患者に親身に接し、希望の持てない診断が下ったときは心のこもった言葉をかけるのだ。
(出典:『AI世界秩序 : 米中が支配する「雇用なき未来」』、李開復(カイフー・リー)、日経BP、2020年。「5 AIの4つの波」の章内の、「“アルゴリズムが診断します”」の節より)
マンガ編集者の能力もChatGPTで差が無くなる
マンガ編集者の佐渡島庸平さんは、「ChatGPTの登場によって、マンガ編集者としての自分のスキルが無価値になってしまった」という話を、下の動画の「27:29~30:13」のところで語っています。その話も、「ChatGPT(AI)の登場によって、人々の知的能力の差が無くなることで、差別化ができなくなる」ということの実例のひとつだと言えるでしょう。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
(※佐渡島庸平さんは、『宇宙兄弟』、『ドラゴン桜』、『働きマン』、『バガボンド』など、有名なマンガの数々を、編集者として支えてきた人です。)
27:29
▼佐渡島庸平さん:マンガ編集者、株式会社コルク社長
ChatGPTにマンガのあらすじを入力して、ChatGPTから漫画家さんにアドバイスしてもらうと、編集者よりも良いアドバイスをしてくれる。
なので、ストーリーの打ち合わせは、ChatGPTと漫画家さんだけでやってもらう。むしろ、「ChatGPTをどう使うと、ChatGPTとの良い打ち合わせができるのか」ということを漫画家さんにアドバイスしている。
つまり、僕が20年間のキャリアで蓄積してきたマンガ編集者のスキルは、ChatGPTによって無効化されてしまっている。
僕は、これまで身につけたスキルが無効化されたら、それはそれで、「他のことを学ばないと」という気持ちが湧く性格なのでいいですが、
そうは言っても、「せっかく身につけたスキルが無効化されるのは悔しい」という気持ちには、誰しもがなると思いますよ。
28:41
▼岩本Pさん:チャンネル運営プロデューサー
だからといって、AIを拒絶しても、何の意味もないということですよね?
28:45
▼佐渡島庸平さん
AIを拒絶してしまうと、AIを活用する他の人たちに負けてしまう。〔なので、AIを使わざるを得ない。〕
僕も、「マンガ編集者として、俺いらないじゃん」って思うので、むちゃくちゃモヤモヤしますよ。
この20年間、出版業界でスキルを磨いてきたのに、意味が無くなってしまった、ということについては、むちゃくちゃモヤモヤします。
そうは言っても、ChatGPTの普及は止められない。
自分がAIを拒絶したとしても、AIを活用して成功する新人クリエイターたちはどんどん出てくる。
だから、僕は、その新人クリエイターをサポートできるような、これまでとは違う能力を身に付けようとしている。
今まではストーリーについてのアドバイスをすることが、新人作家のためになると思っていたけれど、〔その役割は、ChatGPTに取って代わられてしまった。〕
なので、これまでとは別の方向に、自分の能力を磨いていくことにしました。〔具体的には、〕ビジネス面でのアドバイスをするようにしたり、クリエイターがキャリアを積んでいくなかで起こるトラブルを予防するためのアドバイスをするようにしたり。
また、マンガ編集者の佐渡島庸平さんは、「AIで置き換えられる仕事と、そうでない仕事」について、下の動画の「21:20~25:48」のところで語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
21:20
▼佐渡島庸平さん:マンガ編集者、株式会社コルク社長
〔AIによって〕自分のスキルが無効化されてしまって、自分の優位性が無くなってしまうことは、クリエイターだけじゃなくて、すべての職業で起きるだろうと思う。
例えば、これまでは、感じが悪い医師であっても、みんなが「先生」として扱ってくれていた。
でも、診断をほとんどAIに任せるようになると、状況が変わる。
「患者の不安をわかってくれない人なんて、お医者さんじゃない」とか、「なんで目を見て話せないんですか?」とか、「目を見て話せない医者は、全員失職です」みたいなことだって起きる可能性がある時代が来ている。
今、ケアワーカーとして働いてる人たちがAIを使うようになると、今の医師の職業をほとんど奪っちゃう可能性だって全然ある。そういう時代が来ている。すべての産業において、そのような変化が来ている。
僕らが、より他者とか社会と向き合わないといけなくなってきている。
僕らが、他者とか社会と向き合うっていうのは、より豊かな世界になっていくことだと思うので、僕はそういうことを全部前向きに捉えてるんですよね。
〔中略〕
23:10
▼佐渡島庸平さん
ケアワーカーの人たちは、とてつもない、言語化できない、数値化できないスキルを持っている。それなのに、現状は、軽く見られていて、給与が低い。
たとえば、うちの息子は不登校気味なんですけど、うちの息子を学校の入り口まで連れていって、僕らが半日説得しても息子は学校行かないと、
そこに先生が来て息子と話すと、「えっ、そんなことが今週あるんだったら、学校行ってみようかな」みたいな感じで、息子が学校に行けたりする。
そうした、先生のしゃべり方のうまさは、簡単に数値化できないし、計測しにくい能力だったりしますよね。
多分、ほとんどの病院で、看護師の人たちによる声がけがなかったら、患者さんが不安を感じて、医師との診断時間が短すぎることに対しての不満が爆発して、入院がうまくいかなくなる可能性がある。
でも、看護師さんが、そうした患者さんの不安を鎮めていることに対しては、診療点数はつかない。そういうスキルを持ってる人たちが評価されていない。むしろ、言語化しやすかったり、確認しやすいスキルを身につけている人のほうが給与が高い。
でも、言語化しやすいものは、AIで置き換えやすい。だから、人の心をケアしてる人たちがAIをうまく使えればいいと思います。
〔中略〕
25:14
▼佐渡島庸平さん
だから、いろんな人にチャンスが開かれている。
AIはコパイロット(人間をサポートする役割)でしかないので、人間の代替物にはならない。
〔中略〕
25:33
▼梶谷健人さん:POSTS代表
そもそも、「AIと競争する」ということじゃないんですよね。
「AIと人間のどちらが勝つか」というより、AIと協力して、定式化できない部分を人間が担う。そういう時代ですよね。
AIで置き換えできる仕事と、人間向きの仕事の4分類
さきほどの佐渡島庸平さんの動画で、「AIで置き換えられる仕事と、そうでない仕事」についての話が出たので、参考までに、それについての話を、もうひとつ紹介したいと思います。
さきほど紹介した李開復(カイフー・リー)さんは、『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』という本のなかで、「AIに置き換えられやすい仕事」と、「人間向きの仕事」を分類した図を紹介しています。具体的には、「ホワイトカラーの仕事(認知系職業)」と、「ブルーカラーの仕事(身体系職業)」の、2つの職業区分のそれぞれについて、「AIに置き換えられやすい仕事」と、「人間向きの仕事」を、4つに区分して説明しています。(下の「4つに区分された図」が、それらの図です。)
下の「4つに区分された図」については、李開復(カイフー・リー)さん本人による解説を、下の動画の「9:51~20:43」のところで見ることができます。
(※李開復(カイフー・リー)さんの略歴:コンピュータ・サイエンスの分野で世界トップクラスのカーネギー・メロン大学でコンピュータ・サイエンスの博士号を取得。Apple、Microsoftに勤務した後、Google中国法人の社長を務めました。彼が創業したベンチャーキャピタルの投資先のなかには、企業価値10億ドル以上(約1000億円以上)の評価を受けている会社が 17社あり、企業価値1億ドル以上(約100億円以上)は 70社あります。)
▼ 9:51~20:43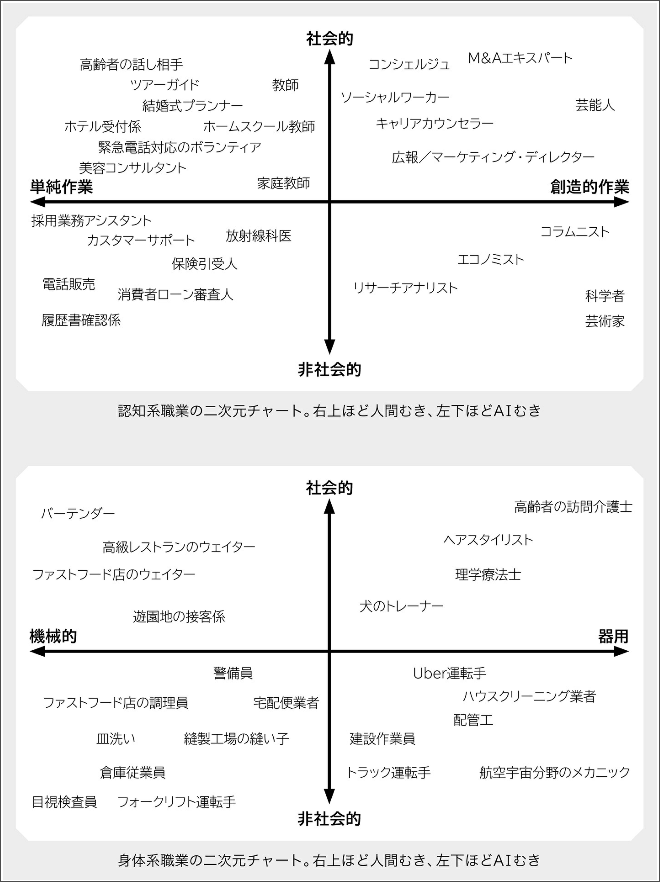
(図の出典:『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』、李開復(カイフー・リー)、文藝春秋、2022年。「未来8」の章内の、「テクノロジー解説」の節内の、「肝心な問いとして、AIはなにが苦手なのか」の項目より)
「AIに置き換えられやすい仕事」と、「人間向きの仕事」についての話は、李開復(カイフー・リー)さんの著書『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』のなかで、下記のように語られています。(ただ、AIの分野では、「突然、それまで不可能とされていたことが可能になる」ということが起こり得ます。ですので、下記の話をすべて鵜呑みにしてしまうのは、あまりよくないかもしれません)。
AIがもたらす大転職時代に人々を路頭に迷わせないために、まず知るべきこと。それは、AIができない業務はなにかだ。それがわかれば、AIに負けない職業を創出してそなえることができる。就職案内も職業訓練もその方向をめざし、需給をバランスさせられる。
わたしが考えるAIの苦手分野は3つあり、2041年の時点でもこれらの欠点を補えていないはずだ。
1 創造性
AIは創造、概念化、戦略策定ができない。目標を絞って最適化するのは得意だが、みずから目標を選んだり、創造的に考えることはできない。領域間にまたがって考えることも、常識を適用することもできない。
2 共感
共感や同情を感じられない。その感覚をふまえてやりとりすることができない。そのため相手に、理解されている、大切にされていると感じさせることもできない。AIのこの欠点を改善できたとしても、共感や心づかいを求められる分野、いわゆる“人間的なサービス”を求められる分野で、人間が気持ちよくロボットと交流できるところまで技術を高めるのは至難の業だろう。
3 器用さ
手先の器用さや目と手の正確な連携が求められる複雑な身体作業は、AIとロボット技術では達成できない。未知の空間や構造化されていない空間、とくに過去に見たことのない空間には、AIは対応できない。
これらの条件から未来の職業を見るとどうなるだろうか。
非社会的で単純作業の仕事、たとえば電話による販売業や保険の損害査定人は、完全にとってかわられるだろう。
社会性がとても高いが単純作業の仕事は、人間とAIが協力して得意分野をおぎないあうだろう。たとえば未来の教室では、AIが宿題や試験の採点をこなし、標準的な授業や個別に練習問題を出すところまでやるだろう。一方で人間の教師は共感力のある精神的指導者になる。実習で学ばせたり、感情知能を育てるグループ作業を監督したり、個別のカウンセリングやはげましをあたえたりする。
創造的だが社会性が低い職業では、人間の創造性をAIツールで補助することになる。たとえば科学者はAIツールを使って創薬研究を加速できる。
最後に創造性も社会的スキルも求められる職業、たとえば「大転職時代」のマイケルやアリソン〔本書内の物語の登場人物〕のような戦略に知恵を絞る会社取締役の仕事は、人間にしかできないところだ。
〔中略〕
たとえば高齢者の入浴を補助する介護士は、社会的スキルも器用さのスキルも求められる。対して工場の組み立てラインでの品質検査はどちらも必要ない。ハウスクリーニングは未知の環境にはいって作業する能力を求められるが、バーテンダーはおもに社会的スキルを使っている。カクテルをつくるだけならロボットのほうが上手だろう。
AIにはなかなか習得できないと思われる職種もそれなりにあり、それを選べば労働者はキャリアを追求するのに比較的安全だろう。
とはいえAIにたちまち置き換えられてしまう職種でたくさんの労働者が悲劇を見ることは避けられない。有意義な人生を送りたいという基本的な人間の欲求を満足させるにはどうすればいいだろうか。
(出典:『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』、李開復(カイフー・リー)、文藝春秋、2022年。「未来8」の章内の、「テクノロジー解説」の節内の、「肝心な問いとして、AIはなにが苦手なのか」の項目より)
人々の身体的能力の差が無くなる
さきほどの、AI研究者の今井翔太さんと、投資家の藤野英人さんの対談動画のところで、「知的能力を AI(ChatGPT)にサポートしてもらえるようになると、個々の人間の賢さの差が無くなる」という話をしました。
それに加えて、これからは、そうした「知的能力の差が無くなる」だけでなく、個々の人間の身体的能力の差も無くなっていきます。なぜなら、AIや、ロボット技術、IoTなどを活用することで、身体的能力を補うことができるようになっていくからです。これによって、お年寄りや、体の不自由な方と、その他の人たちとの身体的能力の差が無くなっていきます。
このことも、「世の中の大きな流れの変化」を知るうえで重要なことなので、すこしお話させていただきます。(投資家、経営者、ビジネスパーソンなど、すべての人に影響を与える、重要なことだと思います)。
そうした「身体的能力の補強」のなかには、身体と機械を融合させた、一種の「サイボーグ化」のようなかたちのものも含まれます。「サイボーグ化」というと、まるでSFの「おとぎ話」のように聞こえるかもしれませんが、真面目に研究され、急速に発展しているテクノロジーのひとつになっています。
ちなみに、パラリンピックの100m走などの選手は、オリンピックの同種目の選手よりも速く走れるようになる可能性があると言われています。このことも、体の不自由な方の身体的能力が、技術によって補われることで、その他の人たちと変わらない能力になる(場合によっては、それ以上の能力になる)ということの、あらわれのひとつだと思います。(余談ですが、パラリンピックの選手のための義足を開発する会社のひとつに、Xiborg(サイボーグ)という会社があります。この会社の会社名が「サイボーグ」であることは、示唆的だなと思います)。
また、筑波大学准教授の落合陽一さんは、「多様化する能力自体を技術でインクルージョンする社会」(Inclusive Society by AI and IoT Technologies)についての図(イラスト)の紹介を、下の動画の「18:30」のところでしています。その図では、「テクノロジーを活用することで、個々の人間の身体的能力の差が無くなる」という未来像が、イラストで表現されています。(下の動画内の図は、英語表記ですが、こちらの動画の「5:57」と、こちらの動画の「9:07」のところで、同じイラストの日本語表記版を見ることができます。)
▼ 18:02~22:50ロボットはここまで進歩している
さきほど、「身体的能力の補強」の話のところで、「サイボーグ」の話をしました。それに関連して、ロボット技術が現在どのくらい進歩しているのかを、すこし紹介したいと思います。
ちなみに、投資家の藤野英人さんは、「10年後を考えるための研究テーマ」として、「3つの大テーマと、10の研究テーマ」を掲げています(下記参照)。
その「10の研究テーマ」のひとつが、「省人化&ロボティクス(ロボット工学)」です。このことにもあらわれているように、ロボット技術の現状や、その先の展望を知っておくことは、「世の中の大きな流れの変化」を知るうえで重要なことだと思います。(投資家、経営者、ビジネスパーソンなど、すべての人に影響を与える、重要なことだと思います)。
ひふみ投信の「3つの大テーマと、10の研究テーマ」
(1)テクノロジー&サステナビリティ
①グリーン&エネルギー
②スマートインフラ&イノベーション
③省人化&ロボティクス
森林監視、農業効率化、労働力不足解消のためのドローンとロボティクス技術
(2) ソーシャルインパクト&ヘルスケア
④ダイバーシティ&エデュケーション
⑤フード&ウォーターセキュリティ
⑥ヘルスケアイノベーション
⑦デジタルコミュニケーション&プライバシー
(3) グローバルエコノミー&地政学
⑧エコノミー&トレーディング
⑨地政学&セキュリティ
⑩人口動態&高齢化
(出典:YouTube動画「ひふみ目論見倶楽部 スタートします」(36:46~38:09)と、藤野英人『「日経平均10万円」時代が来る!』の第5章第1節の「3つの大テーマと10の研究テーマ」の項目より)
下記の動画は、NVIDIA(エヌビディア)の2024年の新製品発表イベントにて、NVIDIAのCEO ジェンスン・フアンさんが行った基調講演の映像です。下記の動画の「1:54:40~1:56:22」のところで、有力なロボットメーカー各社のロボットたちが一斉に登場しています。
その場面で登場しているロボットたちは、左から順番に、下記のメーカーのロボットたちです。
- Figure 01:Figure(フィギュア)
- H1:Unitree(ユニツリー・ロボティクス、宇樹科技)
- Apollo(アポロ):Apptronik(アプトロニック)
- Digit(ディジット):Agility Robotics(アジリティ・ロボティクス)
- 〔NVIDIAのCEO ジェンスン・フアンさん〕
- Sanctuary AI(サンクチュアリAI)
- 1X(ワンエックス)
- GR1:Fourier Intelligence(フロンティア・インテリジェンス、傅利叶智能科技)
- Atlas(アトラス):Boston Dynamics(ボストン・ダイナミクス)
- PX5:Xpeng Motors(シャオペンモータース、小鵬汽車)
- Disney Research(ディズニーリサーチ)
ジェンスン・フアンさんが語るロボット産業の未来についての話は、下の動画の「1:55:35~2:08:26」のところでも見ることができます。(下の動画は、2025年の新製品発表イベントの映像です)。
▼ 1:55:35~2:08:26上記の動画をご覧いただくと、いずれロボットが、どんなに優秀な人間の働き手よりも、正確に、速く、安く作業をすることができるようになる将来が想像できるかと思います。そのようなロボットが実現されたあとは、「(ロボットと人間には、能力の差がありすぎるため、)ロボットと比較すると、個々の人間の労働力の高低は無意味になる(「どんぐりの背比べ」になる)」という状態になるでしょう。これも、ある意味で、さきほどの「賢いアリのたとえ話」と同じように、「個々の人間の能力の差が無くなる」ということに通じるものがあると思います。
「優秀さ」の定義が変わる
ここまで、「人々の知的能力の差が無くなる」という話を紹介してきました。それに関連する話として、「優秀さ」の定義が変わる、という話を紹介します。それについて、山口周さんは、下記のようなことを語っています。
(※山口周さんの経歴:電通や、ボストン・コンサルティング・グループなどで、コンサルタントとして従事。現在は、著作家、経営コンサルタント。『ビジネスの未来』や、『ニュータイプの時代』、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』、『クリティカル・ビジネス・パラダイム』など、著書多数。)
▼山口周さん
これからは「人間の優秀さの定義」が変わっていくよなと思っていて。典型的に言うと、麻布や開成に入れるような子が優秀と言われていた。でも何のことはなくて、これは「正解を出せます」ということなんですよね。
(AIのように)正解を出す機械が出てきて、このコストが10年で100分の1とか恐ろしい下がり方をしてる。
(出典:「山口周氏「これからは『人間の優秀さの定義』が変わっていく」 AI研究者・松原仁氏と語る、AI時代に求められる能力とは | ログミーBusiness」より)
また、「優秀さ」の定義が変わる、という話について、山口周さんは、著書のなかで下記のようなことも語っています。
AIによって多くの人が信じて疑うことのなかった「従来の優秀さ」が大きく価値を失っていくことになると思っています。
〔中略〕
AIの価格破壊で「優秀さ」の定義は変わる
IBM社が開発したAI「ワトソン」が、2011年にアメリカの人気クイズ番組『ジョパディ!』に出場し、米国のクイズ王2人と戦ってこれを破ったことが話題になりました。クイズで勝つためには「正解を出す力」が求められます。クイズ番組で、人間のクイズ王がなす術もなくAIに敗れたということは、すでに「正解を出す」能力について、人間はAIに敵わない時代がやってきている。ということを意味します。ChatGPTなどの生成AIによってこの動きはさらに加速することになるでしょう。
このトレンドにおいて忘れられがちだけれども非常に重要なのは、それらAIのコストが非常に安くなってきている、ということです。
〔中略〕
私たちは「優秀さの定義」を書き換えなければならない時期に来ていると思います。
AIの生産性は東大生の40倍!?
AIが得意とするのはクイズやパズルのような「正解がある」問題ですが、これはまさに「受験」と同じなんですね。
日本では優秀な人の定義がものすごく偏っていて、開成や灘から東京大学や京都大学へ進学するような人が優秀とされているわけですが、それの何が優秀なのかと言えば、要するに「クイズやパズルについて速く正確な回答を出せる」ということです。そのような偏差値優等生的な優秀さが量販店で売られるコンピュータに凌駕されるようになると、「正解を出す」という能力が安価に過剰供給をされることになります。
〔中略〕
そうなると「標準的な正解を出す」という類の仕事に関しては、AIの価格が従来通り10年で100分の1という驚異的なペースで低下し続けることに伴って、労働市場における報酬水準もまた劇的に低下していくことになる可能性が高い。
〔中略〕
競争のルールが変わる
これはつまり、「従来とは競争のルールが変わる」ということですから、一部の人にとっては非常に大きなチャンスになると思います。
〔中略〕
重要なのは、AIが情報労働市場に参入することで新たに発生するボトルネックはどこか、そこでビジネスをするためには何が必要なのかをしたたかに見通し、自分のポジショニングを変えていくことが求められます。
(出典:『ChatGPTは神か悪魔か』、落合陽一、山口周、野口悠紀雄、井上智洋、深津貴之、和田秀樹、池田清彦、宝島社、2023年。「第2章 AI時代には「中央値」から外れる勇気にこそ人間本来の知性が求められる 山口周」より)
このように、AIの登場によって、「優秀さ」の定義が変わってしまった現在では、どのような能力が求められているのでしょうか? そのことについて、山口周さんは、「外れ値」が重要だと語っています(下記参照)。(※下記の話は、さきほど紹介した、AI研究者の今井翔太さんと投資家の藤野英人さんの対談動画で語られていた、「他の人とは異なる、極端なおもしろいことをすることの価値が高まる」ということにも通じる話です)。
中央値ではなく「外れ値」で戦う
生成AIのテクノロジーのベースにあるのは統計です。〔中略〕
言い換えると、ChatGPTは統計でいう正規分布グラフの山の一番高い部分、つまり両端から数えてちょうど真ん中のところ、「中央値」を答えとして出すということです。統計の中央値ですから、往々にして「それはわかるけど、まあ当たり前だよね」といった内容になりがちです。
これに対して統計的に出現率の低い、正規分布グラフの山から大きく離れた値を「外れ値」と言います。人間は「中央値」での勝負ではChatGPTに勝てるわけがありませんから、必然的に「外れ値」で勝負したほうがいいということになるわけです。
しかし、外れ値で戦うと言っても、単に奇抜なだけ、トリッキーなだけでは意味がありません。「意外だけど納得感がある」「思いもよらない答えだけど、その手があったか!と思える」、そのような「外れ値」が求められるのです。
〔中略〕
〔中略〕人間の知性というものは、標準的な正解が通用しない特殊な状況において、きわめて独創的な「外れ値」の回答を導き出し、それを実現するクリエイティビティや洞察力、閃きのようなものを持っている。これが「外れ値で戦う」ということです。
(出典:『ChatGPTは神か悪魔か』、落合陽一、山口周、野口悠紀雄、井上智洋、深津貴之、和田秀樹、池田清彦、宝島社、2023年。「第2章 AI時代には「中央値」から外れる勇気にこそ人間本来の知性が求められる 山口周」の章内の、「中央値ではなく「外れ値」で戦う」の項目より)
日本にはびこる短期利益志向
さきほどの投資家の藤野英人さんの話で、「短期投資は儲からなくなる」という話がありました。そうした「短期利益志向」は、これまでもたびたび批判されてきましたが、ChatGPTに代表される生成AIの登場によって、いよいよ「短期利益志向」は、本格的に終わりを迎えつつあります。
ここからは、そうした短期利益志向の問題点と、長期志向に転換する必要性がわかる事例を、いくつか紹介します。
マイクロソフトの元社長が語る、日本の経営者の短期利益志向
下の動画は、マイクロソフト日本法人の元社長である成毛眞さんと、投資家の藤野英人さんの対談の映像です。お二人は、「日本企業の経営がうまくいかない理由」として、短期利益志向を挙げています(17:58~19:20)。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
▼ 17:58~19:2018:01
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
日本の大企業を中心とした経営がうまくいかない大きな理由は、時間軸が短い、もしくは、合ってない、時代にそぐわないやり方をしていることが大きな理由。
18:20
▼成毛眞さん:マイクロソフト日本法人 元社長
もうひとつは、企業の業績を四半期で見ちゃいけないってことなんです。日本の証券取引所は、「四半期でやれ」と、うるさく言ってくる。あれは、ほんとにやめさせないといけない。あれは、企業の足をひっぱる最凶の方法ですよ。
〔それがあるために、〕短期的な利益を求め続けさせられている。
エクイティファイナンス〔※〕をしているわけでもないのに、ちょっと株価が落ちると、株価を気にする経営者とか、おかしいと思う。
〔※エクイティファイナンス:株式を発行して資金調達をすること。〕
エクイティファイナンスをする予定がないのだから、株価なんてどうでもいいはず。それにもかかわらず、四半期報告書のことを気にする。それが、日本企業の力を削いだ最大の理由のひとつ。
もうひとつの理由は、大企業の「雇われ社長」の任期が、3~5年という短い期間であること。あれも最悪。
この2つの「昭和から続く悪習」を取り払わないと、会社経営は成立しない。
また、成毛眞さんと、藤野英人さんは、長期志向の重要性と、短期利益志向の問題点について、次のようなことを、下の動画の「0:40~4:14」のところで語っています。
0:45
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
伸びている会社の3つのポイント
- 1.徹底した顧客主義(お客様第一主義)
- 2.長期主義(長期目線、未来目線)
- 3.データにもとづいて意思決定している
ダメな会社は、これらがすべてできていない。
1:40
ダメな会社は、短期主義。四半期決算ばかり気にしていて、長期的な展望をもっていない。
1:45
ダメな会社は、データを見ていない。
2:20
3年先、5年先を予測するのは難しい。でも、10年先はわかる。
3:20
多くの経営者は、3年先、5年先という、一番予測できない予測をしようとしているから、うまくいかない。
3:40
▼成毛眞さん:マイクロソフト日本法人 元社長
Amazonは、ものすごく長期目線。データを重視している。うまくいっている会社は、そうしている。
下の動画は、投資家の藤野英人さんと、ウェルビーイングの専門家である、石川善樹さんとの対談映像です。この対談のなかでも、「日本企業の経営がうまくいかない理由」として、「短期利益志向」が挙げられています(13:33~15:00)。
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
13:33
時間軸の長さは大事。
日本の会社が競争力を失った原因は、時間軸が短くなったから。
〔中略〕
14:01
四半期決算や、コンプライアンス〔などの「細部」への「部分最適」に集中しすぎてしまった〕。
手段と目的が逆転してしまった。
14:40
時間軸が短くなってしまったことで、長期の投資ができないようになってしまった。長期的なビジョンで人を考えられないようになってしまった。
メルカリの社長が語る、日本の投資家の短期利益志向
メルカリの社長&COO(最高執行責任者)の小泉文明さんは、日本の投資家の問題点として、時間軸が短い(短期利益志向である)ということを指摘しています。その話については、下の動画の「19:41~21:41」のところで、安宅和人さんからの問題提起を受けて、小泉文明さんがそのことについての考えを語っている様子を見ることができます。
(※小泉文明さんと安宅和人さんの肩書きは、撮影当時のものです。小泉文明さんは、現在、メルカリの会長です)。(※安宅和人さんのプロフィール:Zホールディングス シニアストラテジスト。慶應義塾大学 SFC 環境情報学部 教授。元マッキンゼーの経営コンサルタント。イェール大学で脳神経科学の博士号取得。データサイエンティスト協会理事)。
18:58
▼安宅和人さん:ヤフー株式会社 CSO(最高戦略責任者)
R&D(研究開発)に対する投資についての、日本の最大の問題は、投資している金額が少なすぎることです。
アメリカや中国による投資額の20%~25%の資金しか、日本は投資していません。ほかの国々は、この数十年間で、R&D〔研究開発〕への投資額を数倍に増やしています。
むしろ、日本は、R&D〔研究開発〕への投資を減らしてしまっています。日本は豊富な資金を持っているのに、それを投資せずに、自滅しつつあります。
19:44
▼小泉文明さん:メルカリ社長&COO(最高執行責任者)
すごく短期的に企業経営をやっていることによる悪い結果が出ていると思います。時間軸が短いという問題です。
たとえば、メルカリは今、IoT〔モノのインターネット〕や、AIについてのR&D〔研究開発〕に取り組んでいます。
また、メルカリでは、ほぼ全社員を、中国への視察に数百人単位で送って、「中国で今どんなイノベーションが起きているのか」を見てもらっています。今は、シリコンバレーではなく、中国でイノベーションが起きているからです。
また、インドについては、IIT〔インド工科大学〕から、33人の新卒者を、メルカリで採用することになっています。
そういったことをすることで、自発的に「時間軸の長い勝負」に向かっていく必要があります。
メルカリがIPO〔株式上場〕をするとき、海外の機関投資家から、「メルカリの〔長期志向的な〕戦略はとても良いので、その戦略で成長していってください」と言ってもらえました。
ですが、〔短期志向的な考え方をしている〕日本の投資家からは、「利益を出してください」と言われました(※)。そのような日本の投資家は、根本的に〔間違った考え方をしています〕。
〔※この発言の意味は、おおまかには下記のような意味です。「メルカリに早く利益を出してもらうことで、私(日本の投資家)がメルカリに投資したお金を、できるだけ早く回収したい。」〕
20:41
▼安宅和人さん
時価総額が7兆円の Uber (ウーバー) なんて、赤字ですよ〔赤字であること(利益を出さないこと)は、当たり前のことですよ〕。
〔※この発言の意味は、おおまかには下記のような意味です。「Uber (ウーバー) のように、大きく成長するためには、赤字になってもいいので、初期段階で大きく投資をするべきです」(早期に利益を出そうとして、大きく投資するべきときに投資せずに、小さなビジネスのまま成長が止まってしまうようなことは避けるべきです。)〕
20:43
▼小泉文明さん
アジアの投資家たちは、「赤字には慣れているから〔、赤字であったとしても大丈夫ですよ〕」と言ってくれます。
20:48
▼安宅和人さん
「ちゃんと未来に向けて投資しているということですね」
20:53
▼小泉文明さん
〔アジアの投資家は、〕「5年以上赤字がつづくことは、ふつうのことですよ。 たとえ赤字でも、売上高が成長していれば、それで問題ないですよ」と言ってくれます。
20:58
ですが、こうした話は、〔残念ながら、〕日本の投資家にはぜんぜん通じなかった。
〔※日本の投資家は、短期志向的な考え方をしているため、長期志向的な方針を理解してもらうことができなかった。〕
21:06
そうした、〔日本の投資家の、短期志向的な〕考え方を変えないといけない。
グノシーの創業者が語る、日本の投資家の短期利益志向
下の動画は、ニュースアプリのグノシー(Gunosy)の創業者の竹谷祐哉さんと、投資家の藤野英人さんとの対談の映像です。そのなかで、竹谷さんは、日本の投資家が短期利益志向に陥ってしまっていることを指摘しています(3:41~4:35)。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
▼ 3:41~4:35「投資家の仕事とは?」
3:41
▼竹谷祐哉:グノシー(Gunosy)社長
藤野さんと初めてお会いしたとき、印象的なことがありました。
他の投資家の皆さんは、質問する内容が、「3ヶ月先どうなってるんですか?」とか、「半年先どうなんですか?」とか、「数値の進捗状況はどうなんですか?」といった、短期的な視点で質問をされる方が大半なんです。
ですが、藤野さんとお話させていただいたときは、1年後・3年後の話や、「君は、世界がどう見えているの?」といった、非常に抽象度が高い質問をされました。
それまで使っていたQ&Aリスト(投資家対策のための「模範解答」集)がまったく役に立たなくて、「すごく試されてるな」「怖いな、この時間」って思いながら緊張してました(笑)。
4:23
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
竹谷社長の言う通りで、今の投資の現場は、3ヶ月後とか半年先の「業績当てゲーム」になってしまっています。
四半期報告書を廃止したことで、持続的に成長できた事例
ここまで、短期利益志向によって引き起こされている弊害の事例を紹介してきました。ここでは、そうした、短期利益志向による問題を解決した事例を紹介します。
下のグラフは、ユニリーバのCEOに就任したポール・ポールマンさんが、短期利益主義と決別したあとに、ユニリーバの株価が、長期的に向上したことをあらわしているグラフです。(※ポール・ポールマンさんが行った「短期利益主義との決別」というのは、具体的には、「業績予想の公表や四半期開示の中止」などです)。この事例は、「長期志向(未来志向)な会社は、業績が向上する」ということを証明する事例のひとつです。
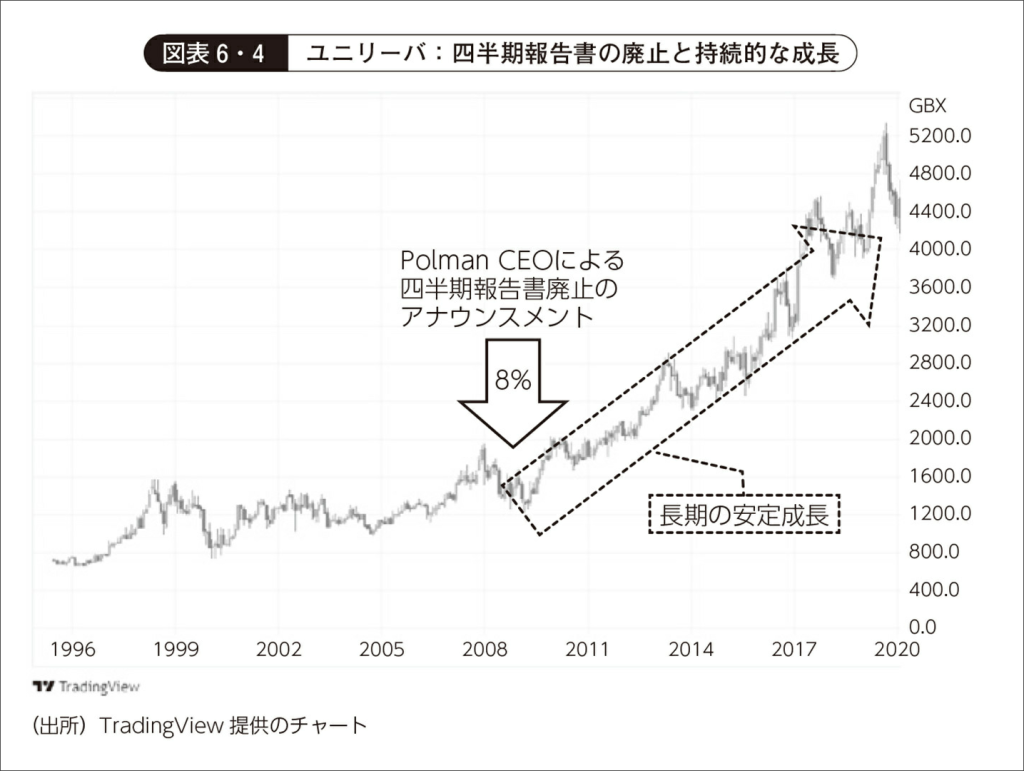
(グラフの出典:スズキトモ (鈴木智英) 『「新しい資本主義」のアカウンティング : 「利益」に囚われた成熟経済社会のアポリア』、中央経済社、2022年。「第6章 シミュレーション2 : 就活生-従業員・投資家・役員・事業の行動変化」の章内の、「5 ユニリーバ:1つのケースから抽象的モデルへ」の節より)
コピペ・コンサルや、コピペ・マーケター、コピペ経営者は消えていく
良い参考事例を取り入れて、自分のものにしていくことはたいせつなことです。ですが、なかには、「うまくいっているらしい」と噂になっている手法を、自分で検証したり分析したりすることなく、そのままパクったり、コピペしたりしてビジネスをしている人たちもいます。また、自分の頭で考えたうえで決断して行動するのではなく、他の会社の出方をうかがいながら、空気を読んで、まわりに同調して動く、「横並び」志向の人たちもいます。
こうした人たちは、いわば、コピペ・マーケターや、コピペ・コンサルタント、コピペ経営者です。長期的な視野をもたず、「短期的に、ラクして儲かればいいや」と考えているという点で、こうした安直なパクリ志向や、コピペ志向は、短期利益志向の一種だと言えるでしょう。
こうした志向は、これまでずっと問題視されてきました。そこへ生成AIが登場したことで、安直なパクリ志向や、コピペ志向では、存続が難しい時代になりつつあります。パクリ志向やコピペ志向な人たちは衰退していく可能性が高いので、投資家や経営者やお客さんから避けられてしまうようになるでしょう。
ここからは、「生成AIが登場したことで、安直なパクリ志向や、コピペ志向では、存続が難しい時代になった」ということについて、いろいろな人が語っている話を紹介します。
ハブスポット(HubSpot)のCMO(最高マーケティング責任者)であるキップ・ボドナーさんは、「コピペマーケターは消えていく」と言っています(下記参照)。(※HubSpot は、CRM(顧客管理システム)を提供している、世界的に有名な会社です。)
少し怠け者で、ただ基本的なことをやるだけのマーケターもいます。例えば、製品のストーリーを書くだけの人や、コピー&ペーストが得意な人もいる。
他の業界で起きていることをまねし、自分の業界でもやってみよう、というアプローチは実はこれまで結構うまくいっていたのです。
しかし、AIはそのコピペモデルをコモディティ化していきます。
これは本当にすぐに起きるはずです。そうすると、ダラダラとコピー&ペーストをするのは難しくなっていく。
そして、本当に差別化されるのは、独創的なアイデア、大規模な言語モデルがあまり見たことがなく、訓練することもできなかった新しい独創的なアイデアです。ですから、新しいこと、異なること、独創的であることは、今後10年間のマーケティングにおいてますます重要になっていくでしょう。
(出典:NewsPicks(ニューズピックス)の記事「【直撃】「マーケティング」はAIでここまで激変する」の「コピペマーケターは消えていく」の項目より)
ちなみに、安直なパクリ志向や、コピペ志向は、コンサルタント業界や、マーケティング業界だけでなく、裁判官のあいだにもはびこっています。(「コピペ裁判官」という言葉があるほどです)。このことについて、人工知能研究者で起業家でもある野村直之さんは、次のように語っています。
頭を使わずに楽に稼ぐことができればありがたい、という発想は、AI時代には捨てるべきだと思います。易(やす)きに流れる人はどの業界のどのポジションにもいます。ある週刊誌で「コピペ裁判官」が話題になりました 注7。過去の判例を支えた本質的理由との一貫性や、相違部分の評価について深く悩み、考えるよりも、無難な落としどころをつぎはぎコピーして判決文を作れるのであれば、確かに楽でしょう。
不毛な仕事をさせられているという自覚や辛さがあるために、ダークサイドに落ちる(易きに流れる)のでしょうか。
〔中略〕
注7 判例検索ソフトによる検索結果をコピーアンドペーストして、判決文を作成する裁判官が増えているというものです。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51901 を参照。
(出典:『実践フェーズに突入 最強のAI活用術』、野村直之、日経BP、2017年。第6章内の「ベーシックインカムでは問題は解決しない」の項目より)
他にも、下記のような危惧があります。
米コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーは、英国の従業員を対象に早期退職パッケージを提示している。世界的にコンサル企業が需要減速を目の当たりにしていることがあらためて示唆された。
〔中略〕
経営コンサル企業は長い間、ホワイトカラーの景気の目安とみられてきた。マクロ経済環境が不透明な中で、長期的な投資を見送ろうと考える顧客企業が増えており、コンサル企業もコスト削減を模索している。
(出典:Bloomberg(ブルームバーグ)の記事「ベインが英従業員に早期退職案、経営コンサル需要減速の新たな兆候」より)
AIにできることが増えれば増えるほど、平凡なコンサルはいらなくなる。
「新卒採用もなくなるかもしれない」(コンサル専門の人材エージェント)という声すらある。
(出典:NewsPicks(ニューズピックス)の記事「【初公開】アクセンチュアのAIが「SaaS」を飲み込む」より)
塩野誠さん(経営共創基盤(IGPI)の共同経営者)は、「ChatGPTの登場によって、大多数のコンサルタントは不要になる」という話を、下の動画の「9:54~12:04」のところでしています。
▼コンサルバブルがはじけた後はどうなる?
〔中略〕
9:54
これからすぐに起こること。
コンサルタントはお客さんに「他社事例ないかな?」と言われたときに、他社事例を10個、20個紹介していました。
ですが、お客さんが〔ChatGPTを使って〕手元で調べるようになると、「そんなの知ってるよ」と言われてしまうようになる。
〔中略〕
10:32
人数が膨れあがったコンサルバブルの中で相当絞っていいってことですね?何分の1ぐらいになるんでしょうか?
10:44
ChatGPTの導入が終わった後は、〔コンサルタントは〕要らなくなっちゃいますよね。
人間に残ったのはビジョンですよね。
〔中略〕
11:17
「人間に残されているものはなにかな?」と考えるべき。
トッププレイヤーだと、ビジョンと、現場。
「中」〔中間層の仕事〕は無くなる。「中」は、マシン〔AI〕がやってくれる。
だから、想いと意志のある人にはいい時代ですよね。AIの肩に乗ることができるので。
シリコンバレーと日本に拠点を置くベンチャーキャピタルのWiL(ウィル)の元共同経営者である久保田雅也さんは、「〔AIは、〕マッキンゼーのコンサルを置き換えるかもしれない」と語っています(出典:NewsPicks(ニューズピックス)の記事「【証言】グーグルが悩む「イノベーションのジレンマ」」より)。
マッキンゼーは、世界的に有名なコンサルティング会社であり、大企業とともに世界中の経済を動かしてきた、飛び抜けて優秀なコンサルタントさんたちの集団です。久保田さんがおっしゃっていることは、そのような、抜群に優秀なコンサルタントでさえ、ChatGPTなどのAIに置き換えられてしまう可能性がある、ということです。もしそうだとすれば、マッキンゼーのコンサルタントほど優秀ではないコンサルタントは、当然、AIに置き換えられる可能性がある、ということになるでしょう。
落合陽一さんは、下の動画の「19:04~20:18」のところで、「コンサルタントは、いらなくなる」という話をしています。
19:04
▼佐々木紀彦さん
日本でも「コンサルがいらなくなるんじゃないか?」みたいな話がありますよね。
19:07
▼落合陽一さん
確実にいらなくなりますね。
このように、「うまくいっているらしい」と噂になっている手法を、自分で検証したり分析したりすることなく、そのままパクったり、コピペしたりしてビジネスをすることは、どんどん危険な行為になっています。
そのような時代に重要な姿勢として、ケヴィン・ケリーさんは、ものごとを鵜呑みにせずに、みんなが当たり前だと思っている「常識」を疑ってみる、ということを提案しています。そのことについて、ケヴィン・ケリーさんは、『5000日後の世界 : すべてがAIと接続された「ミラーワールド」が訪れる』 という本のなかで、下記のように語っています。
(※ケヴィン・ケリーさんのプロフィール:テクノロジーと文化についての雑誌『WIRED』(ワイアード)の共同創業者であり、創刊編集長。)
今後は、「常に問い続ける」という一種の練習や習慣が、人間にとって最も基本的であり最も価値のある活動になっていくだろうと思います。すでに答えがわかっていることは機械〔AI〕に聞けばいい。人の価値があるとすれば、答えのわからない問いに対して、「こうだったらどうなのか」とか、「これはどうなんだろうか」と考え続けていくことです。
正しいことを問うていく、ということに価値が生まれます。それがイノベーションと呼ばれるものだし、探索やサイエンス、創造性だったりするわけです。人の仕事は問いを投げかける、そして不確実性を扱うというものになっていくと思います。
「問い」を考えるための私の思考法について簡単に説明しましょう。〔中略〕
一つのやり方としてヒントになるものは、常識とされている、皆が当たり前だと思っていることに疑問を抱く、そしてそれを覆して考えてみるということです。ほとんどの場合、常識と呼ばれているものは正しいのですが、中にはやはり間違っているものも混ざっています。それを発見できれば、新たな洞察になります。ですから、常識に対して疑問を抱くという習慣を持つことが大事です。それが新たなストーリーや仮説を作っていくということにつながります。
〔中略〕常識を覆して考えてみるということが、今後の未来を考えるときの非常に強力なヒントになると思います。
〔中略〕
未来を構想するプロセスの半分はその着想(アイデア)であり、その残りの半分というのはそれを実現していくためのエビデンス、やり方を探すということなのです。
(出典:『5000日後の世界 : すべてがAIと接続された「ミラーワールド」が訪れる (PHP新書 ; 世界の知性シリーズ)』、ケヴィン・ケリー [著者 (口述)]、大野和基 [インタビュー & 編集]、服部桂 [翻訳]、PHP研究所、2021年。「第6章 イノベーションと成功のジレンマ」の章内の、「AI時代には「問いを考える」ことが人の仕事になる」の項目より)
知識を教える仕事は無くなり、ファシリテーターに変わる
(コンサルタントの話が出たので、ついでにお話させていただくと、)教師や、セミナー講師、コンサルタントなど、「知識を教える仕事」をしている人は、生成AIの登場によって、役割や仕事の内容が大きく変わります。
前述の、投資家の藤野英人さんが掲げている「3つの大テーマと、10の研究テーマ」のなかに、「ダイバーシティ&エデュケーション」(多様性と教育)が入っています(下記参照)。このことにもあらわれているように、「教育の変化」について知っておくことは、投資家にとっても、経営者にとっても、「世の中の大きな流れの変化」を知るうえで重要なことだと思います。
ひふみ投信の「3つの大テーマと、10の研究テーマ」
(1) テクノロジー&サステナビリティ
①グリーン&エネルギー
②スマートインフラ&イノベーション
③省人化&ロボティクス
(2) ソーシャルインパクト&ヘルスケア
④ダイバーシティ&エデュケーション
多様な背景の人々の受け入れ、教育アクセス、ライフロングラーニング、オンライン学習
⑤フード&ウォーターセキュリティ
⑥ヘルスケアイノベーション
⑦デジタルコミュニケーション&プライバシー
(3) グローバルエコノミー&地政学
⑧エコノミー&トレーディング
⑨地政学&セキュリティ
⑩人口動態&高齢化
(出典:YouTube動画「ひふみ目論見倶楽部 スタートします」(36:46~38:09)と、藤野英人『「日経平均10万円」時代が来る!』の第5章第1節の「3つの大テーマと10の研究テーマ」の項目より)
下の動画では、投資家の藤野英人さんが、安宅和人さんをゲストとして招いて、未来について質問しています。藤野さんは安宅さんに対して、「ふつうの人が AI時代に対応するためには、なにをすればいいのでしょうか?」と質問しています。この質問に対して、安宅さんは、「AI時代には、教育のあり方を変える必要がある」という話をされています。(20:42~26:00)
(※安宅和人さんのプロフィール:Zホールディングス シニアストラテジスト。慶應義塾大学 SFC 環境情報学部 教授。元マッキンゼーの経営コンサルタント。イェール大学で脳神経科学の博士号取得。データサイエンティスト協会理事。)
▼ 20:42~26:00また、「AI時代の教育の変化」について、李開復(カイフー・リー)さんは、『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』 という本のなかの、「教育におけるAI」という項目で、次のようなことを語っています。下記の話では、学びの方法や、教師の役割が、どのように変化するのか、ということの具体例が紹介されています。
学校の教室は100年前からほとんど変わっていない。現代の教育の問題点はあきらかだ。生徒は一人一人ちがうのに教え方は画一的なままだ。教育は多額のコストがかかる。教師一人あたりの生徒数を適切な範囲にとどめながら貧しい国や地域に拡大するのは難しい。このような問題を解決し、教育を改革するのにAIは大きな役割をはたせる。
学校の授業は、講義、練習、試験、個人指導からなる。いずれも教師は多くの時間をとられる。しかし充分に進歩したAIがあれば、教師の仕事の大部分は自動化できる。生徒の誤りを正し、一般的な質問に答え、宿題やテストを課し、採点するのはAIがやれる。歴史的人物を登場させて生徒と交流させることもできる。〔中略〕
AIに大きな機会があるのは個別教育だろう。「金雀と銀雀」〔引用者注:本書内の物語の題名〕で描かれたように、生徒一人一人に専任のAI教師をつけられる。キムザクは大好きなアニメのキャラクター、アートマンの指導を受けて楽しく学習する。アートマンはたんなる愉快な友だちではない。勉強不充分なところを努力するようにキムザクを説得し、人間にかわってデータを蓄積する。二四時間待機して好きなときに呼び出せるところなど、人間の教師には不可能だ。
人間の教師はクラス全体を見なくてはいけないが、バーチャルの教師は生徒一人一人を個別に指導できる。特定の発音を訂正したり、かけ算を練習させたり、小論文を書かせたりできる。どんな場合に生徒の目が大きく開くか、あるいはまぶたが垂れてくるかを観察して、千人の生徒にはうまくいかなくても特定の一人の生徒には効果が上がる指導法をみつけられる。たとえばバスケットボールが大好きな生徒にとって退屈な数学の問題は、バスケットボールの競技場を舞台にした問題にNLP機能で書きかえられる。生徒のペースにあわせて宿題の量を調節し、ある項目を完全に習得してから次の項目に移るようにできる。
オンライン教室ではカスタマイズされたバーチャルの教師とバーチャルの生徒を登場させ、的確な問いかけによって授業への関心を高め、生徒の成績を伸ばすことができる。中国で人気の教育アプリでは魅力的なバーチャル生徒(現在は録画されたものだが、将来はAIで生成できる)を登場させることで、人間の生徒の興味と関心を引き出し、学習意欲を高めている。授業だけでなく、カリキュラムの作成、採点などの単純作業はAIにまかせられる。教育場面でのデータが増えるほどAIは子どもたちの学習を容易に、効率的に、楽しくする。
このようにAIが浸透した学校でも、人間の教師がやるべきことはたくさんある。教師の重要な役割は二つだ。第一の役割は、生徒を人間的に指導すること。批判的思考、創造力、共感、チームワークの成長をうながすのは人間の教師だ。生徒が迷っているときに道をしめし、なまけているときに叱り、落胆しているときになぐさめる。知識を教えるという単純作業の負担を減らし、感情知能、創造力、性格、価値観、柔軟性の育成に集中できる。
人間の教師の第二の役割は、AI教師やAIコンパニオンを制御、管理することだ。目標設定を修正し、生徒の必要性にあわせてやる。これには経験と、人間的な知恵と、生徒の能力や夢への深い理解が必要だ。〔中略〕
AIが教育現場の多くの場面を肩代わりすることで、教育コストは下がり、より多くの子どもたちが平等に学ぶ機会を得られるようになるだろう。エリート教育機関に囲いこまれていたトップクラスの教師や教育コンテンツが開放され、コストがゼロに近いAI教師によって広く普及するだろう。一方で経済的に豊かな国や地域では人間の教師を多く育成し(あるいは家庭教師を雇って)、少人数教室を実現したり、専任のメンターやコーチにするだろう。人間とAIの教師は共生可能であり、柔軟な新しい教育モデルをつくれる。AI時代は教育機会を大きく広げ、生徒一人一人の能力を引き出すはずだ。
(出典:『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』、李開復(カイフー・リー)、文藝春秋、2022年。「未来3 テクノロジー解説」の節内の、「教育におけるAI」の項目より)
上記の文章で、李開復(カイフー・リー)さんが言っている「教育の変化」については、大前研一さんも、同じようなことを言っています。具体的には、大前研一さんは、教師の役割は、「ティーチャー」(知識を教える役割)から、「ファシリテーター」(一緒に答えを見つけていく役割)へと変わっていく、と言っています。
(※大前研一さんの経歴:ビジネス・ブレークスルー大学学長。マッキンゼー日本支社の元社長。MIT(マサチューセッツ工科大学)大学院原子力工学科で博士号を取得。)
大前研一さんは、現在のような「答えの無い時代」における、教育のあるべき姿について、下の動画で語っています。具体的には、「ティーチャー(教師)が、答えを教える教育」から、「学生とファシリテーターが、みんなで一緒に答えを見つけていく学び」へと、学びのかたちを変化させる必要がある、と語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
(※ファシリテーターとは、「会議やミーティングを円滑に進める」人のことです。具体的には、「参加メンバーの発言を促しながら、多様な意見を瞬時に理解・整理していき、重要なポイントを引き出しつつ、議論を広げ、最後には議論を収束させ合意形成をサポートする」という役割をします。(出典:グロービスキャリアノートの記事「ファシリテーションとは?役割と必要なスキル、具体的なやり方」より)。)
▼大前研一さん:ビジネス・ブレークスルー大学学長。マッキンゼー日本支社 元社長
0:04
デンマークの例を紹介します。〔中略〕
0:16
デンマークは「労働市場を改革しなきゃいけない」と考えました。「でも、21世紀は答えが無いんだよね」と。
決まった答えが無い時代なのだから、「答えを教える」という教育から「考える教育」にシフトしようと、教師協会が言い始めました。
そして、学校から「ティーチャー」(教師)という言葉を追放する、ということを最初に言い始めました。
なぜかというと「ティーチ」(教える)という言葉は、「答えがある」ことを前提としているからです。〔中略〕
0:52
「答えの無い時代に教師ができることは、生徒と一緒に答えを見つけに行くことだ」と。
学校というのは、(「ティーチャー(教師)が答えを教える場」ではなく、)「生徒が学ぶ(ラーンする)場だ」ということですね。
「じゃあ、教師はなにをやるの?」と質問すると、デンマークの教師たちは、「教師の役割は、ファシリテーターに変わるんです」と言っていました。
「26人の教室なら、26通りの答えがあっていいんだ。それをみんなで議論しながら、1つにまとめていく。そして、みんなが『これだ』と思ったことを実行する」
このプロセスを、つまずくことなく前に進めていく役割をするのが、「ファシリテーター」。デンマークの教師たちは、「これが教師の役割である」と言っていました。
1:37
そのように教育のあり方を変えた効果は、とても大きいものでした。デンマークの1人当たりGDPは、当時に比べて2.5倍になりました。
日本は、その当時のままです。
デンマークのノーベル賞受賞者は、13人。デンマークは、人口600万人ですから、もし、デンマークの人口が、日本と同じだったと仮定すると、ノーベル賞受賞者は、262人になります。
デンマークのユニコーン企業は、8社あります。グローバル企業としては、
- A.P.モラー・マースク(コンテイナー世界一)
- ヴェスタス(風力発電機)
- カールスバーグ(ビール)
- レゴ(玩具)
このレゴが最高なんです。子どもがレゴで遊ぶことで、なにを作るかを頭のなかに描いて、それを組み立てていく。「ゼロからイチ」の一番良い教育道具はレゴです。だから、レゴは教育玩具に分類されています。世界一のおもちゃ会社はレゴなんです。
デンマークは、こういう会社を世界に向けて生み出している。
2:53
デンマークの新興企業としては、ユニティー・テクノロジーズ(Unity Technologies)があります。(デンマークの首都である)コペンハーゲンで生まれた、ゲームの制作に欠かせないミドルウェアを提供する会社です。「ポケモン GO」の制作にも使われています。自動運転技術の開発にも、Unity(ユニティー)が使われています。
それから、Zendesk(ゼンデスク)。これは、クラウド型カスタマーサービスプラットフォームです。世界140カ国の4万社に利用されています。3億人以上が利用するカスタマーサポートを担うプラットフォームです。
Unity(ユニティー)も、Zendesk(ゼンデスク)も、デンマークで生まれましたが、デンマークの資本市場では十分な資金調達がむずかしかったため、シリコンバレーに引っ越して、アメリカの株式市場であるNASDAQ(ナスダック)に上場しました。
大前研一さんは、「答えを教える教育」(ティーチャー)から、「みんなで一緒に答えを見つけていく学び」(ファシリテーター)へと、学びのかたちが変化している、ということを下の動画でも語っています(3:40~5:48)。
また、会社におけるリーダーシップも、かつての「答えがあった時代」の「部下を命令どおりに動かす」というリーダーシップから、「答えの無い時代」に対応するための「ファシリテーター」型のリーダーシップに変わっていく必要がある、ということを語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
▼大前研一さん:ビジネス・ブレークスルー大学学長。マッキンゼー日本支社 元社長
3:40
自分の頭の中にある構想、思い描いた世界を「見える化」し、AIやロボットにはできない新しい付加価値を創出する。
日本人の知的能力が劣っているわけではなくて、これまでは、「欧米に答えがある」という前提でやってきた。〔現在のような「答えの無い時代」は、その前提ではうまくいかなくなっている。〕
「21世紀は答えの無い世界だ」と、北欧が一番最初に気がつきました。
1994年ぐらいに、デンマークで「学校教師は、教えるのをやめよう」と言われるようになりました。「ティーチャー(教師)という言葉を、教室から追放しよう」という運動が起こり、デンマークやフィンランドに波及していきました。
その理由は、「答えが無いことを教えることはできないから」です。
〔中略〕
4:42
「26人生徒がいれば、26通りの考えがあっていいんだ」と。
4:49
そこから、人間の集団におけるリーダーシップという問題が出てきます。(いろいろな人のいろいろな意見)を聞いて、「誰のアイディアが一番いいのか」を議論していく。そして、それを集約していく。
従来の「先生」の役割は、「ファシリテーター」という役割に変わり、前述のような、「生徒たちの学びの過程」を手伝ってあげる(ファシリテートする)という役割に変わりました。
5:15
ですから、みなさんも会社のなかで、みんなの違うアイディアをいっぱい出してもらったうえで、「うちの会社にとって、どれが一番いいのか?」ということを次第に収斂させて、1つの行動にまとめていく、というプロセスが必要になります。
答えをパッと言っちゃうよりも、会社のなかのいろいろな意見から、みんなが「なるほど、これだ」と思えて、「自分たちもやろう」と思えるものをひっぱり出していくのが、21世紀のリーダーシップの典型的なスタイルになると思います。
「人間の役割が、ファシリテーターとしての役割に変わっていく」ということについて、マンガ編集者の佐渡島庸平さんは、「これまでの編集者の仕事の技術が、AIによって置き換えられていくなかで、これからの編集者には、コーチングや、ファシリテーターとしての役割が求められている」という話を、下の動画の「41:24~42:40」のところで語っています。(※佐渡島庸平さんは、『宇宙兄弟』、『ドラゴン桜』、『働きマン』、『バガボンド』など、有名なマンガの数々を、編集者として支えてきた人です。)
▼ 41:24~42:40また、「教育における、AIと人間の役割分担」については、人工知能の研究者であり経営者でもある野村直之さんが、下記のように述べています。(下記の引用文は、野村直之さんの『実践フェーズに突入 最強のAI活用術』という本で語られている話です。)
(※野村直之さんのプロフィール:人工知能の研究者、経営者。MIT(マサチューセッツ工科大学)では、「人工知能の父」マービン・ミンスキーと一時期同室。メタデータ株式会社 社長。法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼担教員。)
中学の数学の勉強に1対1でとことん付き合うAIを使って大半の生徒が3年分の数学を20日で学習できたとする、AI活用塾の成功ストーリーがあります。つまずき方に関する膨大なバリエーションと照合して、目の前の生徒一人ひとりの状況を診断し、処方箋に基づいて辛抱強く課題とヒントを出し続けるというのは、AIの得意技です。人間の教師は、全人格的な教養や人間性、コミュニケーションの機微などの教育にシフトすることになりそうです。
(出典:『実践フェーズに突入 最強のAI活用術』、野村直之、日経BP、2017年。第6章内の「ベーシックインカムでは問題は解決しない」の項目より)
▼ 第2部
新しい経営指標
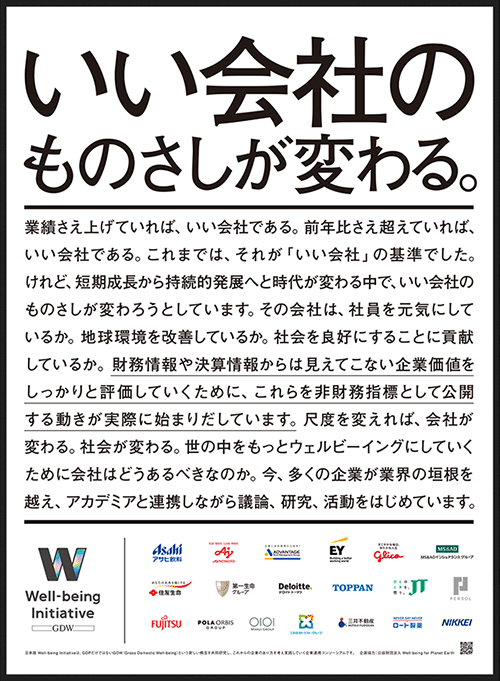
いい会社のものさしが変わる。
業績さえ上げていれば、いい会社である。前年比さえ超えていれば、いい会社である。これまでは、それが「いい会社」の基準でした。けれど、短期成長から持続的発展へと時代が変わる中で、いい会社のものさしが変わろうとしています。その会社は、社員を元気にしているか。地球環境を改善しているか。社会を良好にすることに貢献しているか。財務情報や決算情報からは見えてこない企業価値をしっかりと評価していくために、これらを非財務指標として公開する動きが実際に始まりだしています。尺度を変えれば、会社が変わる。社会が変わる。世の中をもっとウェルビーイングにしていくために会社はどうあるべきなのか。今、多くの企業が業界の垣根を越え、アカデミアと連携しながら議論、研究、活動をはじめています。
(※上の画像の広告は、日本経済新聞に掲載された、日本版ウェルビーイングイニシアチブによる広告です。画像と文章の出典:「Well-being Initiative 2022年活動報告」のページより)
ここまで、「AIの登場による長期志向への転換」をテーマにしてお話してきました。
ここからは、その「転換」に関連する、「世の中の大きな流れの変化」として、「経営指標の変化」をテーマにしてお話していきます。具体的には、世界中の投資家や経営者が注目している「新しい経営指標」や、それにまつわるキーワード(用語)を紹介していきます。それらの指標やキーワードを知ることで、世の中の流れの変化をとらえて、投資判断や経営判断に活かすことができるでしょう。
これから紹介していく指標や、それに関連するキーワードは、下記のとおりです。これらの新しい指標やキーワードの根底にある考え方の共通点は、「長期間にわたって継続的に良い業績を出し続けることを目指すためのものである」ということです。
- ウェルビーイング
- GDW(国内総ウェルビーイング、国内総充実)
- CWO(最高ウェルビーイング責任者)
- 人的資本経営
- ESG(環境、社会、企業統治)
- インパクト加重会計
- サステナビリティ(持続可能性)
- ステークホルダー資本主義
- ダイベストメント(投資資金の引き揚げ)
- ソーシャルネイティブ
(※ここで紹介する指標やキーワード(用語)は、良くも悪くも「マーケティング用語」であるという側面があります(これらの言葉自体が、一種の「商品」になっています)。ですので、これらの用語を金科玉条のように、無批判に良いものだと信じ込むことには危険がともなうのでご注意ください。)
ものさしを変えれば、社会が変わる
上で紹介した画像のなかに、「いい会社のものさしが変わる」という言葉がありました。ここで言う「ものさし」とは、「企業価値を測る指標」のことです。
「ものさし」(企業価値を測る指標)として、とくに重要なのは、財務諸表にまつわる指標です。なぜなら、財務諸表にまつわる指標は、「会社が目指すべき目標」に大きな影響を与えているからです。会社は、その「目標」にしたがって経済活動をおこなっています。そして、会社がおこなう経済活動は、社会に対して大きな影響を与えます。つまり、ある意味で、財務諸表にまつわる指標を変えることは、「社会全体として目指すべき目標」を変えることでもあります。そのため、財務諸表にまつわる指標を変えることは、社会を変えることでもあります。
ウェルビーイングや、人的資本、ESG(環境、社会、企業統治)に対する取り組みについてのデータなどの、いわゆる、「非財務情報」を測る「ものさし」は、ひと昔前まで存在しませんでした。そのため、たとえ会社がどれだけ、ウェルビーイングや、人的資本、ESG に対する取り組みをしていたとしても、「経済的には価値が無い」と判断されてしまっていました。
ですが、現在では、そうした「非財務情報」を測るための「ものさし」が生まれつつあります。
ウェルビーイングや、人的資本、ESG(環境、社会、企業統治)などの「非財務情報」を測る「ものさし」(指標)があれば、それらの指標を向上させることが、「会社が目指すべき目標」になります。そうなれば、会社は、その「目標」にしたがって経済活動をおこなうようになります。それによって、ウェルビーイングが広まり、ESGに対する取り組みが増え、人がたいせつにされる社会になっていくでしょう。
このように、「ものさし」(企業価値を測る指標)を変えることは、社会を変えることなのです。
ESGの世界的権威であるジョージ・セラフェイムさんは、「非財務情報」を測る「ものさし」について、次のように語っています。(※「インパクト加重会計」については、後述します。ここで言う「インパクト」というのは、「環境や、顧客や、従業員などに与える影響」というような意味です)。
評価のモノサシがあれば、大きなことも考えられる。例えば、政府がインパクト加重会計というモノサシを使い、企業のなした害悪に課税したり、逆にプラスのインパクトに対して直接的な経済的インセンティブを与えたりすることも想像できる。またインパクト加重会計は投資家・消費者・就業者としての我々に、究極の比較ポイントを与えてくれる。投資先・購入先・就職先の企業を選ぶ際、それらの数値から総合的に判断すればいい。
〔中略〕
私は、上記のすべてが大きな変化を起こすことにつながると心から信じている。インパクト透明性は、まさに資本主義をつくり直す可能性を秘めている。利潤追求が問題を生むのではなく、それが世界に問題解決をもたらすように変えていけば、我々は成功の意味を再定義し、おカネだけではなく、人が一生の間に生み出したプラスのインパクトを成功のモノサシにすることができる。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第3章 透明性と結果責任 : もはや隠し事は不可能」の章内の、「インパクト加重会計がゲームチェンジャーとなる」の項目と、「次のステップは何か」の項目より)
「伊藤レポート」の作成者として有名な、伊藤邦雄さん(一橋大学CFO教育研究センター長)という方がおられます。(※「伊藤レポート」の詳細については、後述します)。その伊藤邦雄さんも、上記のような新しい「ものさし」(非財務情報を測る指標)の重要性について、下記のようなことを語っています。
- 企業価値を高めたり、企業価値の大きさを投資家に伝えたりするための、非財務情報(ESGや、人的資本、持続可能性(サステナビリティ)に対する取り組みについての情報)の重要性が高まっている。
- 非財務情報を評価するための新しい指標(評価手法)の必要性が高まっている。
上記の件について、伊藤邦雄さんは、『企業価値経営 第2版』という本のなかで、下記のようなことを述べておられます。
非財務・ESG情報に目配りした企業評価
経営の大原則である企業価値創造という点で,地殻変動が起こっていることに留意すべきである。それは,企業価値の決定因子が有形資産から無形資産へと転換していることだ。無形資産はそのほとんどが非財務情報であり,厄介なことに財務情報を主として開示してきた伝統的なバランスシートには,無形資産のほとんどが表示されず,オフバランスとなっていることである。
このため,企業価値を評価し,分析し,創造していくためには,無形資産や非財務情報にも目配りする必要が生じている。会計学やファイナンスのテキストは,伝統的にこうした大変化に十分に対応することが困難だった。
〔中略〕
非財務情報にも目配りする理由は他にもある。
企業価値を評価する側である機関投資家の間で,「持続可能性」(サステナビリティ)という観点から,近年,ESG(環境:Environment,社会:Society,ガバナンス:Governance)に着目した新たな投資スタイルが台頭してきている。中長期の投資家は保有期間が長いだけにリスクが顕在化する確率も高い。投資期間中に,社会環境や自然環境が変化する可能性が高いため,そうした環境変化に投資先企業が対応し,持続可能かいなか,ビジネスリスクが仮に顕在化しても再生できるだけのレジリエンス〔復元力〕を持っているのかに鋭い関心をもつ。
こうしたESGをめぐる動きは近年,企業経営にも世界的に広がってきている。ESGに真剣に向き合わなければ,投資家のみならず様々なステークホルダー〔利害関係〕からの信認を失い,企業の持続可能性が危うくなってしまう時代に入っているからだ。
このため企業側もESGに関する有用な非財務情報をいかに開示するかが問われている。〔中略〕そうしたレーティングを投資意思決定に組み込む機関投資家も増えつつあるため,ESGに関する情報をいかに開示するかは企業経営上,非常に重要なテーマとなっている。
〔中略〕
気候変動問題と資本主義の見直し: サステナビリティと向き合う
こうしたESGやサステナビリティをめぐる動きを加速する,さらに深部での変化があることを忘れてはならない。それは,資本主義を見直す動きである。ミルトン・フリードマンがかつて唱え,そして資本主義のエンジンとなった,利益を最大化することが社会的責任であるとの見方の妥当性が問われ始めているのである。日本は伊藤レポートでの分析や提言にあるようにそうではなかったが,欧米は株主第一主義に走りすぎたとの反省から,この2~3年で「ステークホルダー資本主義」が叫ばれ,台頭してきている。
こうした動きを加速しているのが,ESGのEの中でも最も深刻なテーマである気候変動問題である。〔中略〕
気候変動問題に向き合い,外部不経済を緩和するには,企業側も投資家・金融機関も「共通言語」をもつ必要がある。つまり,「共通言語」となる情報開示を活用して双方が,企業が排出する二酸化炭素の実態を把握し,投資・融資行動や企業活動の是正につなげることが求められている。〔中略〕
普遍的テーマとしての企業価値
〔中略〕経営の普遍的テーマである「企業価値」に向き合い,企業価値をどういう情報を用いてどのように評価するのか,そしてそうした評価を経営戦略の策定にどのように反映し,企業価値をどのように創造していくのか〔中略〕
〔中略〕いかに有用な情報を活用し,適切なプロセスを駆使して企業価値を評価するかが重要である。その点で,企業価値評価(バリュエーション)という領域での必要な知識を欠くと,企業の競争力にはかり知れない格差を生じかねない。まさに「デジタル・デバイド」ならぬ,「バリュエーション・デバイド」である。〔中略〕
〔中略〕無形資産やESGや非財務情報の重要性がかつてないほどに高まっていることから,そうしたテーマにも射程を広げて企業価値と向き合うことが重要となっている。
〔中略〕
これまで述べてきたように,財務・会計情報だけでは企業価値評価は十分ではない時代に入った。投資家は,いまや無形資産・非財務情報・ESG情報を企業評価に取り入れつつある。こうした新たな企業評価手法は現在も進化しつつある。
〔中略〕
企業価値経営をめぐるテーマは〔中略〕財務に加えて,「非財務」に関する情報分野がさらに拡大した。「非財務」を「将来財務」と読み替えるべきだとの論調も高まっている。それに関連して,サステナビリティ(持続可能性)をめぐるテーマが深化し,企業経営におけるそのトランスフォーメーション(SX)〔サステナビリティ・トランスフォーメーション〕の重要性が格段に上昇した。
さらに今日,企業価値の主要な決定因子となった無形資産の中核に位置する「人的資本」の重要性が世界的に認識されるようになり,かつその情報開示に投資家をはじめとするステークホルダーが並々ならぬ関心を持つに至っている。
(出典:『企業価値経営 第2版』、伊藤邦雄、日経BP、2023年。巻頭の「はしがき」より)
ちなみに、上記の文章のなかに出てきた「ステークホルダー資本主義」というのは、「会社が、株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会、環境など、幅広い利害関係者(ステークホルダー)の利益を重視し、長期的な価値創造を目指すという資本主義のあり方」のことです。『ステークホルダー資本主義』という本では、次のように説明されています。
このシステム〔ステークホルダー資本主義〕では、経済、社会におけるすべてのステークホルダー〔利害関係者〕の利害が考慮され、企業は短期的な利益だけでなく、中長期的な成長を最大にしようとする。政府は機会の均等と公平な競争条件を約束する。さらに、システムがサステナブル(持続可能)であり続けること、そしてあらゆる人を包摂することについて、すべてのステークホルダーが等しく貢献し、同時にシステムの恩恵を平等に受けられるよう、管理する役割をも果たす。
(出典:『ステークホルダー資本主義 : 世界経済フォーラムが説く、80億人の希望の未来』、クラウス・シュワブ、ピーター・バナム、日経ナショナルジオグラフィック、2022年。「第8章 コンセプト」の冒頭より)
伊藤穰一さんも、新しい「ものさし」(非財務情報を測る指標)の重要性について、同様のことを言っています。伊藤穰一さんは、「お金で測れない価値」(非財務情報)を測ることができるような「会計の未来」(非財務情報を測ることができる会計指標)について、下の動画の「13:17~14:43」のところで、下記のようなことを語っています。(※伊藤穰一さんのプロフィール:元MITメディアラボ所長。千葉工業大学 学長)。
(※下の動画の当該部分は、伊藤穰一さんの発言の要点だけを編集して手短にまとめた映像になっています。その影響で、ところどころ、すこし意味がわかりにくいところがあります。そのため、その動画を書き起こした下記の文章では、わかりやすさを優先して、言葉を補ったり、意訳したりしている部分が多くなっています。)
13:17
▼伏見京子さんからの質問
「お金で測れない価値」が顕在化されてくると、経済システムを大きく変える必要が〔あるのではないでしょうか?〕
13:25
▼伊藤穰一さん:元MITメディアラボ所長、千葉工業大学 学長
〔ESG(環境、社会、企業統治)や、人的資本などの、「お金で測れない価値」も包含した新しい経済システムのことを、〕「会計の未来」と、僕は呼んでいます。
〔中略〕
13:54
〔「お金で測れる価値」を測定するための指標については、〕会社を運営するための会計システム〔指標〕があって、最終的に、その会計データを財務諸表(BS(貸借対照表)と、PL(損益計算書))としてまとめて、誰でも読めるものにします。
〔それと同じように、ESGや、人的資本などの、「お金で測れない価値」を測定するための指標についても、〕会計システム〔経営指標〕が標準化されて、〔その指標のデータが〕オープンになると〔誰でもかんたんに、その指標のデータを取得できるようになると〕、〔ESGや、人的資本などの、「お金で測れない価値」についてのデータを〕解析しやすくなります。
〔その結果、たとえば、〕、「この会社とこの会社が合併した場合のデータ」や、「ESGの観点から見た場合のデータ〔ESG情報開示〕」や、「社員の目線から見た場合のデータ〔人的資本の情報開示〕」〔などの、「お金で測れない価値」についてのデータを分析しやすくなります。〕
〔そういった、「お金で測れない価値」についてのデータを含む、〕いろんな情報を、本来、会社は持っているはずです〔会社は、そうした「お金で測れない価値」についてのデータを保有しているはずです〕。〔中略〕
ですが、社会的には〔その会社のステークホルダーの人たち(利害関係者の人たち)が、〕会社に対して、そうした〔「お金で測れない価値」についての〕質問をしたくても、〔ESGや、人的資本などの、「お金で測れない価値」を測定するための指標が無いために、〕会社側は、そういったデータを出すことができない状態になってしまっています。
そうした、〔「お金で測れない価値」を測定するための〕会計基準など〔の経営指標〕が変わることで、もっと複雑な情報〔「お金で測れない価値」を含んだ企業価値のデータ〕を、オープンに〔誰でもかんたんに〕知ることができるようになるといいなと思います。
ちなみに、上の動画での、伊藤穰一さんの言葉の背景には、「会社を運営するシステム(会計基準)を変えることで、「お金で測れない価値」を測定したり伝達したりすることができる「会計の未来」を実現したい」という考えがあるように思えます。そのような考えの背景には、伊藤穰一さんのエッセー「還元に抗うマニフェスト : 機械と共に歩む複雑な未来を設計する」のなかで語られている、「社会全体として目指す目標を変えることで、社会システムに変化を起こすことができる」という考え方があるのではないかと思います。
(※会計基準は、「会社が目指すべき目標」に大きな影響を与えています。会社は、その「目標」にしたがって経済活動をおこなっています。そして、会社がおこなう経済活動は、社会に対して大きな影響を与えます。つまり、ある意味で、会計基準を変えることは、「社会全体として目指すべき目標」を変えることでもあります。そのため、会計基準を変えることは、社会を変えることでもあります。)
そのエッセーのなかで、伊藤穰一さんは、『世界はシステムで動く』という本で示されているアイディアを借りて、「あるシステムの構造(仕組み)に変化を起こしたいときは、目標を変えることが効果的だ」というような意味のことを言っています。
そのような、「社会全体として目指す目標を変えることで、社会に変化を起こす」という考え方は、この記事のテーマである、「社会全体として目指す新しい目標(長期志向の「新しい経営指標」)を設定することで、社会を良い方向へ変えていくことができる」という考え方と通じるところがあります。
(※伊藤穰一さんのエッセーで語られている「目標を変える」というアイディアは、ドネラ・H・メドウズさんの著書『世界はシステムで動く : いま起きていることの本質をつかむ考え方』の、第7章で語られているアイディアです。その第7章では、あるシステムの構造(仕組み)に変化を起こしたいときに、「どういったものごとを変えると、より効果的に変化を起こすことができるのか」、ということについて、12個の項目を挙げて説明されています。その12個のうちのひとつに「目標(ゴール)」という項目があります。)
ここからは、新しい「ものさし」として、ウェルビーイングや、人的資本、ESG(環境、社会、企業統治)などの「非財務情報」や、それらを測る指標について、お話していきます。
ただ、その話をする前に、どうしても触れておかなければいけないことがあります。それは、GDP(国内総生産)の負の側面についてです。「これまでの古い指標」であるGDPが生まれた背景や、その問題点を知ることで、「これからの新しい指標」がなぜ必要とされているのかという背景や、その重要性が、より理解しやすくなるかと思います。
GDPは人を幸せにしない「戦時の指標」
現在、GDP(国内総生産)は、重要な経済指標としてあつかわれています。ですが、GDPには、致命的な問題点があります。そのため、「GDPは、社会の向かう先を判断するための指標としては、ふさわしくない」という批判もあります。そもそも、GDPの考案者の一人であるサイモン・クズネッツさん自身が、「GDPは人々を幸せにするための指標ではない」というような意味のことを言っています。そうしたことから、今の世界的な潮流として、「GDPを超えて」(ビヨンドGDP、脱GDP)という言葉が、重要なキーワードのひとつになっています。
経済学者のダイアン・コイルさんは、『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』という本のなかで、「GDPは人々の豊かさを測る指標ではない」ということについて、次のように語っています。
(※ダイアン・コイルさんの経歴:経済学者。ケンブリッジ大学教授。ハーバード大学で経済学の修士号と博士号を取得。イギリス財務省のアドバイザー、BBCの監督機関の会長代理などを歴任。経済学への貢献によって大英帝国勲位を受勲。)
しっかりと認識しておいてほしいのは、GDPが生活の豊かさを測る指標ではないという事実だ。よく指摘されるように、GDPの値は訴訟などの「ネガティブな」活動によっても増加する。ハリケーンや洪水の被害で橋や家の修繕が必要になれば、その費用もGDPに加算される。GDPは単に産出額を測るものであり、人々の豊かさは考慮の外なのだ。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、47ページより)
世界経済フォーラム(通称、ダボス会議)のウェブサイト内のいくつかのページには、下のような画像が掲載されています。下の画像には、ノーベル経済学賞の受賞者であるジョセフ・スティグリッツさんの写真とともに、「GDPでは、経済活動を正確に計測することはできず、幸福度(ウェルビーイング)を正確に計測することもできない」という言葉が書かれています(意訳です)。(原文:「GDP is not a good measure of economic performance, it’s not a good measure of well-being」)。
(※下の画像が掲載されている世界経済フォーラムのウェブページの一例としては、たとえば、「『GDPでは進歩を正確に計測できない』と語る、ダボス会議の経済学者たち」のページがあります(この「日本語のページ名」は意訳です。原題:「GDP a poor measure of progress, say Davos economists」)。)
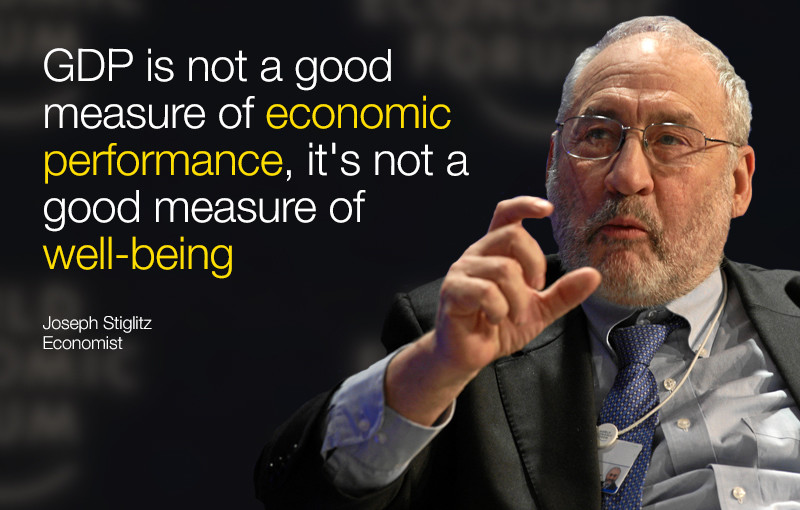
OECD(経済協力開発機構)の「GDPを超えて : 幸福度を測るOECDの取り組み」という文章では、GDPが考案された目的や、当時の時代背景が、次のように紹介されています。
GDP が考案されたのは,1930 年代の大恐慌から第二次世界大戦に至る時期で,大恐慌の間に失われた経済規模や戦争を遂行する上で必要な軍事調達をどの程度できるかを把握する目的で作成された.
(出典:村上由美子、高橋しのぶ「GDPを超えて : 幸福度を測るOECDの取り組み」、『サービソロジー』6巻4号、サービス学会、2020年1月、8ページより)
下の動画は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスが制作した、「GDPってなに?(GDPが悪いものである理由)」というような意味の題名が付いている、GDPについての解説動画です。
(※ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスは、経済学をはじめとする社会科学に特化した世界最高峰の大学のひとつです。)
1930年代の大恐慌の時代にGDPが生まれた背景や、GDPの考案者の一人であるサイモン・クズネッツさんや、ロバート・ケネディさんが、「GDPやGNPは、人間性が欠けている指標である」と批判していたことについて紹介している映像が、下の動画の「1:16~1:43」のところで視聴できます。(※GNP(国民総生産)は、GDP(国内総生産)と同じように、国の経済活動の規模を測る指標です)。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
1:16
なぜGDPが生み出されたのでしょうか?
GDPは、1930年代に起こった世界恐慌に対処するために、アメリカとイギリスが、国の生産力を把握するための指標として開発したものです。
その主要な生みの親の一人であるサイモン・クズネッツは、当初から、「GDPは、社会的進歩や、経済的福祉を測る尺度として、適切な指標ではない」と主張していました。
また、アメリカの司法長官であったロバート・ケネディは、「GNPでは、人生を価値あるものにするものを計測することはできない〔GNPは、価値の無いものを計測する指標だ〕」と主張していました。
(※下の動画は、英語の動画ですが、日本語字幕を表示させることができます。
※スマホのYouTubeアプリの場合は、映像の上をタップして、右上の歯車のアイコンを押してから、「字幕」→「自動翻訳」→「日本語」を選択すると、日本語字幕が表示されます。
※パソコンの場合は、映像の右下にある「字幕」アイコンを押してから、歯車のアイコン(「設定」)を押して、「字幕」→「自動翻訳」→「日本語」を選択すると、日本語字幕が表示されます。)
さきほどの、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの動画のなかで紹介されていた、アメリカの司法長官であったロバート・ケネディさんの演説は、1968年3月18日にカンザス大学で行われた演説です。さきほど紹介したように、その演説のなかで、ロバート・ケネディさんは、GNPを批判しました。(彼が指摘したGNPの欠点は、同様の指標であるGDPが抱えている欠点でもあります。)
(※こちらのリンクで、その演説の原文(英語)を見ることができます。リンク先の文章のなかの、22番目の段落(パラグラフ)が、「GNP批判」の部分です。このリンク先のウェブサイトは、ロバート・ケネディさんの兄であり、第35代アメリカ大統領である、ジョン・F・ケネディさんについてのウェブサイトです。)
下記の引用文は、その演説で、ロバート・ケネディさんがGNPを批判している部分を意訳したものです。(ちなみに、ロバート・ケネディさんは、この演説の2日前に大統領選挙への出馬を決めたばかりでした。ですが、この演説の約3ヶ月後に、彼は暗殺されてしまいました。)
(※下記の文章は、実際のロバート・ケネディさんの演説での発言を、ところどころ意訳した文章になっています。そのため、大意は同じであるものの、原文の意味と完全に同じではありません。下記の文章は、調査会社ギャラップのトム・ラスさんの本からの引用です。)
「私たちは、すばらしい地域社会に守られて生活しています。その地域社会は物質的な財の蓄積によって構築されています。
財の蓄積は、国民総生産で表されますが、国民総生産を増やすために、大気汚染やタバコの広告、交通事故に向かう救急車が増えています。
国民総生産が増えるに従い、ドアにもう1つ複雑な鍵が必要になり、そんな鍵までこじ開けてしまう犯罪者を収容する刑務所も増え続けています。
国民総生産が増えるに従い、無秩序に拡大する郊外の住宅で森が破壊され、すばらしい自然が失われてきています。
同時に、国民総生産の増加は、ナパーム弾や核弾頭による犠牲、市街地で暴徒と化した人々と戦うための装甲車まで必要とする状況を招いています。
国民総生産の増加は、ライフル魔ホイットマンが所持していたライフル銃、殺人鬼スペックが所持していたナイフ、子どもにおもちゃを売るためのバイオレンス映像を流し続けるテレビ番組も増やしています。
これほど大きな犠牲を払っているにもかかわらず、わが国の国民総生産によって、子どもの健康、教育、遊びの楽しみなどが保証されるにはいたっていません。
国民総生産には、詩の美しさや結婚生活の絆は含まれないのです。私たちの国政を論じる議論の知性や公僕の誠実さも含まれないのです。
国民総生産には、ユーモアや勇気も含まれません。私たちの智恵や学び、国に対する献身的な思いやりや愛情も含まれないのです。
国民総生産は、あらゆるものを測る指標となっているにもかかわらず、その中に、私たちの人生を価値あるものにしているものは1つも含まれていないのです」
(出典:『幸福の習慣 : 世界150カ国調査でわかった人生を価値あるものにする5つの要素』、トム・ラス、ジム・ハーター、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2011年、154~155ページより)
下の動画は、1968年3月18日にカンザス大学で開催された、ロバート・ケネディさんの演説の短いダイジェスト映像です。演説の雰囲気がどんなものだったのかを感じることができると思います。
▼ 0:00~1:34上の動画の演説の全体を録音した音声は、下の動画で聞くことができます。
さきほど、この演説のなかで、ロバート・ケネディさんがGNPを批判している部分の文章を、トム・ラスさんの本から引用して紹介しました。その「GNP批判」の部分の音声は、下の動画の「16:19~18:09」のところで聞くことができます。(ただ、さきほど紹介した引用文は意訳なので、大意は同じであるものの、実際の演説内で語られている内容(原文)の意味と完全に同じではありません)。
また、さきほどの、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの動画のなかで紹介されていた演説の部分は、下の動画の「17:54~17:59」のところで聞くことができます。
▼ 16:19~18:09世界経済フォーラム(通称、ダボス会議)の創始者であるクラウス・シュワブさんは、『ステークホルダー資本主義』という本で、サイモン・クズネッツさんが、GDPを考案することになった歴史的背景や、クズネッツさんが当時からGDPの問題点について警告していたことについて、次のように語っています。
今日の世界経済というパズルを一緒に解く相手として、恐らくサイモン・クズネッツほどふさわしい人物はいないだろう。クズネッツは旧ロシア生まれの米国人経済学者で、1985年に死去している。
〔中略〕ノーベル賞を受賞したこの学者の教えをもっとよく聞き入れていたら、私たちが現在直面している諸課題がこれほど困難な問題になっていなかったであろうと強く思う。
実際のところ、クズネッツは80年以上前、GDPは経済政策を立案するには欠陥のあるツールだと警鐘を鳴らしている。ただ皮肉にもその数年前、まさにそのGDPという概念を初めて作り出し、それが神聖な目標となるのに一役買ったのは彼自身であった。
〔中略〕
今日、私たちは、もっと厳密な分析を行ってこなかったこと、あるいは、考え方があまりにも独断的であったことの報いを受けている。私たちがGDPの成長こそ最優先の目標だと考えるようになったのと同時に、成長は失速してしまったのだ。経済がこれほど発展したことはなかったが、同時に不平等がこれほど悪化したこともない。環境汚染の減少を期待するどころか、私たちは今やグローバルな環境危機の真っただ中にいる。
〔中略〕
自由貿易の精神と資本主義の原則にも助けられて、投資、イノベーション、生産、貿易の好循環が起こり、それによって米国は、一人当たりのGDPで、世界で最も豊かな国になったのだ。
しかし「狂騒の20年代」のめくるめく経験は、やがて悲惨な大恐慌に取って代わられる。1929年には、好景気に沸く米経済は制御できない状況に陥っていた。〔中略〕その結果、1929年10月下旬に株式市場が暴落し、世界中で連鎖反応を引き起こした。
〔中略〕
米国の政策立案者たちは、どうすればこの危機を食い止め、終わらせることができるかについて懸命に取り組んではいたが、実のところ経済状況がどのくらい悪いのか、という根本的な問題に対する答えを持っていなかった。経済指標は十分でなく、今日私たちが経済を評価する尺度となっているGDPは、まだ発明されていなかった。
ここで登場したのがサイモン・クズネッツだ。〔中略〕クズネッツはGNI/GNPと密接に関連するGDPの基となる概念を生み出した〔中略〕
それは天才のひらめきだった。他のエコノミストたちは、1930年代のその残りをかけて、この経済生産の尺度を標準化することに力を注いだので、1944年に第二次世界大戦後の国際金融体制を作り上げたブレトンウッズ会議が開催される頃までには、GDPが経済の規模を測る主要なツールとして認められるようになった。
〔中略〕
これ以降、GDPは、世界銀行やIMF(国際通貨基金)の国別報告書に見られる指標となっていった。GDPが成長しているときは国民や企業に希望を与えるし、GDPが減少傾向にあるときは、政府はそれを上昇に転じさせるべくあらゆる手段を講じる。それまで、様々な危機や挫折があったものの、世界経済は全体として成長の物語だった。だから、成長は善いことだという考えが常に幅を利かせてきたのである。
しかし、この物語には、つらい結末がある。私たちがサイモン・クズネッツの警告にもっと耳を傾けていたら、そのことを予見できたかもしれない。1934年、ブレトンウッズ合意が成立するはるか前に、クズネッツは米議会に対して、GNP/GDPにあまりとらわれすぎないようにと警告していた。彼は「国の幸福(ゆたかさ)というのは国民所得の尺度では推測できない」と言った。この点において彼は正しかった。GDPは消費については教えてくれるが、幸福については教えてくれない。生産については教えてくれるが、環境汚染や資源の利用については教えてくれない。政府の支出や民間投資については教えてくれるが、生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)については教えてくれないからだ。オックスフォード大学の経済学者ダイアン・コイルは、2019年8月に行ったインタビューで、実のところGDPは戦時の指標だと語っている。戦時中に持てる経済力で何をどれだけ生産できるかについては知ることができるが、平時に国民を幸せにする方法を教えてはくれない。
クズネッツが警告したにもかかわらず、誰もそれに耳を傾けなかった。政策立案者たちや中央銀行は、GDPの成長を支えるためにできる限りのことをすべてやり、そして力尽きた。GDPはかつてのようには成長しないし、人々の幸福度は、ずっと前に増えなくなっていた。恒久的な危機感が社会を支配しているが、それにはもっともな理由がある。クズネッツは気付いていたが、私たちはGDPの成長だけに着目して政策を立案すべきではなかったのだ。残念ながら、それが現状である。GDPの成長率は今も主要な指標だが、それはずっと減速し続けている。
(出典:『ステークホルダー資本主義 : 世界経済フォーラムが説く、80億人の希望の未来』、クラウス・シュワブ、ピーター・バナム、日経ナショナルジオグラフィック、2022年。「第2章 クズネッツの呪い : 今日の世界経済の諸問題」の冒頭より)
経済学者のダイアン・コイルさんは、GDPを考案することになった歴史的背景や、クズネッツさんが当時からGDPの問題点について警告していたことについて、次のように語っています。
(※ダイアン・コイルさんの経歴:経済学者。ケンブリッジ大学教授。ハーバード大学で経済学の修士号と博士号を取得。イギリス財務省のアドバイザー、BBCの監督機関の会長代理などを歴任。経済学への貢献によって大英帝国勲位を受勲。)
現在私たちが使っているようなGDPができたのは、世界を揺るがした二つの歴史的事件がきっかけだった。1930年代の大恐慌と、それにつづく第二次世界大戦(1939–1945年)である。
〔中略〕
アメリカでは、サイモン・クズネッツが〔中略〕アメリカ版の国民所得計算を作成することになった(クズネッツはこの業績によって、のちにノーベル経済学賞を受賞している)。〔中略〕彼が1934年1月に連邦議会に提出した最初のレポートは、アメリカの国民所得が1929年から1932年のあいだに半減していることを明らかにするものだった。〔中略〕国民所得推計の包括的なデータは政策を推し進めるうえで大きな力となった。〔中略〕国内生産がたった数年で半減しているという正式なデータを見せられれば、対策が必要なことは誰の目にも明らかだった。
しかしクズネッツが本当にめざしていたのは、単なる生産量ではなく、国民の経済的な豊かさを測定することだった。彼は次のように述べている。
本当に価値のある国民所得計算とは、強欲な社会よりも先進的な社会の見地から見て益よりも害であるような要素を、合計の金額から差し引いたものであると思われる。軍事費や大部分の広告費、それに金融や投機に関する出費の大半は現在の金額から差し引かれるべきであり、また何よりも、我々の高度な経済に内在するというべき不便を解消するためのコストが差し引かれなくてはならない。都市文明特有の巨額の費用、たとえば地下鉄や高価な住宅などの価格は、通常は市場で生みだされた価値として扱われる。しかしそれらは実のところ、国を構成する人々の役に立つサービスではなく、都市生活を成り立たせるための必要悪としての出費でしかない。
クズネッツの見解は、GDPに対する現代の批判を先取りしているといえるだろう。GDPはけっして、福祉や豊かさのレベルを計測するものではないのだ〔中略〕。だがクズネッツの主張は、時代にそぐわなかった。戦時には人々の暮らしなど後回しだ。この文章が書かれたのは1937年、完成した経済統計データを彼が最初に議会に提出した年だった。まもなく大統領はクズネッツの主張とは逆に、軍事支出もすべて含めた統計情報を希望した。政府の軍事支出が国の経済を縮小させてしまっては都合が悪いからだ。この点はまさに戦前の国民所得計算における悩みの種だった。たとえ軍事費が経済の一部をうるおしていたとしても、民間の消費に利用できる財が減少すれば、経済は縮小したことになってしまう。〔中略〕政府支出の拡大を人々に納得させるためには、国民所得の定義を書き換えなくてはならない。クズネッツの考えるようなものではなく、現在のGDPのような形にする必要があったのだ。
〔中略〕
アメリカ初のGNP統計は1942年に発表された。政府支出を含めた支出のタイプがいくつかに分かれており、戦争のための生産力を分析しやすい形になっている。「事業税および減価償却費を(市場価格で計算されたGNPに)含めたことによって、戦争の経済に対する影響をより正確に予測できるようになった」。
クズネッツはこのやり方にかなり懐疑的だった。「商務省のやり方は、政府支出が経済成長の数字を増大させることを同語反復的に認めているにすぎず、人々の豊かさが向上するかどうかは考慮されていない」と彼は論じている。だが結局、クズネッツは政治的争いに敗北し、戦争を見据えた現実路線の政策が勝ちを収めた。
この決着が、国民所得計算のターニングポイントとなった。GNP(そしてのちのGDP)が映しだす経済の姿は、それ以前に考えられていた経済の姿とはまったく異なるものだった。
〔中略〕
福祉を重視するクズネッツのやり方が廃れ、政府支出を組み込んだGDPが開発された〔中略〕
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、18~26ページより)
ダイアン・コイルさんは、著書で、GDPの定義や計算方法などを、8ページにわたって長々と説明したあとで、次のように言っています。この言葉には、「GDPの数値は、恣意的に操作される可能性がある」ということが示されています。
そこそこシンプルに説明したつもりだが、現実にはこのほかにも計算方法が何十通りもあり、しかもそれぞれに異なる結果が出てくる。インフレの影響を差し引いた本当の経済成長率を計算したいのに、計算方法のちがいで「実質の」結果がいかようにも変わってしまうのだ。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、38ページより)
ダイアン・コイルさんは、GDPが恣意的な指標であることについて、次のように語っています。
先進国では実質GDPの計算に「連鎖方式」の物価指数を使うことが多くなっている。さまざまな品物の物価をひとつにまとめるためのウェイトを、毎年更新していくやり方だ。これによって、基準年のウェイトが現実の経済からどんどん乖離するという問題は避けられる。〔中略〕
連鎖方式を使うと、ちょうどウェイトの基準改定をしたときのように、経済の大局的な見え方が変わってくる。たとえば、先述のアンガス・マディソンが経済協力開発機構(OECD)のために作成したもののようなGDPの歴史統計は、連鎖方式を使わずに計算されたものだった。もしも連鎖方式を使ったら、世界の経済成長の様子はかなりちがったものに見えてくるはずだ。マディソン自身も「この時代(1950年以前)に新たな統計手法をあてはめたなら、アメリカの歴史は大きく再解釈されることになるだろう」と述べている。1914年のアメリカの生産性はイギリスよりも低くなり、1929年までの成長率とGDP水準もアメリカがイギリスに大きく劣ることになるのだ。これを受け入れるなら、経済史の一般的な見方が書き換えられることになるし、何が経済成長を促すのかという説明――現実の政策に深く関わる問題だ――にも再考の必要が出てくる。19世紀および20世紀の経済の姿を、これまで誤って捉えていたことになるからだ。最近の途上国の例が示すように、物価指数の計算方法変更は経済成長の見え方をがらりと変えてしまう。物価指数をいかに正確に算出するかという問題は、単なる技術的な議論にとどまらない。手法の選択ひとつで、経済成長というものの大まかなイメージまでもが完全に書き換えられてしまうのだ。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、40~41ページより)
また、ダイアン・コイルさんは、GDPが恣意的な指標であることについて、ガーナ共和国の例を挙げて、次のように語っています。
ガーナを例に挙げよう。支援団体がある国への支援を検討するときには、実質GDPが鍵になる。1人あたり実質GDPが世界銀行の決めた基準値に達しているかどうかで「低所得国」や「中所得国」のように判定されるのだ。この判定次第で、金銭的支援や低金利の融資など、受けられる支援の種類が決まる。さて、ガーナは2010年11月まで、低所得国に分類されていた。つまり貧しいということだ。ところが2010年11月5日から6日のあいだに、ガーナのGDPは一夜にして60パーセントも上昇し、「低位中所得国」へとランクアップした。実際の経済が変わったのではなく、GDPの計算方法が変わったためだ。ガーナの統計機関はこのとき、物価指数の計算に使うウェイトの基準を1993年以来初めて更新した。その結果、実質GDPが大きく書き換えられたのだ。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、39ページより)
山口周さんは、『ビジネスの未来』という本で、GDPは「都合よく操作することができる数値」であることを指摘して、下記のように批判しています。
(※山口周さんの経歴:電通や、ボストン・コンサルティング・グループなどで、コンサルタントとして従事。現在は、著作家、経営コンサルタント。『ビジネスの未来』や、『ニュータイプの時代』、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』、『クリティカル・ビジネス・パラダイム』など、著書多数。)
どのような補正をしても、結局のところGDPが「恣意性の含まれた数値」であることには変わりがない、ということです。GDPの算出にあたっては、目が眩むほど多くのデータポイントを拾いながら、どれを算入し、どれを算入しないかについての主観的な判断が、つねに介在します。たとえばガーナのGDPは2010年11月5日から翌日の6日にかけて、一夜にして60%も成長し、「低所得国」から「低位中所得国」へとランクアップしました。
なぜこんなことが起きるかというと、GDPの計量には必ず政治的配慮が絡むからです。「低所得国」と「低位中所得国」では国際機関や金融機関から受けられる経済支援や金利優遇などのレベルが変わってくるので、「どの程度の数値に落とし込むのがもっとも得か?」という問いに対する施政者の判断によって「政治的調整」が謀られるわけです。
さらに指摘すれば、計算上のさまざまな約束事の適用の仕方によっても数値は大きく変わってくることになります。たとえばすべての国のGDPは最終的にドルベースで算出されますが、この時、各国の通貨をドルに換算するにあたって、為替レートでドル換算するか、物価水準(購買力平価)でドル換算するかで容易に10%以上の差が生まれます。今日の日本ではGDP成長率の「0.5%の上下」に大騒ぎしていますが、そもそもGDPというのはそのような微差の議論に耐えられるようなハードデータではなく、ある「基本的に合意された方針」に基づいて各国の統計担当者が恣意的に拾い上げた数値、言うならば「一つの意見」でしかない、ということです。〔中略〕そもそもGDPには「実態」などありません。
〔中略〕
GDPという指標はもともとアメリカによって考案されたわけですが、この指標で国威を測るからこそアメリカがつねに優位な立場にある(ように見える)という点を忘れてはなりません。〔中略〕この指標で測るからこそ「アメリカは世界一の覇権国」であり続けられるのです。そしていま、製造産業から情報産業へのシフトが大きく進むアメリカによって「非物質的な財=無形資産をGDPに算入しよう」という議論が主導されている。
この議論の裏側に横たわるホンネを「いままでは自分がよく見えるモノサシだったけど、このモノサシだといまひとつ成長率が鈍くなってきた上に、猛烈な勢いで追い上げてくる国も出てきたので自分たちが優位に見えるようなルール改変を導入したい」と解釈すれば、この提案に対して眉に唾したくなるのが当然の反応ではないでしょうか。
(出典:『ビジネスの未来 : エコノミーにヒューマニティを取り戻す』、山口周、プレジデント社、2020年。第1章内の、「GDPは「恣意性の含まれた数値」」の項目と、「新しい価値観、新しい社会ビジョンを再設計する」の項目より)
(※上記の文章で指摘されているような、「自分にとって都合のいい指標を作って、都合よく利用したい」という「下心」をもって動いているのは、なにもアメリカだけではなく、ヨーロッパ(EU)などの、ほかの国も同じです。ですので、上記で指摘されている「アメリカの問題点」は、アメリカだけに特有の問題では無いということに、注意が必要だろうと思います。)
また、これまでに、「恣意的にGDPを改ざんする」という事件はいくつもありました。
ギリシャで、恣意的にGDPが改ざんされた事件は、下記のようなものでした。
ギリシャの統計機関は長年のあいだ、政治家の指示で数字を操作しつづけてきた。そこには大きな利害が絡んでいた。政府支出および債務残高に関する厳しい基準をクリアできなければ、救済措置が受けられずに経済が崩壊するかもしれない。この基準値は財政赤字の対GDP比という形で突きつけられていた。
〔中略〕
欧州委員会がおこなった調査によると、ギリシャは何年間も統計データを改ざんしつづけていた。
〔中略〕
あやしい徴候のひとつは、2006年にGDPをそれまでの計算より2パーセントも多い数字に修正したことだった。ギリシャ国家統計局はこの年、無申告の経済活動を推計値に含めることにしたのだ。そうしたいわゆるインフォーマル経済〔中略〕の推定額を公式なGDPに含めている国はほかにもあるが、ギリシャの場合はタイミングが絶妙すぎた。より多くの借り入れを必要としていたときに、返済能力の目安となるGDPが大きく増えたのだ。
〔中略〕
欧州委員会の調査報告書は、〔中略〕ギリシャの不正を指摘した。ギリシャ財務省が、融資を受ける目的で、財政赤字とGDPの数値を統計局に改ざんさせたというのである。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、7~9ページより)
イタリアで起こったGDPの改ざん事件は、下記のようなものでした。
1987年、イタリアはGDPが一夜のうちに急上昇したことを発表した。無届けの経済活動の推計をGDP統計に含めることにしたからだ。この変更でイタリアの経済規模は約20パーセントも拡大し、一気にイギリスを抜いて、4位のフランスに僅差で迫る世界第5位に躍り出た。イル・ソルパッソ(追い越し)と呼ばれるできごとである。
〔中略〕
非公認の経済活動をGDPに含めるというイタリアの決定は少々議論を呼んだが、すぐに騒ぎはおさまった。今ではほかにもいくつかの国が同様の修正をおこなっている。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、112~113ページより)
下記の話を見ても、これまで、いかにGDPが恣意的に改ざんされてきたか、ということがわかるかと思います。
人々が労働に費やす合計時間の半分以上は無償労働なのだ。2001年のイギリスを例に挙げれば、こうした無償労働を同種の仕事の賃金をもとにお金に換算した場合、国民生産の値が従来の1.85倍にまでふくらむ計算になる。国によって数字に差はあるけれど、その重要度は変わらない。これほど大きな活動が、慣習的にそして恣意的に、正式なGDPデータから除外されているのである。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、114~115ページより)
経済学者のダイアン・コイルさんは、GDPではない新しい経済指標が必要になっていることについて、次のように語っています。
こうした議論から導かれる教訓は、GDPは生活の豊かさを測る尺度ではないし、そのように意図されてもいないという事実だ。GDPは生産量を測る尺度である。〔中略〕もともと国民経済計算の先駆者サイモン・クズネッツは豊かさを測る指標をつくりたがっていた。だが戦争を前にして彼の理想は破れ、限られた資源と労働力を有効利用するための生産物および生産力を測るという切迫した問題にその座をゆずったのだ。もしも国民の生活の豊かさを測りたいなら、GDPはあまりいい出発点ではない。つまり、GDPをそのように修正しようとすれば〔中略〕それは必然的に、GDPを本来の目的とはまったく別のものにつくり変える試みとなってしまうのだ。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、96~97ページより)
もっぱらGDPだけで経済を測ることについては疑問の声も出てきている〔中略〕
そうした批判のなかにはGDPやそれを偏重した経済政策に対する的を射た意見もあるし、複雑すぎる手順でつくられた数字が本当に正しいのかというもっともな疑問もある。その一方でGDPは、のちに論じるように、資本主義市場経済が生みだした自由や可能性を映しだす重要な指標でもある。
〔中略〕
ただし、GDPだけで景気が測れるかというと、そうではないと私は考えている。GDPは20世紀の大量生産経済を前提とした指標であり、21世紀の経済における急速なイノベーションやデジタル化された無形サービスには対応しきれていない。
いつの世も、経済の動きは日々の政治に大きく影響してくる。だからこそ、現在のGDPよりもうまく「経済」を反映するような、新たな指標が必要となってくるはずだ。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、11~12ページより)
私は、GDPを今すぐ投げだすべきではないという結論を示そうと思う。ただし、GDPという指標が時代に合わなくなっているのも事実だ。ダラス連銀のレポートにもこう述べられている。「GDPは大量生産に合わせてつくられた統計である。そのやり方は単純に、数を数えるというもの。何個つくられたかがすべてであり、形のない価値は測れないのだ。……変化は人生のスパイスというように、何ごとも量がすべてではない」。経済のあり方が変化している以上、それを測るやり方も変わらざるをえない。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、127ページより)
(※余談ですが、ダイアン・コイルさんの著書『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』の原書(英語版)の英文のなかでは、「well-being」(ウェルビーイング)という英単語がたくさん使われています。それらの「well-being」という英単語は、日本語翻訳版の本のなかでは、ほとんどの場合、「(暮らしの)豊かさ」や、「幸福」というような意味の日本語に翻訳されています。)
『ハーバード・ビジネス・レビュー』の「幸福の戦略」と題した記事では、GDPの問題点と、それに代わる新しい指標として、「幸福度」(ウェルビーイング)が世界的に注目されていることを、次のように伝えています。
現在、GDPは攻撃の的になっている。経済学者と国家のリーダーたちは、国の状態を別の基準で、しかも「幸福」のような曖昧とも思える概念で測定しようと発言することが増えている。
2009年に行われたGDPに代わる尺度の研究は、フランスのニコラ・サルコジ大統領がその前年に委託し、経済学者のアマルティア・セン〔ノーベル経済学賞受賞者〕、ジョセフ・スティグリッツ〔ノーベル経済学賞受賞者〕、ジャン=ポール・フィトゥシ〔フランスを代表する経済学者〕がその指揮を執ったもので、世界じゅうで専門家を騒がせている。それに続いて2011年10月、世界の富める国の連合体であるOECD(経済協力開発機構)は、加盟国の「幸福度」(well-being)〔ウェルビーイング〕に関する報告書 How’s Life?(幸福度の測定)を発行した。
〔中略〕
ロバート・ケネディは68年の大統領選挙戦の際の遊説で、こう述べている。「わが国のGNPは(中略)大気汚染やタバコの広告、幹線道路から死体を取り除くための救急車を計算に入れています。自宅の扉や監獄を破られないための特殊な鍵を計算に入れています。伐採された杉林や、都市が無秩序に拡大することで失われた貴重な自然を計算に入れています。(中略)しかし、我々の子どもたちの健康や教育の質、遊びの楽しさは含まれません」
当時、ケネディの批判はほとんど注目されなかった。その後になって有名になったが、それは当然そうなるべきものであった。GDPに対する主要な批判のほぼすべてを簡潔に言い表しているからである。
その批判は、以下の3つの大きな要点から成る。
- 1 GDPはそれ自体欠陥のある指標である。
- 2 持続可能性や持続性を考慮に入れていない。
- 3 進歩と発展の測定には別の指標のほうが優れている場合がある。
〔中略〕
1 指標の誤り
GDPを算出するには数多くの選択を行う必要があり、合理的な選択でさえ偏った結果につながる可能性がある。統計学者たちは当然ながら、売買により市場価格で簡単に価値を測定できる財とサービスのほうを好み、価値を推定しなければならない経済活動はあまり好まない。
無償の家事労働などは経済的にきわめて重要なのは明らかだが、計算から除外されている。さらに、医療の提供などの政府プログラムの価値は、余暇の価値と同様、基本的に実際より過小評価される。
〔中略〕
2 持続可能性
ケネディの発言が明らかにしているように、GDPは、天然資源をむしばむ経済活動(杉林の伐採など)、将来の浄化コストや病気の原因となる経済活動(汚染など)、あるいは、コスト計上されない災害の単なる復旧(救急車など)と、国富を増大させる経済活動とを区別できない。経済成長の持続可能性(環境面であれ何であれ)を測定するには、もちろん推定が必要となる。
〔中略〕
3 その他の指標
生活のなかにある、価値ある事物の多くは、GDPによって完全にとらえることはできない。しかし、健康、教育、政治的自由などの指標によってこれらを測定することが可能となる。インド人経済学者アマルティア・セン〔ノーベル経済学賞受賞者〕は80年代に、GDPに算入される「財」(commodities)〔コモディティーズ〕と算入されない「潜在能力」(capability)〔ケイパビリティ〕とを区別するというアイデアを提唱した。〔中略〕その成果は、GDPを代替する試みとしては現在までで最も成功したものとなっている。
〔中略〕
年1回〔UNDP(国連開発計画)から〕発行される『人間開発報告書』では、主要な指数はあまり変わっていないものの、持続可能性や所得分布など他のさまざまな指標も取り扱っている。最新の報告書では、アメリカは HDI〔人間開発指数〕で4位だが、不平等調整済み HDI(国内の不平等の程度を加味した指数)では23位に留まっている。
(出典:ジャスティン・フォックス「幸福の戦略」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2012年05月号』、ダイヤモンド社、2012年、25~30ページより)
ウェルビーイング
ここまでお伝えしてきた、GDPのような古い指標の問題点を解決するための、新しい指標のひとつとして注目されているのが、ウェルビーイングです。
(※下の画像の「GDW」というのは、「国内総ウェルビーイング(国内総充実)」のことです。「GDW」は、従来の「GDP」とは違う、新しい指標として注目されています。)
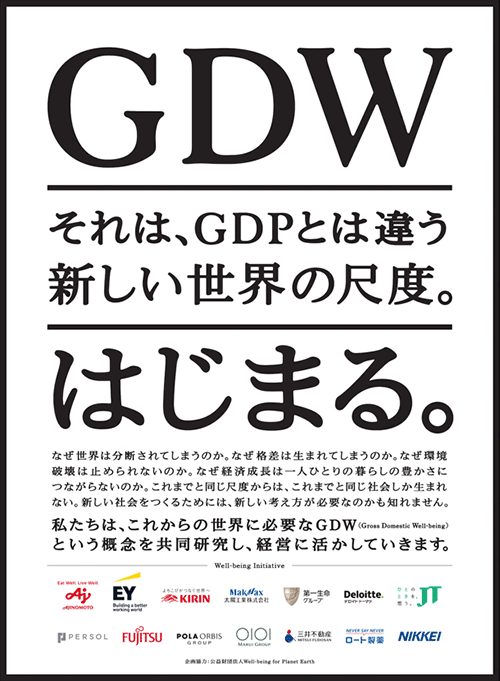
GDW
それは、GDPとは違う新しい世界の尺度。
はじまる。
なぜ世界は分断されてしまうのか。なぜ格差は生まれてしまうのか。なぜ環境破壊は止められないのか。なぜ経済成長は一人ひとりの暮らしの豊かさにつながらないのか。これまでと同じ尺度からは、これまでと同じ社会しか生まれない。新しい社会をつくるためには、新しい考え方が必要なのかも知れません。
私たちは、これからの世界に必要なGDW(Gross Domestic Well-being〔グロス・ドメスティック・ウェルビーイング〕)という概念を共同研究し、経営に活かしていきます。
(※上の画像は、GDW(国内総ウェルビーイング、国内総充実)の広告です。この広告は、日本経済新聞に掲載された、日本版ウェルビーイングイニシアチブによる広告です。画像と文章の出典:「Well-being Initiative 2022年活動報告」のページより)
ウェルビーイングってなに?
ウェルビーイングというのは、かんたんに言うと、「心身ともに健康な生き方」のことです。他にも、「生活に満足を感じている状態」や、「幸せ(幸福感を感じる生き方)」と表現されることもあります。
投資家の藤野英人さんは、「ウェルビーイングとは何なのか?」ということについて、『プロ投資家の先の先を読む思考法』という本のなかで、次のように語っています。
ウェルビーイングとは being well、つまり「well」な状態であることを言い、心身共によい状態を目指すという考え方です。
「お金持ちであること」や「長生きすること」や「やりがいのある仕事を持っていること」などは、それ自体が直接的に人を幸せにするとは限らず、そういったものを目指すことで不幸になるケースもあります。
それよりももっと本質的な「よい状態」を目指すことこそ、大きな目標であるべきだということです。
(出典:『プロ投資家の先の先を読む思考法』、藤野英人、クロスメディア・パブリッシング、2022年。「第3章 先の先を読むための「材料」の集め方 : 「情報」を集め「体験」を積むことで、未来につながる「快」を読み取る」の章内の、「快・不快への想像力が高いほど「先の先」が見える」の項目より)
(※この記事で言う「ウェルビーイング」は、おもに「主観的ウェルビーイング」(その人自身が実感しているウェルビーイング)のことです。)
ウェルビーイングな状態であるための5つの要素をあらわす言葉として、PERMA(パーマ)という言葉があります。その5つの要素は、下記のとおりです。
- ポジティブな感情
- 没頭(エンゲージメント、フロー体験)
- 意味(意義)
- 達成感
- 良い人間関係
藤野英人さんは、PERMA(パーマ)について、次のように語っています。
ウェルビーイングの定義はさまざまありますが、要素を分解して研究を深めていくほど、「wealth(富)」と「health(健康)」はウェルビーイングの中心的な要素ではないこともわかります。
富と健康というのは、いかにもウェルビーイングのど真ん中というイメージがありそうですが、じつはいずれも副次的なものとされているのです。
最新の分析の一つに、「PERMA(パーマ)」が揃っていることがウェルビーイングであるというものがあります。
PERMAの「P」は Positive emotion〔ポジティブな感情(ポジティブエモーション)〕、「E」は Engagement〔没頭(エンゲージメント)〕。「R」は Relationship〔良好な人間関係(リレーションシップ)〕、「M」は Meaning〔意味、意義(ミーニング)〕、「A」は Achievement〔達成感(アチーブメント)〕の頭文字であり、ポジティブ心理学で著名な心理学者のマーティン・セリグマンが提唱したものです。
つまり、ワクワクしたり楽しかったりするようなポジティブな感情があること(Positive emotion)、没頭したりよい意味でのめり込むことができるものがあるなど、物事に積極的に関わっていること(Engagement)、他者とよい関係性を築いていること(Relationship)、自分の人生に意味を感じられること(Meaning)、達成感を持てること(Achievement)という5つの要素がそろっているとき、人は「ウェルビーイングだ」と感じるということです。
(出典:『プロ投資家の先の先を読む思考法』、藤野英人、クロスメディア・パブリッシング、2022年。「第5章 先の先に見えてきた「未来のかたち」 : これからはウェルビーイングが投資の成否のカギを握る」の章内の、「「富」や「健康」より「PERMA」」の項目より)
下の動画は、投資家の藤野英人さんと、ウェルビーイングの専門家である、石川善樹さんとの対談映像です。藤野英人さんが、PERMA(パーマ)とウェルビーイングについて語っている様子は、下の動画の「0:05~1:19」のところで見ることができます。
▼ 0:05~1:19島田由香さんが、「ウェルビーイングを向上させる要素としてのPERMA(パーマ)」について語っている様子は、下の動画の「36:37~38:18」のところで見ることができます。
(※島田由香さんの経歴:ユニリーバ・ジャパン 取締役人事総務本部長 や、ゼネラル・エレクトリック(GE) 日本法人 人事マネジャーを経て、現在、YeeY 代表。)
▼ 36:37~38:18上記の、藤野英人さんや、島田由香さんのお話のなかに出てきた、ウェルビーイングやPERMA(パーマ)の科学的根拠となっているのは、ポジティブ心理学という、新しい心理学の分野の知見です。そのポジティブ心理学の創始者で、アメリカ心理学会の元会長でもある、マーティン・セリグマンさんは、『ポジティブ心理学の挑戦 : “幸福”から”持続的幸福”へ』という本のなかで、次のように語っています。
私は現在、ポジティブ心理学という、心理学の大きな地殻変動に関わっている。1998年、私はアメリカ心理学会(APA)の会長として、心理学の従来の目標に新しい目標をつけ加えるよう呼びかけた。「何が人生を生きるに値するものにするのかを探究する。そして、生きるに値する人生を可能とする状態を築き上げていく」という目標だ。
人間のウェルビーイング(よいあり方)について理解し、よい生き方を可能とする状態を築くという目標は、人間の苦悩について理解し、人生を台なしにする状態を解消するという目標と同じではない。この瞬間にも、世界中の数千の人がこの新しい心理学分野に携わっており、こうした目標に向かって努力している。
〔中略〕
私は今や、ポジティブ心理学のテーマは「ウェルビーイング」だと考えている。ウェルビーイングを測定する判断基準は「持続的幸福度(フラーリッシング)」で、ポジティブ心理学の目標は持続的幸福度を増大することだと考えている。
(出典:『ポジティブ心理学の挑戦 : “幸福”から”持続的幸福”へ』、マーティン・セリグマン、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2014年、4ページ、27ページ)
(※マーティン・セリグマンさんによる、PERMA(パーマ)についてのくわしい説明は、『ポジティブ心理学の挑戦 : “幸福”から”持続的幸福”へ』の本のなかの、33~44ページで語られています。)
「ウェルビーイングってなに?」ということについて、経営学者の岩本隆さんは、『経営戦略としての人的資本開示』という本のなかで、「人的資本経営における主要KPI」のひとつとして、ウェルビーイングを次のように説明しています。(※岩本隆さんは、慶應大学大学院経営管理研究科特任教授や、慶應大学大学院政策・メディア研究科特任教授、山形大学学術研究院産学連携教授などを歴任されています。)
にわかに重要なKPIとなっているのはウェルビーイングである。ウェルビーイングはフィジカルとメンタルの健康に加え、幸福感も含む概念であるが、特に、幸福感を高めるために、個々の従業員のキャリア充足度を高めることが重要になっている。
(出典:『経営戦略としての人的資本開示 : HRテクノロジーの活用とデータドリブンHCMの実践』、HRテクノロジーコンソーシアム [編集]、日本能率協会マネジメントセンター、2022年。第1章の第2節内の「人的資本経営における主要KPIの例」の項目より)
また、経営学者の入山章栄さんは、『世界標準の経営理論』という本のなかで、「ビジネスが追い求めるべき目標として、ウェルビーイングが重要視されている」ということについて、次のように語っています。(※入山章栄さんは、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授です。)
ビジネスにおいて我々が追求すべき「価値」とは、そもそも何だろうか。言い換えれば、そもそもビジネスの目的とは何なのだろうか。
〔中略〕
この問いに正面から向き合い、様々な論考を提示しているのが、ミシガン大学のジェームズ・ウォルシュである。
〔中略〕
論考の結果、ウォルシュはコレクティブ・バリュー(collective value)という概念を提示し、「それを最適化することこそがビジネスの目指すべきものではないか」という問題提起をしている〔中略〕。さらに同論文の結論部でウォルシュは、このコレクティブ・バリューに近い概念がウェル・ビーイング(well-being)であると認めている。
ウェル・ビーイングは最近聞かれることも多くなってきた。一義には「精神的・身体的・社会的に良好な状態」のことであり、そしてもっと直感的に言えば、それは、「我々一人ひとりがよりよく生きる」ことであり、そして「幸せである」ことだ。実は、世界最大の経営学会であるアカデミー・オブ・マネジメントの2016年世界大会のテーマが、まさにウェル・ビーイングだった。ビジネスと幸せを同期させることに、世界の経営学者が注目を持ち始めたのである。
一方、現実は先を行きつつあるかもしれない。第35章で触れたように、近年は多くの経営者が、「ビジネスの目的は社会の様々な人々や従業員、ステークホルダーの幸せを追求すること」だと主張し始めている。ユニリーバCEOを務めたポール・ポールマン氏やセールスフォース・ドットコムのマーク・ベニオフ氏がそうだし、日本ではヤフー前CEOの宮坂学氏や、丸井の青井浩氏などがその筆頭だろうか。ウェルビーイングの重要性を訴える予防医学研究者・石川善樹氏の言動も、メディアで広く注目されている。
(出典:『世界標準の経営理論』、入山章栄、ダイヤモンド社、2019年。第39章内の「我々がビジネスで生み出すべき「価値」は何か」の節などより)
ちなみに、上記で名前が挙がっている、丸井グループ社長の青井浩さんは、ウェルビーイングについて、下の動画の「46:34~48:35」のところで、次のように語っています。
46:52
▼青井浩さん:丸井グループ社長
SDGs〔サステナビリティを実現するための目標〕には、2030年という期限があります。
では、2030年以降の社会は、何を目指していくことになるのか?
そのとき、一番大事になるのが、ウェルビーイング〔幸せ〕です。
ウェルビーイングの対になっている考え方が、GDPです。
将来世代の若者のなかには、「GDPの成長〔経済成長〕が永遠に続く」という「神話」を信じている人はいません。
そこで、〔GDPに代わって〕目指すべき目標となるのが、ウェルビーイングです。
なので、「ウェルビーイングは、サステナビリティとともに、今から取り組んでいくべき課題だ」というのが、将来世代の若者の感覚です。
「ウェルビーイング〔幸せ〕とは何か?」ということを、ダイバーシティ〔多様性〕の観点から考えると、「一人ひとりが、自分の人生を生きられる」ということだと思います。
そのことが、ダイバーシティであり、インクルージョンだとすると、それらは、ウェルビーイングとひとつのものであるととらえるべきものです。
「これもあれもやらなきゃいけない」という「負担」としてとらえるのではなく、これまでの目標に代わる「未来に向けた新しい目標」だととらえることで、楽しくなっていくんじゃないかなと思います。
国会では、総理大臣が、ウェルビーイングについて言及しています。下記の動画は、2023年10月23日の、第212回国会における、内閣総理大臣の所信表明演説の映像です。岸田文雄総理は、ウェルビーイングについて、下記の動画の「33:46~34:18」のところで、次のように述べています。
このことからも、社会的に、ウェルビーイングが重要視されていることが感じとれるかと思います。
持続的な賃上げに加えて、人々のやる気、希望、社会の豊かさといったいわゆる「ウェルビーイング」を拡(ひろ)げれば、この令和の時代において再び、日本国民が「明日は今日より良くなる」と信じることができるようになる。日本国民が「明日は今日より良くなる」と信じられる時代を実現します。
ウェルビーイングの第一人者である石川善樹さんは、ウェルビーイングを測る指標を「生活満足度」と定義して、その指標の測定方法や、その指標を向上させる方法などについて、下の動画の「20:31~57:25」のところで語っています。
▼ 20:31~57:25(※上の動画の32:12のあたりで、「主観的ウェルビーイング」という言葉が使われています。この言葉については、石川善樹さんご自身がこの言葉について解説しているPDFファイルがあり、ウェルビーイング学会のウェブサイトから閲覧できます。)
上の動画で話をしている石川善樹さんは、予防医学研究者であり、ウェルビーイングの研究を支援する公益財団法人ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースの代表理事でもあります。また、ウェルビーイング学会の理事でもあります。
(※石川善樹さんが代表理事をつとめるその財団の、役員や評議員のなかには、下記のように、各分野の第一級の方々が参画されています。)
▼公益財団法人ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースの役員・評議員の方々(一部)
- 石川善樹:ウェルビーイングの専門家。ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事。ウェルビーイング学会 理事。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で医学の博士号を取得。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学など。
- 北川拓也:元 楽天常務執行役員 CDO(最高データ責任者)(楽天史上最年少の常務執行役員)、元 楽天技術研究所グローバル所長。量子コンピューター企業 QuEraの社長。理論物理学者。ハーバード大学数学・物理学専攻、同大学院物理学科博士課程修了。
- 矢野和男:データサイエンスを活用してウェルビーイングを向上させる手法の第一人者。日立製作所 特別研究員(フェロー)、株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO。
- 小林正忠:楽天株式会社 常務執行役員 CWO(最高ウェルビーイング責任者)。
- エド・ディーナー:イリノイ大学名誉教授、ウェルビーイング研究の権威。
- 前野隆司:ウェルビーイングの専門家。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM) 教授。
- 孫泰蔵:起業家、投資家。
- ドミニク・チェン:早稲田大学文学学術院准教授、NPOコモンスフィア理事。
ポストSDGsの本命は、ウェルビーイング
ウェルビーイングは、「ポストSDGs」と呼ばれることもあります。この「ポストSDGs」という言葉には、「今後、ウェルビーイングは、SDGsと同じように、社会全体で目指すべき大きな指針となる」というような意味が込められています。
下の動画は、投資家の藤野英人さんと、ウェルビーイングの専門家である、石川善樹さんとの対談映像です。この対談のなかで、石川さんは、「ポストSDGs」(SDGsの次に、人類が目指すべき社会課題)として、ウェルビーイングを挙げています(4:54~7:32)。
4:54
▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事
SDGs(持続可能な開発目標)は、2030年で終了します。
その次の、2031年~2045年の期間に、人類全体で取り組むことになる社会課題は、「ポストSDGs」と呼ばれています。その「ポストSDGs」の社会課題についての活動を、国内や海外でやっています。
5:26
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
よく、メディアや本でお話をされていますが、「SDGsは、ネガティブをゼロにするためのもの」なんですよね。SDGsは、「社会課題に対して、マイナスがたくさんあるので、そのマイナスを無くす」ためのもの。SDGsは、ネガティブな現状を、「ネガティブではない状態にする」ためのもの。
〔中略〕
6:46
▼石川善樹さん
SDGs(持続可能な開発目標)の「開発」〔ディベロップメント〕という言葉にあらわれているように、SDGsは、おもに経済的な社会課題に対処するためのものです。そのため、SDGsには、平和や、文化的、社会的な側面があまり含まれていません。
そういったことまで含めた、次の時代の社会課題が、永続的なウェルビーイング〔サスティナブル・ウェルビーイング〕です。
ウェルビーイングの専門家である石川善樹さんは、ポストSDGs(SDGsの次に、人類が目指すべき社会課題)としてのウェルビーイングの重要性について、下の動画の「1:23:24~1:24:53」のところで語っています。
▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事
1:23:24
ウェルビーイングは、経営だけでなく、今後の時代のキーワードです。
ウェルビーイングは、2030年以降の「ポストSDGs」の重要なキーワードになってくるので、ぜひご注目ください。
〔※ここで言う「ポストSDGs」というのは、2030年にSDGsの終了期限が来たあとに、人類全体で取り組むべき重要課題として設定されることになるテーマのことです。その「ポストSDGs」の有力候補として、ウェルビーイングが注目されています。〕
1:24:00
寿命は、かなり長くなりました。
では、人生の質(ウェルビーイング)はどう変わったのか?
「日本人のウェルビーイングの推移(1958~1987年)」のグラフ
戦後、GDPは、右肩上がりに伸びたのに、ウェルビーイングがまったく変わってない。
1:24:30
社会の進歩を表す指標のほぼ全てが改善したのに、実感としての豊かさ(ウェルビーイング)を感じられていない。
1:24:43
ここが予防医学の一番のフロンティア。ここが、今、予防医学の最前線のテーマ。このテーマに取り組んでいます。
上の動画のなかで示されている「日本人のウェルビーイングの推移(1958~1987年)」のグラフ(下のグラフ)は、石川善樹さんが代表理事を務める、「公益財団法人 Well-being for Planet Earth : WPE Foundation」の公式サイト内のページで閲覧できます。
(※下のグラフのような、「経済状況(一人当たりGDPや、所得)が向上しても、ウェルビーイング(生活満足度、幸福感)が向上しない」という逆説的な現象は、「幸福のパラドックス」と呼ばれています。(また、この現象の発見者の名前を採って、「イースタリン・パラドックス」と呼ばれることもあります)。ただ、ノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンなど、イースタリン・パラドックスに疑問を呈している人もいます(Google翻訳を使用)(原文)。)
ウェルビーイングの専門家である石川善樹さんは、ウェルビーイングをめぐる、近年の世の中の大きな流れの変化や、ポストSDGs(SDGsの次に、人類が目指すべき社会課題)について、下の動画の「1:38~5:30」のところで語っています。
▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事
1:38
この2年〔2020年~2021年〕で起こったこと。この2年でウェルビーイングはいろんな出来事がありました。端的に、3点ほどお話させていただきます。
▼1点目
今年〔2021年〕に、日本政府は、ウェルビーイングを、骨太方針と、成長戦略に、明確に位置づけました。
具体的には、「各省庁における基本計画等においてウェルビーイングのKPIを定めること」ということが定められました。日本のすべての省庁の、すべての基本計画には、ウェルビーイングという横串が入って、ウェルビーイングのKPIを設定しなければならなくなりました。
また、概算要求が提出されて、予算も付きました。いろいろな省庁を合わせると、現時点で、32の基本計画に、ウェルビーイングのKPIが入りました。
例えば、科学技術基本計画のなかの、ウェルビーイング技術がそのひとつです。この分野は、〔ここにいらっしゃる〕矢野和男さんをはじめとして、日本には、世界を取れる要素技術があります。そのウェルビーイング技術の開発に、予算が大きく付きました。
また、象徴的なのは、「ムーンショット目標」です
「ムーンショット目標」のすべての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています(ムーンショット・フォー・ヒューマン・ウェルビーイング)。つまり、「ムーンショット目標」全体も、ウェルビーイング研究だということです
このように、「国をあげて、ウェルビーイングをやるんだ」という宣言が、今年出されたということが大きなトピックです
〔※「ムーンショット目標」とは、「ムーンショット型研究開発制度」のプロジェクトが目指す目標のことです。これは、内閣府が主導する国家プロジェクトであり、「未来社会を展望し、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象として、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)及び構想を国が策定」する、というものです。〕
3:12
これは、経営においても同様です。これから、ウェルビーイングについての様々なガイドラインが出てきます。
3:24
▼2点目
この2年〔2020年~2021年〕で、企業経営について、大きく変わったのが、「従業員のウェルビーイング」を考える時代から、「経営にまつわるステークホルダーのウェルビーイングを考える時代」へと変わりました。
人事部門が取り組むべきテーマから、経営者が取り組むべきテーマへと変わりました
3:48
その動きに合わせて、今年〔2021年〕、日本経済新聞社が、「ウェルビーイング・イニシアチブ」を立ち上げました。
〔※この「ウェルビーイング・イニシアチブ」というのは、日経ウェルビーイングイニシアチブ(日本版ウェルビーイングイニシアチブ)のことです。〕
ロート製薬や、丸井グループ、第一生命などの先進的な企業が参加して、ウェルビーイングと企業価値を高めていこうという動きが始まっています。
4:17
▼3点目がグローバルの視点
SDGsは、2030年まで。ポストSDGsが2031年から2045年までの期間でおそらく設定されます。2045年は国連の生誕100周年ということもあって、2031年からの15年間になる。
ポストSDGsでは、何がアジェンダ〔目指すべき目標〕になるのか?
ウェルビーイングが最有力。
日本国政府としても、ポストSDGsのアジェンダ設定に参画できるように、積極的に動いています。国連や、OECDなどの、いろいろな国際機関も動き始めている。その動きを主導しているのは、日本です。
ヨーロッパは、サステナビリティというアジェンダを設定しました。日本から発信するグローバルアジェンダ〔人類全体で取り組む社会課題〕として、ウェルビーイングが注目されています。
ウェルビーイングは、事業成長のグランドデザイン
ウェルビーイングを向上させる取り組みは、事業の成長につながります。
投資家の藤野英人さんは、「ウェルビーイングは、成長戦略である」ということを、『プロ投資家の先の先を読む思考法』という本のなかで、次のように語っています。
これからはウェルビーイングを追求する企業が成長する
第3章で触れた「ウェルビーイング」について、私はこれからの成長戦略の基本になると考えています。
テクノロジーの世界であれ、投資の世界であれ、ウェルビーイングの重要性は今後ますます高まっていくことになるでしょう。
先にも触れたように、ウェルビーイングは英語で言えば being well、つまり“How are you?”です。言語を問わず、つねに相手の状態を尋ね合うことは、人間のコミュニケーションの柱です。
相手の状態が心身共によいかどうかを大切にすることが、企業とお客さまとの関係、企業と従業員の関係などあらゆる場面で大切なのは言うまでもないことです。
しかし、企業の経営や行政など、本来はウェルビーイングな状態を追求すべき場面において、これまでウェルビーイングという視点はあまり語られてきませんでした。
「儲かるのか」「効率がいいのか」といったことが重視され、「それは、人が『よい状態』でいることにつながるのか」「人の主観的な幸福感とはどのようにすれば得られるのか」と考える視点がすっぽり抜け落ちていたのです。
近年、ウェルビーイングという言葉はさまざまな場面で使われるようになっていますが、この言葉の意味を曖昧に捉え、「従業員の健康やメンタルにも配慮しろということだろう」「またよくわからないバズワードが出てきたのか」などと軽く考えている人がいるとすれば、見方を変える必要があるでしょう。
これから企業は、お客さまをはじめとしたステークホルダーにとってのウェルビーイングを深く考えることが要求されるようになります。
そしてウェルビーイングについて深く考え、自分たちが考えるウェルビーイングとはなにかを提示できた会社は、高く評価されて大きく成長するでしょう。ウェルビーイングは、力強い成長戦略なのです。
(出典:『プロ投資家の先の先を読む思考法』、藤野英人、クロスメディア・パブリッシング、2022年。「第5章 先の先に見えてきた「未来のかたち」 : これからはウェルビーイングが投資の成否のカギを握る」の章内の、「これからはウェルビーイングを追求する企業が成長する」の節より)
また、藤野英人さんは、「世の中の流れの「先の先」を読むうえでも、ウェルビーイングが重要である」ということを、次のように語っています。
快・不快への想像力が高いほど「先の先」が見える
さまざまな学びや体験から私がなにを得ているかというと、ひと言で言えば「人間にとってなにが快で、なにが不快か」ということです。
「先の先」を読んで未来を予測していくとき、大前提となるのは「人間とはなにか」についての洞察です。
未来というのは、人間の行動の積み重ねによってつくられるものですから、人間とはなんなのか、人間はどんな理由でどんな方向に向かっていくのかを考える必要があります。
そこで重要なのが、近年注目を集めている「ウェルビーイング」です。
ウェルビーイングとは being well、つまり「well」な状態であることを言い、心身共によい状態を目指すという考え方です。
「お金持ちであること」や「長生きすること」や「やりがいのある仕事を持っていること」などは、それ自体が直接的に人を幸せにするとは限らず、そういったものを目指すことで不幸になるケースもあります。
それよりももっと本質的な「よい状態」を目指すことこそ、大きな目標であるべきだということです。
〔中略〕
ウェルビーイングの重要性を考えると、これまで以上に価値が高まるのは「体験」です。
なにかの情報を文字や映像として知っているということではなく、体験を通じて「それがどのような状態なのか」を感じ、人間の快・不快への想像力を高くできる人ほど「先の先」を読む力は上がるのではないかと思います。
ウェルビーイングは「先の先」を読むうえで非常に重要な視点です〔後略〕
(出典:『プロ投資家の先の先を読む思考法』、藤野英人、クロスメディア・パブリッシング、2022年。「第3章 先の先を読むための「材料」の集め方 : 「情報」を集め「体験」を積むことで、未来につながる「快」を読み取る」の章内の、「快・不快への想像力が高いほど「先の先」が見える」の項目より)
このように、ウェルビーイングの向上に取り組むことで、未来を予測して、事業の成長につなげていくことができます。そのように、ウェルビーイングの向上が事業成長につながっていく仕組みについては、次の項目でくわしく説明していきます。
幸せな人は生産性が高い科学的証拠
「幸せな人(ウェルビーイングな人)は、生産性が高い」ということが、科学的に証明されています。
前野隆司さんは、「幸福度とパフォーマンスの関係」について、著書『ウェルビーイング』のなかで次のように語っています。(※前野隆司さんは、ウェルビーイング研究の第一人者であり、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)の教授です。)
『ハーバード・ビジネス・レビュー』(ダイヤモンド社)の2012年5月号に、著名な研究結果を集めた「幸福の戦略」という特集が組まれました。そのなかで、幸福度の高い社員の創造性はそうでない社員の3倍高く、生産性は31%高く、売上も37%高い、とリュボミアスキー氏やディーナー氏らが解説しています。
また、幸福度の高い社員は、そうでない社員よりも欠勤率が41%低く、離職率が59%低く、業務上の事故が70%少ないという研究結果もあります。
つまり、幸せな人は創造性も生産性も高く、ミスも少なく休んだり辞めたりもしないということです。働く者にとって幸福度がいかに大事であるかを理解できると思います。
(出典:『ウェルビーイング (日経文庫)』、前野隆司、前野マドカ、日経BP、2022年。第4章の第1節内の「幸福度とパフォーマンスの関係」の項目より)
(※上記の文中で紹介されている、「ソーニャ・リュボミルスキーさんや、エド・ディーナーさんたちの研究によって判明した、幸福感とパフォーマンスの関係についての数値」については、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2012年05月号』の61ページの1段目や、63ページの左側のところに書かれています。なお、それらの数値の根拠となっているのは、彼らの論文「頻繁なポジティブ感情の効用: 幸福は成功につながるか?」(仮邦題)です。(原題:「The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?」、書誌情報)。)
「幸せな人は生産性が高い」ということについては、矢野和男さんが、下の動画の「1:30~2:16」や「13:24~13:53」のところで語っています。(※矢野和男さんは、データサイエンスを活用してウェルビーイングを向上させる手法の第一人者であり、日立製作所の特別研究員(フェロー)です。)
▼ 1:30~2:16
- 幸せだと仕事がうまくいく。
- 幸せなセールスパーソンは、受注率が30%高い。
- 幸せな人は、創造性が3倍高い。
- 幸せな人は、離職率が半分。
- 幸せな人が多い会社は、一株あたりの利益が18%高い。
▼ 13:24~13:53
実証実験:83社、4300人、3週間の日々の前向きな宣言による幸福度指標の向上
33%の心の資本の向上
↓
10%の生産性向上に相当
▼ 13:24~13:53
上の動画で語られている「幸せな人は生産性が高い」ということについては、矢野和男さんの著書『予測不能の時代』のなかで、次のように説明されています。
この20年間あまりのポジティブ心理学やポジティブな組織行動の研究により、予測不能な変化の中での人や組織のよりよい状態に関して、重要な発見があった。幸せと仕事や健康の間にある、従来の常識を覆す因果関係を発見したのだ。
我々は、幸せと仕事や健康との関係について、「仕事がうまくいくと幸せになる」「健康だと幸せになりやすい」というふうに考えがちである。実は、研究が明らかにしたのは、因果関係はこれとは逆だということだった。「幸せだから、仕事がうまくいく」、すなわち、幸せにより生産性や創造性が高くなり、「幸せだと、病気になりにくく、なっても治りやすい」のだ。
研究によると、主観的に幸せな人(幸せだと感じている人)は、仕事のパフォーマンスが高い。具体的には、営業の生産性は30%程度高く、創造性では3倍も高い。さらに、同じく幸せな人は、健康で長寿で、結婚の成功率も高く、離職もしにくい。そして、幸せな人が多い会社は、そうでない会社よりも、1株あたりの利益が18%も高い。このようなエビデンスに基づく知見が続々と得られたのである。
(出典:『予測不能の時代 : データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』、矢野和男、草思社、2021年。「第2章 新たな幸せの姿」の章内の、「「幸せな人は生産性が高い」という発見」の項目より)
「なぜ、幸せだと生産性が高まるのか?」ということについては、矢野和男さんが著書『予測不能の時代』のなかで、次のように説明しています。
なぜ、幸せだと生産性が高まるのだろうか。この疑問への答えを示唆する、スマートフォンを用いて行われた大規模な実験がある。〔中略〕
〔中略〕いいムードで幸せな人は、面白くなくても、やらなければいけない活動を増やしたのだ。しんどくても、面倒くさくても、やらなければいけないことを、より多く行うようになっていたのである。
仕事では、工夫をしたり、人に頭を下げたり、未経験のことに背伸びして挑戦できるかどうかで、結果は大きく異なってくる。主観的な幸福感やいいムードは、このような工夫や挑戦を行うための「原資」となる精神的なエネルギーを与えていたということだ。逆に、幸福感が低くなって、このような精神的なエネルギーや精神的原資が低下すると、気晴らしなどに時間を使うようになる。この場合、必然的に、しんどくて面倒なことは、先送りされる。
この実験の結果を解釈すると、それ以前の研究で指摘されていた「主観的に幸せな人は、仕事のパフォーマンスが高い」「幸せな人が多い会社は、1株あたりの利益が高い」ということの理由が見えてくる。幸せな人は、重要だが面倒で面白くない仕事を、労をいとわず行うことができる。このような仕事は、行き詰まった局面を打開したり、変化する状況に適応したりするのに役立ち、成果は大きい。一方、幸せでない人は、精神的な原資や精神的なエネルギーが足りないため、このような面倒な仕事になかなか手をつけられないのである。
ここから、予測不能な変化の中では、この精神的な原資があるかどうか、ひいては幸せであるかどうかが、仕事の成否に決定的な影響を与えるということがわかる。
再度書くが、あなたのこれからの仕事は、大きな目的やミッションにこだわり、絶えざる実験と学習を通して道を見つけ、既存のルールや計画を廃棄し、上書きすることである。しかし、あなたの前にはこれらを阻む人がいて障害となる。そのような人たちと必ず闘うことになる。これは決して楽な仕事ではないし、実行には精神的なエネルギーが必要である。
すなわち、予測不能な変化の中でいい仕事を行うには、幸せと、それを精神的な原資とする前向きな行動が必要なのだ。
(出典:『予測不能の時代 : データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』、矢野和男、草思社、2021年。「第2章 新たな幸せの姿」の章内の、「「幸せな人は生産性が高い」という発見」の項目より)
『ハーバード・ビジネス・レビュー』に掲載された論文「社員のパフォーマンスを高める 幸福のマネジメント」のなかでも、「幸せな人は、生産性が高い」ということが下記のように述べられています。
ミシガン大学スティーブンM・ロス・スクール・オブ・ビジネスのポジティブ組織研究センターが高業績企業の秘訣を調査したところ、幸福感を抱く社員は、そうでない人と比べて長期にわたって高いパフォーマンスを上げることが明らかになった。このような社員は「成功している」(thriving)働き手であり、成果を出して充実感を得るだけでなく、会社と自身の将来を切り開こうと熱意をみなぎらせている。彼ら彼女らは、精力的であるとともに、燃え尽きない術を心得ている。また、たゆまぬ学習意欲が高く、新しい知識や技能を身につけ成長していく。
〔中略〕
我々が安定的に高業績を上げる組織の秘訣について調査したところ、「幸福感を抱く社員は、そうでない人と比べて長期にわたって高いパフォーマンスを上げる」ということが明らかとなった。欠勤が少なく、離職率が低く、求められた以上の働きをし、自分たちと同様に意欲の高い人材を引き寄せるのだ。しかも、短距離走よりもマラソン向きだといえ、すぐに息切れするようなことがない。
〔中略〕
さまざまな業界や職種を対象に調査したところ、この条件を満たす人材〔幸福感を抱く社員〕は他の人材と比べて、全般的な業績に関する上司からの評価が16%高く、「燃え尽きてしまった」という自己申告は25%も少なかった。組織への献身度は32%、仕事の満足度は46%高かった。欠勤と病院での受診がともに際立って少ないため、勤務先にとっては不稼働時間や医療費負担が少ないという効用もある。
(出典:グレッチェン・スプレイツァー、クリスティーン・ポラス「社員のパフォーマンスを高める 幸福のマネジメント」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2012年05月号』、ダイヤモンド社、2012年、46ページ、47ページ、48ページより)
また、上記の論文では、逆に、「ひどい扱いを受けた人は、生産性が下がる」ということが下記のように述べられています。
ぞんざいな扱いの代償は大きい。サンダーバード国際経営大学院教授のクリスティーン・ピアソンと我々との共同研究からは、職場でぞんざいな扱いを受けた人の半数は仕事に傾ける努力を意識的にセーブした、という結果が得られている。
3分の1を超える人々が、仕事の質をわざと落とそうとしたという。また、3人に2人は、自分をぞんざいに扱った相手を避ける時間が長いと言い、ほぼ同数が「自分のパフォーマンスが下がった」と回答している。
(出典:グレッチェン・スプレイツァー、クリスティーン・ポラス「社員のパフォーマンスを高める 幸福のマネジメント」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2012年05月号』、ダイヤモンド社、2012年、54ページより)
さきほど紹介した矢野和男さんの動画の「2:15~6:28」のところで、「生産的で幸せな組織であるために重要な、三角形の関係」について語られています。その「三角形」についてのくわしい説明については、下の動画の「28:34~39:59」のところで語られています。
▼ 28:34~39:59上の矢野和男さんの動画の「33:45~36:45」のところで、「FINE(ファイン)」(ポジティブで幸せな組織の4つの特徴)という言葉が紹介されています。それについては、矢野和男さんの著書『予測不能の時代』のなかで、次のように説明されています。
〔中略〕データを詳しくみると、ポジティブで幸せな組織に普遍的にみられる特徴があることが明らかになったのである。これは裏返せば、ネガティブで幸せでない組織には、逆の特徴が見られるということでもある。
我々は、このような特徴を4つ見出した。ここだけを見れば、幸せな組織とそうでない組織の違いがわかるという特徴だ。その4つの特徴は以下のようにまとめられる。いずれもウエアラブル端末の計測データを組み合わせることで、定量化が可能な特徴である。
- 第1の特徴 フラット(Flat)=均等 人と人のつながりが特定の人に偏らず均等である
- 第2の特徴 インプロバイズド(Improvised)=即興的 5分から10分の短い会話が高頻度で行われている
- 第3の特徴 ノンバーバル(Non-verbal)=非言語的 会話中に身体が同調してよく動く
- 第4の特徴 イコール(Equal)=平等 発言権が平等である
逆にいうと、幸せでない組織の特徴は下記の4つである。
- 第1の特徴 人と人のつながりが特定の人に偏っている
- 第2の特徴 5分から10分の短い会話が少ない(長い会議や会話が多い)
- 第3の特徴 会話中に身体が同調せず動きも少ない
- 第4の特徴 会議や会話での発言権が特定の人に偏っている
(出典:『予測不能の時代 : データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』、矢野和男、草思社、2021年。「第2章 新たな幸せの姿」の章内の、「幸せな組織の普遍的な4つの特徴「FINE」」の項目より)
上の矢野和男さんの動画の「21:11~23:41」のところで、「幸せは性格ではなく、訓練で身につけるスキルである」という話がされています。そして、それを身につけるための要素として、「HERO(ヒーロー)」(幸せを高める4つの能力(心の資本))という言葉が紹介されています。それについては、矢野和男さんの著書『予測不能の時代』のなかで、次のように説明されています。
このスキルとして身につけられる持続的な幸せの姿を、より具体的に示したのが第2章でも紹介した、ネブラスカ大学の名誉教授で、アメリカの経営学会の会長も務めた組織行動学の権威、フレッド・ルーサンス教授である。
ルーサンス教授らは、既に学界で研究されていた個人や組織の好ましい状態を数値化するさまざまなものさし、あるいは尺度のなかに、訓練や介入によって高められ、幸せと生産性にポジティブな影響を持ち、学術的にデータで検証済みの尺度を見出す研究を推進した。このために、経営学や心理学において研究されてきたさまざまな概念や尺度を網羅的に調べたのである。この結果、持続的で学習可能な幸せを表す重要な尺度が、既に複数、見出されており、それが以下の4つの力であることを明らかにした [4ー5]。
- 第1の力 ホープ(Hope)自ら進む道を見つける力
- 第2の力 エフィカシー(Efficacy)現実を受けとめて行動を起こす力
- 第3の力 レジリエンス(Resilience)困難に立ち向かう力
- 第4の力 オプティミズム(Optimism)前向きな物語を生み出す力
経営学や心理学の専門用語としてのホープなどの言葉の意味は、日本語の「希望」などのニュアンスとは、ずれがあるので、ここでは誤解を避けるために、敢えて訳さず原語のままとする。
これらの4つの尺度は、それぞれ単独でも専門書が書けるテーマであり、それぞれを深めてきた研究者たちが存在していた。ルーサンス教授は、前記の明確な基準を設け、持続的で訓練や学習が可能な幸せという観点で、それらの研究を統合したのである。
ルーサンス教授は、この4つを合わせて「心の資本(Psychological Capital)」と呼んだ。4つの尺度の頭文字を取って、「HERO within」(HERO=Hope-Efficacy-Resilience-Optimism)とも呼ばれる。「内なるHERO〔ヒーロー〕」という意味で、とても語呂もよい。
「資本」という言葉には、将来に向けて「蓄積できるもの」という意味がある。このため、刹那的で享楽的な幸せとは一線を画し、身につけられ、しかも社会に貢献可能な幸せに、この名称をつけたのである。そして、この心の資本こそが、予測不能な変化の中で最も必要なことなのだ。
(出典:『予測不能の時代 : データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』、矢野和男、草思社、2021年。「第4章 幸せとはスキルである」の章内の、「幸せを高める能力「心の資本=HERO」」の項目より)
「ウェルビーイングを向上させることで生産性を高めるための重要な要素」については、下記のように説明されています。(下記の文章は、『戦略的人的資本の開示 運用の実務』という本からの引用です)。(※「従業員エンゲージメント」というのは、「従業員が、自社や仕事に対して愛着や誇りを持ち、自発的に貢献しようとする心理状態(行動意欲)」のことです。)
北米地域を中心にさらなる従業員エンゲージメント〔行動意欲〕の向上を図るために、2019年頃から「エンプロイー・エクスペリエンス」が新たなトレンドとなってきている。エンプロイー・エクスペリエンスとは、従業員(エンプロイー)を顧客に見立て、一人ひとりが心身が健全で社会的に良好な状態でいる「ウェルビーイング」を体験(エクスペリエンス)できることで自律的に生産性を持続的に上げていく考え方である。〔中略〕
従業員の幸福度を増幅し、生産性を持続的に向上させるエンプロイー・エクスペリエンスに必要な要素としては、ウェルビーイングに直接的に関連するものとして「健康」「家族」「通勤」「財政面の健全さ」などがあり、関連性は間接的であるが重要なものとして「(仕事上の)価値観」「職責(仕事内容)」「キャリアに対する姿勢」などがある。これ以外にも、ハード面だけでなく心理的安全性などが保たれて働きやすい職場環境に変革する「ワークプレイス・エクスペリエンスの向上」なども不可欠な要素といわれる。
こうした要素に配慮がなされて、ウェルビーイングが実感できることで持続的なパフォーマンスが発揮できるようになる。
(出典:『戦略的人的資本の開示 運用の実務 : 必須知識の体系的整理と実戦的戦略策定ガイド』、HRテクノロジーコンソーシアム [編集]、日本能率協会マネジメントセンター、2022年。「第6章 開示に向けた実践的アプローチ」の章内の、「4 人的資本における推奨項目のトレンド」の節内の、「従業員エンゲージメントからエンプロイー・エクスペリエンスの向上へ」の項目より)
GDW(国内総ウェルビーイング、国内総充実)ってなに?
今はまだ、ウェルビーイングを計る指標の、世界標準が決まっていません。
内閣府のシンクタンクである、経済社会総合研究所が発表した、調査研究レポート「Well-being “beyond GDP” を巡る国際的な議論の動向と日本の取組」では、次のように、「世界では、国連や、OECD(経済協力開発機構)などの、国際機関や各国が、ウェルビーイングを測定する指標の世界標準を策定するために動いている」ということが述べられています。
世界金融危機以降、GDP では捉えられない人々の満足度(Well-being)や経済社会の進歩の計測、その政策への反映に多くの国が取り組んできたが、コロナ禍を経て改めてその意義に注目が集まり、以前から取組の中心であった欧州、大洋州などに加え、アジア各国においても関心が高まっている。
こうした中、OECD や国連などの国際機関がWell-being の計測方法やGDP を補完する(Beyond GDP)指標群についての国際的な基準作りの議論を加速している。
OECD は従来からWell-being の動向を把握するためのフレームワークや「主観的 Well-being」の計測ガイドラインの策定に取り組んできたが、依然として国による違いも大きいことから、一層の標準化に向けた検討を行っている。国連は SDGs 目標達成の観点からGDP を補完する指標群の選定と合意を目指している。関係する機関や各国政府が連携しながら作業に当たっており、本年から来年にかけて取りまとめが行われる見込みである。
Well-being に関する国際的な基準作りには一定の意義があるものの、実際の計測や国際比較に当たっては様々な論点がある。Well-being を高める経済政策実現の観点から日本としても国際的な議論に参画していく必要がある。
(出典:内閣府経済社会総合研究所「Well-being “beyond GDP”を巡る国際的な議論の動向と日本の取組」、3ページより)
上記のような、国際機関や各国が動いている状況のなか、日本発のウェルビーイングの指標として注目されているのが、「GDW」(国内総ウェルビーイング、国内総充実)です。
衆院議員の下村博文さん(当時)は、第204回国会の、衆議院の予算委員会(2021年2月4日開催)にて、下記のお二人に対して、ウェルビーイングや、GDW(国内総ウェルビーイング、国内総充実)について、下記のような発言をされています。その映像は、下の動画の「1:13:13~1:19:09」のところで見ることができます。(※下村博文さんは、文部科学大臣・教育再生担当大臣や、菅政権で政調会長を務めた人です。)
- 内閣総理大臣の菅義偉さん(当時)
- 文部科学大臣、兼、教育再生担当大臣の萩生田光一さん(当時)
▼下村博文さんの発言
(内閣総理大臣の菅義偉さんに対する質問)
〔前略〕
1:13:13
最後に、ウェルビーイング、幸福を実感できる社会に向けた取組について伺います。
私は、GDPの拡大が重要なのは当然でありますが、全ての人がウェルビーイング、幸福を実感できる社会をつくり上げることが政治の役割だと考え、私が政調会長になってから、自民党の中に日本ウェルビーイング特命委員会を、これまでのPT〔プロジェクトチーム〕から格上げいたしました。
イギリスではブレグジット投票の前に実はこの主観的幸福度が下落していた、エジプトではアラブの春の前にこの主観的幸福度が下落していたというふうに、幸福度と政治経済は深く結びついているというふうに思います。
こうした中で、世界では、国連でもOECDでもこのウェルビーイングという指標が、取り組んで、既につくっておりますが、ニュージーランドでは二〇一九年から、具体的に幸福予算と名づけ、ウェルビーイング重視の予算編成を行っております。コロナ禍にありまして、国民の視点で幸福を高める政策をどう実現するかが重要になっています。我が国においても、本格的にウェルビーイング重視の政策形成にかじを切るべきではないでしょうか。
そこで、これまでのGDPから、国民一人一人のウェルビーイング、幸福、充実度、これを測る物差しとして、GDPからGDW、国民総充実度、新たな物差しとして考えたらどうか〔中略〕
〔中略〕
▼下村博文さんの発言
(文部科学大臣、兼、教育再生担当大臣の萩生田光一さんに対する質問)
1:16:30
このウェルビーイングの観点で、価値観を変えることが重要な分野の一つが教育であります。
〔中略〕
1:17:13
一人一人が幸せになるための教育という観点から大胆に日本の教育を再検討していくことが重要だと思います〔後略〕
(※上の動画のなかの、「下村博文さんの、ウェルビーイングについての発言の映像」は、「衆議院インターネット審議中継」のウェブサイト内の、「2021年2月4日の予算委員会の映像」でも視聴できます。その映像のなかの「1:23:05~1:29:00」のところで、上記の下村博文さんの発言の映像が視聴できます。)
さきほど紹介した、内閣府経済社会総合研究所のレポートで、「Well-being を高める経済政策実現の観点から日本としても国際的な議論に参画していく必要がある」と述べられているように、日本の政財界も、「ウェルビーイングを測定する指標の世界標準」の策定に参画するために、積極的に動いています。
いま、世界中の国々や国際機関が、自分たちが策定したウェルビーイングの指標を、世界標準の指標にしようという動きを見せています。こうした動きは、次の時代に大きな影響力を持つのは誰になるか、ということをめぐる動きでもあります。
たとえば、国連でも、ウェルビーイングの指標の世界標準を策定しようという、同じような動きがあります。具体的には、2024年5月に、国連統計委員会(UNSC:United Nations Statistical Commission)が、国連経済統計家ネットワーク(UNNES)に対して、「ウェルビーイング測定の専門家グループ」を設立するように要請を出しています。
そのような、ウェルビーイングの指標策定をめぐる世界的なうねりのなかで、日本が国をあげてウェルビーイングの指標の策定を進めている理由のひとつとしては、日本が次の時代に大きな影響力を持つためでもあるのです。
そうした「ウェルビーイングを測定する指標の世界標準」の策定の動きをになっている日本の組織の代表的なもののひとつが、日本版ウェルビーイングイニシアチブという組織です。この組織は、日本が、ウェルビーイングの世界標準の策定に関与することを目指して創設された組織です。
(※「日本版ウェルビーイングイニシアチブ」は、日本経済新聞社が主導している組織なので、「日経ウェルビーイングイニシアチブ」と呼ばれる場合もあります)。
(※ここで言う「イニシアチブ」という言葉の意味は、おおよそ、「課題解決のための取り組みを主導する組織」というような意味だとお考えください。ですので、「ウェルビーイングイニシアチブ」というのは、「ウェルビーイングについての課題解決のための取り組みを主導する組織」というような意味だとお考えください。)
ウェルビーイングの第一人者である石川善樹さんが、日本版ウェルビーイングイニシアチブ(日経ウェルビーイングイニシアチブ)のことを紹介している様子は、下の動画の「3:49~4:17」のところで見ることができます。(※石川善樹さんが代表理事を務めている組織は、日本版ウェルビーイングイニシアチブの協力団体のひとつでもあります。)
3:49~4:17
▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事
日経新聞さんが「日経ウェルビーイングイニシアチブ〔日本版ウェルビーイングイニシアチブ〕」というものを今年〔2021年〕立ち上げました。
そこには、ロート製薬さんや、丸井グループさん、第一生命さんなどの、先進的な企業が参加されていて、ウェルビーイングがいかに企業価値と結びつくのか、という部分の原型となるものを作ろうという動きが始まっています。
(※日本版ウェルビーイングイニシアチブの名称に、「日本版」という言葉が付いている理由は、「ウェルビーイングイニシアチブ」という名称が付いている組織が、ほかにも世界中に複数あるので、それらと区別できるようにするためです。たとえば、有名な組織としては、グローバルウェルビーイングイニシアチブ(Global Wellbeing Initiative)という名称の組織もあります。この組織は、ハーバード大学や、世論調査会社のギャラップ社など、世界各地のウェルビーイングに関する研究者、技術者、国際機関の関係者が集まって設立された組織です。石川善樹さんが代表理事を務めている、ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースは、グローバルウェルビーイングイニシアチブを助成金で支援しています。)
日本版ウェルビーイングイニシアチブは、日本経済新聞社が主導して、ウェルビーイングの専門家や、上場企業などや、各分野の専門家などが集まって創設された組織です。そのメンバーのなかには、ここまでに紹介してきた、下記のウェルビーイングの専門家などの方々もおられます。
▼日本版ウェルビーイングイニシアチブのメンバーの方々
- 岡島悦子さん:日本版ウェルビーイングイニシアチブ 円卓会議 議長。プロノバ 代表取締役社長。ユーグレナ 取締役。丸井グループ 社外取締役。KADOKAWA 社外取締役。スマートニュース 社外取締役。
- 篠田真貴子さん:日本版ウェルビーイングイニシアチブ 円卓会議 副議長。元マッキンゼーの経営コンサルタント。
- 伊藤邦雄さん:日本版ウェルビーイングイニシアチブ 経営委員会 座長。一橋大学CFO教育研究センター長。経済産業省が主催する各種プロジェクトの座長として、「伊藤レポート」や「人材版伊藤レポート」を発表。人的資本経営コンソーシアム会長。
- 鈴木寛さん:日本版ウェルビーイングイニシアチブ 社会指標委員会 座長。自由民主党の日本Well-being計画推進特命委員会 統計調査ワーキンググループ 委員長。元参議院議員。東京大学 公共政策大学院 教授。慶應義塾大学 政策メディア研究科 兼 総合政策学部 教授。
▼日本版ウェルビーイングイニシアチブの協力団体である、公益財団法人ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースの役員・評議員の方々
- 石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースの代表理事。ウェルビーイング学会 理事。ウェルビーイングの専門家。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で医学の博士号を取得。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学など。
- 前野隆司さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースのアカデミックアドバイザー。ウェルビーイングの専門家。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM) 教授。
▼日本版ウェルビーイングイニシアチブの「Well-being有識者インタビュー」でインタビューされている方々
下記は、日本版ウェルビーイングイニシアチブの会員企業のリストです。
▼Well-being Initiative会員企業(一部)
- アサヒ飲料株式会社
- 味の素株式会社
- EY Japan
- NECソリューションイノベータ
- 江崎グリコ
- MS&ADインシュアランスグループ
- SUN FRONTIER(サンフロンティア不動産)
- 住友生命
- 第一生命グループ
- 東京きらぼしフィナンシャルグループ
- 東宝
- TOPPAN(トッパン)
- 日清食品
- 日本航空(JAL)
- JT(日本たばこ産業)
- Nestle(ネスレ)
- PERSOL(パーソル)
- BSテレ東
- 富士通
- ポーラ・オルビスグループ
- 丸井グループ
- 三井住友トラスト・グループ
- 三井不動産
- 森永乳業
- ライズ・コンサルティング・グループ
- 日本経済新聞社
日本版ウェルビーイングイニシアチブが、日本発のウェルビーイングの指標として打ち出しているのが、「GDW」(国内総ウェルビーイング、国内総充実)です。
この「GDW」という名称には、ウェルビーイングが、旧来の「GDP」(国内総生産、グロス・ドメスティック・プロダクト)に並ぶ、重要指標である、ということがあらわれています。
下の動画は、ウェルビーイングや、「GDW」(国内総ウェルビーイング、国内総充実)について、解説してくれているので、参考にしてみてください。語り手は、AIや量子コンピューターの分野でも有名な、北川拓也さんです。北川さんは、石川善樹さんが代表をされている、財団法人ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースの理事です。(北川拓也さんは、史上最年少の楽天の常務執行役員になったことでも有名な人です)。
▼ 0:05~1:08:24ちなみに、上の動画で話をしている北川拓也さんは、AIや量子コンピューターの分野でも有名な人です。そのような、科学技術の最先端にいる北川さんのような人も、ウェルビーイングについての取り組みをしています。このことも、ウェルビーイングが、社会的に重要なことがらであるということの傍証ではないかと思います。
下の動画の「42:04~43:36」のところでは、北川拓也さんが、「人類の目標」としてのウェルビーイングや、北川さんご自身がウェルビーイングについての財団を運営されていることについて、話をされています。また、「10年後に人類は幸福になれるのか」という話題や、AIや量子コンピューターとウェルビーイングの関連性についての話もされています。
▼ 42:04~53:10国策(国家プロジェクト)としてのウェルビーイング
日本では、ウェルビーイングが、国策(国家プロジェクト)となっています。
そのことは、さきほども紹介した下の動画(第212回国会における、内閣総理大臣の所信表明演説の映像)で、岸田文雄総理が、ウェルビーイングについて、次のように述べていることにもあらわれています(33:46~34:18)。
持続的な賃上げに加えて、人々のやる気、希望、社会の豊かさといったいわゆる「ウェルビーイング」を拡(ひろ)げれば、この令和の時代において再び、日本国民が「明日は今日より良くなる」と信じることができるようになる。日本国民が「明日は今日より良くなる」と信じられる時代を実現します。
また、下の動画(第214回国会における、内閣総理大臣の所信表明演説の映像)では、石破茂総理が、ウェルビーイングについて、次のように述べています(15:04~15:30)。
私は、国全体の経済成長のみならず、国民1人当たりのGDPの増加と、満足度、幸福度の向上を優先する経済の実現を目標とします。そのために、官民で総合的な「幸福度・満足度」の指標を策定・共有し、一人一人が豊かで幸せな社会の構築を目指します。
日本版ウェルビーイングイニシアチブの、社会指標委員会の座長である鈴木寛さんは、ウェルビーイングについてのインタビュー記事のなかで、下記のようなことを述べています。
(※鈴木寛さんのプロフィール:自由民主党の日本Well-being計画推進特命委員会 統計調査ワーキンググループ 委員長。元参議院議員。東京大学 公共政策大学院 教授。慶應義塾大学 政策メディア研究科 兼 総合政策学部 教授。)
- 世界的な潮流として、ウェルビーイングを政策に取り入れる動きがあること。
- 世界中の国々や機関が、独自のウェルビーイング指標を提案していること。
- そうした世界の動きのなかで、日本が新しい指標として打ち出しているGDW(国内総ウェルビーイング、国内総充実)の動向や、その将来性。
上記の話のくわしい内容については、下記の「鈴木寛さんへのインタビュー記事」の文章をご参照ください。
▼鈴木寛さん:日本版ウェルビーイングイニシアチブ 社会指標委員会 座長
日本は1990年代に国民一人当たりのGDP(国内総生産)が世界トップクラスになりました。しかし私は当時から「経済的な豊かさを得ただけで、日本人は本当に幸せになったといえるのか」という疑問を抱いていました。〔中略〕
そのころ世界ではすでに幸福度を政治に取り入れる動きが始まっていました。例えばフランスのサルコジ大統領は、ノーベル経済学賞を受賞したスティグリッツらに呼び掛け「経済成果と社会進歩の計測に関する委員会」を立ち上げました。彼らの大きな業績としてGDPでは測れない国民の幸福を数値化するために、適切な指標をピックアップしようと試みたことが挙げられます。そのほかにもいくつかの欧州諸国では幸福度を測る試みが始まり、個人と社会の幸福の両立を重んじる政策が採られるようになっていったのです。
こうした先進的な取り組みの結果、2011年には OECD(経済協力開発機構)で「より良い暮らし指標(Better Life Index:BLI)」というウェルビーイングに関する国際的な指標がつくられました。その後、先進国はGDPに代わる指標としてBLIを経済社会政策に取り入れる方向に本格的にシフトしていきました。
〔中略〕現在、日本政府はウェルビーイング計画に本気で取り組んでいます。先日ウェルビーイングを国策の様々なレベルで組み込んでいくという閣議決定レベルのコンセンサスがとられました。これは大きな進歩で、達成できたのは画期的なことです。
日本社会がかかえる次の課題は何でしょう。私の考えでは他の先進国と同水準でウェルビーイングを数値化できるようにすることだと考えています。「主観的幸福」を構成する要素をある程度数値化できれば、思わしくない結果の項目の理由を分析できるからです。そうすることで初めて効果的な対策を打ち出せますし、施策の効果を測定することもできます。〔中略〕
日本はこの BLI や WHR(世界幸福度報告)の調査で計測や提出できない項目がまだいくつかあります。例えば「主観的な幸福度」です。したがってまず計測できる項目を世界水準に追いつくことが必要です。
世界を見渡せば、英国ではカーネギー財団が提唱したGDWe(国内総ウェルビーイング)という指標を国政に反映していますし、米国ではGNW(国家総健康もしくはウェルビーイング)について民間会社が月間ペースでレポートを出しています。日本での新指標となるGDW(国内総充実)については、現状年1回の発表が目標〔中略〕
今回の政府の成長戦略や骨太方針に「ウェルビーイングを実感できる社会をつくる」と書いてあります。それはつまり社会を構成するすべての人々や組織が共感しあい、幸福の好循環を作っていくということです。GDWが果たすべき役割は施策の妥当性を確認するための指標、つまり社会の“体調”を知るための体温計のようなものと考えると良いでしょう。
内閣府は「満足度・生活の質を表す指標群(ダッシュボード)」をまとめていますが、これをウェルビーイング・インデックスに移行しようとしています。具体的には11分野に分けて調査している国民生活に主観的ウェルビーイングを追加して12項目にすると検討しています。産官学でGDW関連統計指標をつくり、それを内閣府ホームページで公表すべく議論しています。
〔中略〕
世界は SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて動き始めていますが、その次の目標はウェルビーイングになるでしょう。すでに「ウェルビーイングを実感できる社会の形成は、国が果たすべき役割として重大である」という価値観の大転換が起こっています。
SDGs の議論は主に欧州がけん引した印象がありますが、ウェルビーイングへの転換の際は日本がイニシアチブを取ることができれば世界から尊敬される国になるでしょう。たとえ経済的には後退しても世界の歴史を切り開く側に回り、模範となる社会に転換する大事な時期だと思います。そのためには政治だけでなく学術界や企業、市民社会などの幅広い協力が不可欠です。
〔中略〕
この30年間は GDP を基準にして見れば、「失われた30年」だったかもしれません。しかし時代の転換期にあって、様々な衝突や混乱を抱えている日本はある意味、時代の最先端にいるともいえます。
(出典:日本経済新聞社「GDW」のウェブサイト内の「Well-being有識者インタビューVol.4 鈴木寛氏」のページより)
ウェルビーイングの第一人者である石川善樹さんは、下の動画で、ウェルビーイングをめぐる、近年の世の中の大きな流れの変化について述べています。下の動画の「3:30~20:07」のところでは、経済的な観点や、安全保障の観点からも、国家がウェルビーイングに取り組む必要がある、ということが述べられています。
3:30
▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事
1)いま日本(成熟経済下)では何が起きているか?
岸田文雄首相が、総理大臣の所信表明演説で、ウェルビーイングについて言及しました。〔中略〕日本の総理大臣がウェルビーイングという言葉を使ったのは、多分歴史上初めてだと思います。〔中略〕ウェルビーイングという言葉が使われ始めたということは、時代の流れとしてウェルビーイングが普通の言葉になってきたということです。〔中略〕
5:10
令和5年度(2023年)の骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針)で、すべての府省庁および地方自治体において、ウェルビーイング指標を導入することが求められることになりました。〔中略〕
7:10
「経済」がテーマなのに、なぜいま、ウェルビーイングなのか?〔中略〕
15:23
Q. ウェルビーイングが悪化すると、何かいけないの?〔中略〕
〔ウェルビーイングが低下すると、紛争や諍い(いさかい)が起こりやすくなる。〕
18:35
Q. なぜ、ウェルビーイング実感が重要なのか?
A.国内のウェルビーイング実感の悪化は、必ずしもGDPと連動するわけではなく、かつ、その後の社会的混乱の先行指標となっている。〔中略〕
〔ウェルビーイングと危機的状況のあいだには、下記のような関係があることが実証された。〕
「社会のウェルビーイング悪化は、国のリスク」
「従業員のウェルビーイング悪化は、組織のリスク」
また、前述のように、国連のなかにも、ウェルビーイングについての専門的な組織がつくられています。具体的には、UNSD(国連統計部(旧国連統計局))のなかに、ウェルビーイング測定の専門家委員会が設置される予定になっています。こうした動きも、国家レベルでウェルビーイングの重要性が高まっていることのあらわれのひとつかもしれません。
ちなみに、ウェルビーイングは、「国家の政策の成果指標」としてだけでなく、「地方自治体の政策の成果指標」としても活用されています。
その一例として、富山県庁のウェルビーイングに対する取り組みを紹介します。上で紹介した石川善樹さんの講演の動画は、富山県庁の職員向け研修として、富山県が主催した講演の映像です。そのようなウェルビーイングについての講演を富山県が主催している理由は、富山県が、県民のウェルビーイングを向上させる政策を推進しているからです。そのような富山県のウェルビーイング政策を象徴するものとして、「富山県 知事政策局 企画室 ウェルビーイング推進課」によって運営されている、「富山県 わたしの、みんなのウェルビーイング・アクション!」という名前の、富山県公式のウェブサイトがあります。
そのような、富山県の取り組みからもわかるように、ウェルビーイングは、「会社の経営指標(成果指標)」や、「国家の政策の成果指標」としてだけでなく、「地方自治体の政策の成果指標」としても活用されています。
GDPとウェルビーイングは相互に支え合う
前述の、GDPについての説明のところで、「GDPには、致命的な問題点があり、批判も多い」という話を紹介しました。ですが、だからといって、GDPを無くして、ウェルビーイングだけを唯一の指標にすればいいのかというと、そうではありません。GDPとウェルビーイングは、どちらも必要なものです。どちらか一方だけがあればいいというわけではないのです。GDPとウェルビーイングは、おたがいに支え合い、補完し合う関係のものです。
内閣府のシンクタンクである、経済社会総合研究所が発表した、調査研究レポート「Well-being “beyond GDP” を巡る国際的な議論の動向と日本の取組」では、次のように、「ウェルビーイングが、GDPを補完する指標になる」ということが示唆されています。
OECD や国連などの国際機関がWell-beingの計測方法やGDP を補完する(Beyond GDP)指標群についての国際的な基準作りの議論を加速している。
〔中略〕
国連は SDGs 目標達成の観点からGDP を補完する指標群の選定と合意を目指している。
(出典:内閣府経済社会総合研究所「Well-being “beyond GDP”を巡る国際的な議論の動向と日本の取組」、3ページより)
前述の経済学者のダイアン・コイルさんも、その著書『GDP』のなかで、GDPの問題点を挙げる一方で、依然として、GDPが必要であることを述べています(下記の引用文参照)。
(※ダイアン・コイルさんの経歴:経済学者。ケンブリッジ大学教授。ハーバード大学で経済学の修士号と博士号を取得。イギリス財務省のアドバイザー、BBCの監督機関の会長代理などを歴任。経済学への貢献によって大英帝国勲位を受勲。)
私は、GDPを今すぐ投げだすべきではないという結論を示そうと思う。ただし、GDPという指標が時代に合わなくなっているのも事実だ。ダラス連銀のレポートにもこう述べられている。「GDPは大量生産に合わせてつくられた統計である。そのやり方は単純に、数を数えるというもの。何個つくられたかがすべてであり、形のない価値は測れないのだ。……変化は人生のスパイスというように、何ごとも量がすべてではない」。経済のあり方が変化している以上、それを測るやり方も変わらざるをえない。
(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、127ページより)
このように、国家にとって、「GDPとウェルビーイング」は、どちらも重要なものなので、「ウェルビーイングだけを重視していればいい」というわけではありません。これと同じような話としては、会社の場合は、「利益(業績)とウェルビーイング」は、どちらも重要なものなので、「ウェルビーイングだけを重視していればいい」というわけではありません。そのことについて、日本版ウェルビーイングイニシアチブの円卓会議で副議長を務める、篠田真貴子さんは、「どちらか一方ではなく、利益とウェルビーイングの両方が重要である」ということを、次のように述べています。
これはまだ理解が広まっていない点ですが、事業戦略とウェルビーイングを考える際には、企業が財務的な利益を出すことが前提であり、利益とウェルビーイングを好循環させる構造を作ることがウェルビーイングの事業戦略の根幹になります。利益と社会活動の二者択一ではなく、双方が高め合うことが重要であり、未来社会ではそれが企業存続の必要条件になってくると考えています。
(出典:日本経済新聞社「GDW」のウェブサイト内の「Well-being有識者インタビューVol.2 篠田真貴子氏」のページより)
CWO(最高ウェルビーイング責任者)と CHRO(最高人材責任者)の役割
ちなみに、ウェルビーイングを重視している会社のなかには、「CWO(最高ウェルビーイング責任者)」や、「CHRO(CHO)(最高人材責任者、または、最高人事責任者)」という役職を設けて、積極的にウェルビーイングを推進している会社もあります。
たとえば、下の動画の「4:32~6:27」のところで自己紹介をしている、丸井グループ 取締役上席執行役員 CWO の小島玲子さんも、CWO(最高ウェルビーイング責任者)を務めている人の一例です。
また、下の動画の「2:23~3:54」のところで自己紹介をしている、サイバーエージェント 常務執行役員 CHO の曽山哲人さんも、CHO(最高人事責任者)を務めている人の一例です。
▼ 下の動画の出演者の方々のプロフィール
- 石川善樹:公益財団法人Wellbeing for Planet Earth 代表理事
- 小島玲子:丸井グループ 取締役上席執行役員CWO
- 曽山哲人:サイバーエージェント 常務執行役員CHO〔最高人事責任者〕
- 岡島悦子:プロノバ 代表取締役社長
▼ 2:23~3:54 曽山哲人さんの自己紹介
下の動画の「6:21~7:50」のところで自己紹介をしている、楽天グループ常務執行役員 CWO の小林正忠さんも、CWO(最高ウェルビーイング責任者)を務めている人の一例です。
また、下の動画の「2:20~5:38」のところで自己紹介をしている、メルカリの CHRO の木下達夫さんも、CHRO(最高人材責任者)を務めている人の一例です。
▼ 下の動画の出演者の方々のプロフィール
- 木下達夫:メルカリ CHRO(最高人材責任者)
- 小林正忠:楽天グループ株式会社 常務執行役員 CWO(最高ウェルビーイング責任者
- 矢野和男:日立製作所 フェロー/株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO
- 山口文洋:LITALICO 代表取締役社長
- 岡島悦子:プロノバ代表取締役社長
▼ 2:20~5:38 木下達夫さんの自己紹介
前述のPERMA(パーマ)についての話のところで紹介した、島田由香さんは、ユニリーバ・ジャパンで人事部門のトップである取締役人事総務本部長を務めた方です。その当時の肩書きの名称は、CHRO(最高人材責任者)ではなかったものの、実質的には、今の言葉で言うところの CHRO の役職をされていた方なので、ここで紹介させていただきます。(下の動画の「9:15~43:51」参照)。
▼ 9:15~43:51人的資本経営
前述のウェルビーイングに関連して、近年重要視されているのが、人的資本経営です。人的資本も、投資家や経営者が、これからの新しい時代に成長する会社のあり方を考えるうえでの、重要な経営指標のひとつになっています。
金融市場を動かしている機関投資家のなかには、長期志向で投資をおこなっている投資家も多いです。彼らは、長期間にわたって継続的に企業価値を向上させていくことができる企業を探し求めています。そして、長期的に企業価値を向上させていくための重要な要素のひとつが、人的資本です。
伊藤邦雄さん(一橋大学CFO教育研究センター長)は、人的資本経営について、こちらの動画の「15:17~20:01」のところで、下記の2つのことを語っています。
(※伊藤邦雄さんは、人的資本経営について書かれている「人材版伊藤レポート」という有名なレポートの作成を主導した人です。「人材版伊藤レポート」は、人的資本経営によって企業価値を高めるためのアイディアを提示しているレポートです。また、伊藤邦雄さんは、経済産業省が主催する各種プロジェクトの座長として、「伊藤レポート」などを作成したことでも有名です。また、人的資本経営コンソーシアム会長でもあります。)
▼伊藤邦雄さん:一橋大学CFO教育研究センター長
-
15:17~18:30
投資家側は、人的資本経営を重視していて、人的資本についての情報開示を求めているものの、企業側は、その要求に応えられていない、という乖離がある。 -
18:30~20:01
投資家が、人的資本についての情報開示を求めている理由。
上記リンクの動画で語られている上記の2点のことがらの背景には、3つの変化の潮流があります。その3つというのは、「人的資本経営が注目されるようになっている要因」として、伊藤邦雄さんが挙げている下記の3つの潮流です。(下記の文章は、伊藤邦雄さんの著書『企業価値経営 第2版』からの引用です)。
無形資産の中でもとりわけ近年注目されている概念の1つが,人的資本である。人的資本が注目されている背景として,以下の3つの潮流があげられる。
第1に無形資産の中でも人的資本が特に企業価値の決定因子として重要な役割を果たすという認識が広がりつつあることが指摘できる。ブラックロックやステート・ストリートなど主要なグローバル投資家が人的資本や企業文化を最優先のエンゲージメント事項として位置づけている。また EY Center for Board Matters の2019年の調査によれば,Fortune500企業の株主総会招集通知の82%が,人的資本に関するテーマを取り上げていることを説明している。投資家と経営者との間の対話・エンゲージメントにおいて人的資本が重要なテーマとなりつつあるのである。本章でも取り扱った価値協創ガイダンスは,経営者と投資家,有識者から構成される研究会の成果物であるが,その中でも価値創造プロセスにおいて重要な要素の1つとして人的資本がクローズアップされている他,米国のSASB〔サステナビリティ会計基準審議会〕〔中略〕においても人的資本を企業価値創造の中核の1つに位置付けている。
第2に,規制当局が人的資本の拡充をめぐる討議を進めている点である。米国証券取引委員会(SEC)は2016年より現代ディスクロージャーで改善すべき点の棚卸を行っているが,人的資本がリスク情報と並んで改善すべき開示テーマとして取り上げられている。2020年10月に公表された Regulation S-K 項目の現代化においては,原則主義に基づき,事業の説明において重要となる人的資本をめぐる取り組みや目的についての開示を行うよう求めている。EUなどでは非財務情報の開示要件として,取締役の多様性に加えて,従業員の取り扱いについても透明性高く開示することを求めており,投資家やその他ステークホルダーの要求の高まりが規制当局を後押ししていることが確認できる。
第3に,〔中略〕企業価値の創造の源泉である人的資本をより適切に評価・測定する枠組みの必要性が高まっている点である。たとえば,World Economic Forum〔世界経済フォーラム、通称ダボス会議〕で2020年8月に「資産としての人的資本――新たな働き方世界における有能な人材の価値をリセットするための会計フレームワーク」を提唱しており,企業の枠を超えたエコシステムで,中長期的な価値創造を促す人的資本の会計フレームワークの必要性を主張している。
(出典:『企業価値経営 第2版』、伊藤邦雄、日経BP、2023年。「第14章 無形資産の価値評価と戦略的活用」の章内の、「14-6 人的資本の評価・測定」の節より)
「投資家が、人的資本やウェルビーイングについて大きな関心を持っている」ということについては、下記のような説明もあります。(下記の文章は、『戦略的人的資本の開示 運用の実務』という本からの引用です)。(※「ESG(環境、社会、企業統治)」の詳細については、後述します。)
ESGマテリアリティ〔社会課題の解決のために会社が取り組む重要課題〕は機関投資家の活動のベースとなるものであり、企業との建設的な対話(エンゲージメント)、ESG情報の定性・定量評価、投資判断、議決権行使において活用されている。
〔中略〕国内の代表的なアセットマネジメント会社〔資産運用会社(機関投資家)〕がESGマテリアリティとして掲げたテーマのうち、S(社会)に該当するもの〔中略〕「人権」「人権とコミュニティ」「児童労働・強制労働」「人材戦略」「労働安全衛生」「ウェルビーイング」など人的資本に関連したテーマが挙げられている。機関投資家の「人的資本」に対する関心の大きさが窺い知れる〔後略〕
(出典:『戦略的人的資本の開示 運用の実務 : 必須知識の体系的整理と実戦的戦略策定ガイド』、HRテクノロジーコンソーシアム [編集]、日本能率協会マネジメントセンター、2022年。「第3章 投資家が注目する人的資本開示のポイント」の章内の、「1 投資家の関心のありかを正しく理解する」の節内の、「機関投資家を取り巻く2つの環境変化」の項目より)
「人材版伊藤レポート」の作成を主導した伊藤邦雄さんは、日本経済新聞社が主催する、日本版ウェルビーイングイニシアチブ(日経ウェルビーイングイニシアチブ)の、経営委員会の座長でもあります。このことからも、ウェルビーイングと、人的資本経営の間につながりがあることがおわかりいただけるかと思います。
また、日本版ウェルビーイングイニシアチブのウェブサイトに掲載されている下記の文章では、伊藤邦雄さんが、ウェルビーイングと経営の関係について語っています。下記の文章からも、ウェルビーイングと、人的資本経営の間につながりがあることがおわかりいただけるかと思います。
ウェルビーイングを経営に取り入れるためには、幸せのカタチは多様であるということを理解する必要があります。利益を上げるために、従来最も重視されてきたのが「効率」で、一斉に・一律にやることが正しいとされてきました。しかしこれからは、働き方にもダイバーシティーが必要です。
早く能力を身に付けて出世したい人も認めるし、プライベートに時間を割きつつ、ゆっくり成長したい人も認める。例えば、子育てというライフイベントに注力したい社員もいます。そんな人に「仕事に対してやる気がない」と評価してしまっては、その人のモチベーションが下がり、貴重な人材を失うことになります。
また、若い世代と高齢世代とでは、追い求める幸せがかなり異なります。いまの若い世代は生まれたときから情報社会に生きていて、調べれば独力でできることが増えています。彼らにとって幸福なのは、自分で選択して、選んだことをやり抜くことです。そうすることで、強い精神性も養われます。
一方、従来型の日本企業はというと、上司が課題を与えて、部下がこなすという業務が一般的です。命令されたことに対して、部下には選択の余地がありません。その結果、日本の上層部の多くは「選択する」ということに対して不慣れになってしまいました。
指示を待って完璧に遂行する人材は、日本という狭い市場の中では効率的に成果を上げることができますが、グローバル化が進みたくさんの選択肢があふれた社会の中では、自分で選び取ったことを成し遂げようとする人材のほうが、会社に利益をもたらします。つまり、広い視点でとらえれば、ウェルビーイング経営は、企業がサステナビリティーを獲得するためのプロセスでもあります。
(出典:「Well-being有識者インタビューVol.8 伊藤邦雄氏 | GDW」より)
「伊藤レポート」と「見えない価値」で「稼ぐ力」を高める
日本の企業の「稼ぐ力」を高めるために作られた「伊藤レポート」という有名なレポートがあります。(「伊藤レポート」は、ある意味で、「人材版伊藤レポート」の姉妹編のようなレポートです)。このレポートの作成を主導したのも、伊藤邦雄さん(一橋大学CFO教育研究センター長)です。
(※正確には、伊藤邦雄さんを座長とした、経済産業省の「『持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~』プロジェクト」が、2014年に公表した最終報告書が、一般的に「伊藤レポート」と呼ばれているものです。)
下の動画では、投資家の藤野英人さんが、伊藤邦雄さんの「伊藤レポート」が登場したことによって、日本の企業が良くなっていったということについて語っています(26:09~28:31)。
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
26:09
日本の大企業も、ちょっとずつ変わってきたんですね。
2014年8月に「伊藤レポート」というのが出ました。
伊藤邦雄先生が、「このままの日本じゃダメだ」、「持続可能な成長をしなければいけない」、「ROE(自己資本利益率)を上げよう」、という話をして、主に日本の大企業の改革を迫ってきました。それで急に変わるほど世の中は単純ではありません。
ですが、伊藤邦雄先生は、「伊藤レポート1.0」、「2.0」、「3.0」を出していき、「これから人的資本が大事だね」「ESGも大事だね」「SDGsも大切にしよう」と言いながら、日本の企業を本質的に良くしていこうという流れがありました。
また、外国人投資家のプレッシャーも、どんどん強くなってきて、「日本の企業や経営者は変わりなさい」、「もっと成長を目指しなさい」というプレッシャーをかけるようになってきました。それが結果的にどうなったかというと、ちょっとずつ良くなってきたんですね。
それでコロナがあって、日本も、世界的にも、非常に厳しい経済環境になったわけですけれども、その時にけっこう社長さんが代替わりしたんですね。とくに、コロナが終わったあたりに。トヨタとか、ソニーとか、そういう大手のところも社長さんが変わって、「次の体制に行くぞ」という風に変わってきました。そうやって、だいぶ変わったんです。
伊藤邦雄さんは、「伊藤レポート」で、日本の企業の「稼ぐ力」を高めるために、「ROE(自己資本利益率)8%」という基準を提示したことで有名です。また、伊藤邦雄さんは、その「稼ぐ力」を高めるためには、人的資本を含む無形資産を蓄積することが重要だと語っています。(下記の文章は、そのことに関するインタビューに対して、伊藤邦雄さんが語った言葉です)。
ROE向上のためにこそ、無形資産が重要となる
編集部:伊藤レポートに「見えない価値」という言葉が登場します。具体的にはどのようなものを指すのですか。
伊藤:ROE経営では、ROE〔自己資本利益率〕をブレイクダウンした投下資本利益率(ROIC)をどのようにして高めるかが問題になります。ROICは投下資本の生産性を表す指標で、分母は有利子負債+株主資本、分子は当期純利益です。これを高めるには、無形資産を豊かに蓄積していくことが重要になります。
企業の利益には、無形資産から生まれるリターンが含まれています。その代表的なものは、企業のカルチャー、ブランド、知的・人的資産などです。これらの無形資産は、ROICの計算式の分母に当たる投下資本には入っていません。したがって、分母に参入されない無形資産が増えれば、分子の利益は上がっていき、ROICは上昇します。ROICが高い企業ほど、無形資産経営を実践している傾向が高くなっています。ROEの向上のためにこそ、無形資産の価値は重要になるのです。つまり、人材やブランドの価値を含めた無形資産の蓄積です。
ROEを高めるということは、稼ぐ力を高めるということです。稼ぐ力を高めるには、良質の無形資産を蓄積することです。経営者は、良質の無形資産を使ってリターンに結びつける嗅覚を養うことが必要です。この考え方を理解していれば、人件費を削ることが中長期的に見てROICを上げることにつながらないと気づくはずです。
これは、グローバル経営において最も重要な視点の一つです。だからこそ、中長期の良質な投資家に対して企業価値創造のシナリオを語るべきではないでしょうか。無形資産の重要性は、投資家も理解しています。ROEは結果の数字ですし、数字を見ればすぐにわかることです。いま、経営者に求められているのは、中長期的に収益性を高め企業価値を持続的に高めるためのシナリオです。そのためには、財務指標に表れにくい、「見えない価値」の存在に経営者はより敏感にならないといけないのです。
(出典:『「伊藤レポート」の真意とは (インタビュー 企業も投資家を選ぶ時代) (特集 コーポレートガバナンス)』、伊藤邦雄 [著者]、Diamondハーバード・ビジネス・レビュー編集部 [インタビュー]、ダイヤモンド社、2016年3月。「ROE向上のためにこそ、無形資産が重要となる」の項目より)
(※これまでに発表された伊藤レポートは、下記の3つです。それらのレポートのPDFファイルは、経済産業省のウェブサイト内の「企業と投資家の対話」のページのなかの「伊藤レポート」の項目のところから閲覧できます。)
-
伊藤レポート
「「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト(伊藤レポート)最終報告書」 -
伊藤レポート2.0
「持続的成長に向けた長期投資 (ESG・無形資産投資) 研究会 報告書」 -
伊藤レポート3.0(SX 版伊藤レポート)
「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX 研究会)報告書」
「人材版伊藤レポート」の3つの視点と5つの要素
「伊藤レポート」以外にも、伊藤邦雄さんは、「人材版伊藤レポート」と「人材版伊藤レポート2.0」の作成も主導しました。それらのレポートでは、人的資本経営のための、下記の「3つの視点」と「5つの要素」についての提言がされています。
▼3つの視点
- 経営戦略と人材戦略の連動
- AS is-To beギャップの定量把握
- 企業文化への定着
▼5つの要素
- 動的な人材ポートフォリオ
- 知・経験のダイバーシティ&インクルージョン
- リスキル・学び直し
- 従業員エンゲージメント
- 時間や場所にとらわれない働き方
「人材版伊藤レポート」と、「人材版伊藤レポート2.0」や、「3つの視点」と「5つの要素」の詳細については、下の動画で、EY新日本有限責任監査法人の方々が、くわしく説明してくれています。
▼ 0:00~15:55「人材版伊藤レポート」は、「ESGやサステナビリティについての情報開示のための、国際的な会計基準などの変化の動き」のなかで生まれたものです。その経緯については、下記の文章をご参照ください。(下記の文章は、伊藤邦雄さんの著書『企業価値経営 第2版』からの引用です)。
ESG投資が急速に進む中で,いくつかの課題が指摘されるようになっている。その主たるものの1つは,ESG評価機関が提供するESGスコアが必ずしも一貫しておらず,それが収束しない状況が続いている点である。
〔中略〕
こうした金融コミュニティーの動きに伴い,にわかにESG〔環境、社会、企業統治〕やサステナビリティに関わる情報開示の国際的統合化が進展し始めている。特に会計基準の国際的統合化・収斂化を担ってきた IASB〔国際会計基準審議会〕〔中略〕を統括するIFRS財団〔国際財務報告基準財団〕が2021年11月に ISSB〔国際サステナビリティ基準審議会〕〔中略〕を設立したことを契機にこうした動きが加速している。
〔中略〕
日本では,2020年には「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート」,2022年には「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~人材版伊藤レポート2.0」,「人的資本可視化指針」が公表され,人的資本経営や開示に向けた取り組みが進展している。2023年4月事業開始年度より男女賃金格差,女性管理職比率などを有価証券報告書で開示することを義務付ける方針を打ち出している。
ESGやサステナビリティに関わる取り組みを情報開示に結び付ける国際的な動きは今後も進展していくことが期待される。
(出典:『企業価値経営 第2版』、伊藤邦雄、日経BP、2023年。「序章 価値思考が未来を変える」の章内の、「1-5 ESG開示と評価の革新」の節より)
(※上記の文章で紹介されている、「人材版伊藤レポート」などのPDFファイルは、下記リンクから閲覧できます。)
-
人材版伊藤レポート
「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~」
(経済産業省のウェブページ) -
人材版伊藤レポート2.0
「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~人材版伊藤レポート2.0~」
(経済産業省のウェブページ) -
「人的資本可視化指針」非財務情報可視化研究会
(内閣官房のウェブページ)
人的資本開示で企業価値が上がる会社と、下がる会社
さきほど、「人的資本経営についての情報を、有価証券報告書で開示することを義務付ける動きがある」という話を紹介しました。(※さきほどの、伊藤邦雄さんの著書『企業価値経営 第2版』からの引用文中にあった話です)。
下の動画では、山口周さんと、篠田真貴子さんのお二人が、経営における人的資本の情報開示の重要性などについて、語っています。
▼お二人のプロフィール
- 山口周さん:著作家、経営コンサルタント。『ビジネスの未来』や、『ニュータイプの時代』、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』、『クリティカル・ビジネス・パラダイム』など、著書多数。
- 篠田真貴子さん:日本経済新聞社が主催する、日本版ウェルビーイングイニシアチブの、円卓会議の副議長。元マッキンゼーの経営コンサルタント。
下の動画の「51:32~55:04」で、お二人は、次のようなことを述べておられます。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
51:32
▼山口周さん
人的資本開示義務によって、大きな変化が起こる。〔中略〕
52:10
人的資本開示は、長期の業績に一番影響を与える要素になっています。〔中略〕
53:10
▼篠田真貴子さん
人的資本についての変化に気づいているかどうかで、長期的にものすごく差がつく。〔中略〕
上の動画のなかで、山口周さんが言及している、「人的資本の開示義務の重要性」については、下記の文章をご参照ください。下記の文章では、「人的資本経営が注目されるようになってきた経緯」についても、説明されています。(下記の文章は、『経営戦略としての人的資本開示』という本からの引用です)。
日本企業は、2002年からの20年間で世界における時価総額トップ100のエクセレントカンパニーから、数多く脱落していった。その大きな原因の1つに、過去10年来「人への投資」の不足が挙げられている。このような状況を打破すべく、岸田文雄首相は、2022年1月17日通常国会の所信表明演説において、「新しい資本主義」の時代の幕開けを声高らかに宣言した。その実現のための政策の目玉として、3つが挙げられた。
1つが、何よりも「人への投資」を増やすこと。2つめは、「人的資本経営」の実践。そして3つめは、「人的資本の開示」の推進である。本書は、そのうち、「人的資本の開示」というテーマに焦点を当てている。
一方、海外に目を転じると、「人的資本の開示」は、ESG投資家から注目を集め、すでに欧州連合は2017年から企業に開示義務を課している。2020年には、米国でも米国証券取引所が米国の上場企業に対して、人的資本の開示ルールを30年ぶりに改定した。そして、この世界の流れに対して日本もキャッチアップしようとしており、2022年中に人的資本開示ルールが新たに公表される予定となっている。2022年は、まさに日本における「人的資本開示」元年と言われるようになるだろう。
本書の主な読み手としては、「人への投資」を積極化して企業価値向上を目指す経営者と、人的資本開示の実務を担う部門の実務者、そして、人的資本開示を投資判断材料として重要視する投資家を想定している。
(出典:『経営戦略としての人的資本開示 : HRテクノロジーの活用とデータドリブンHCMの実践』、HRテクノロジーコンソーシアム [編集]、日本能率協会マネジメントセンター、2022年。「はじめに」より)
矢野和男さんは、「人こそが企業の価値の源泉であり、その人的資本を企業評価に反映させるべきである」ということを、著書『予測不能の時代』で次のように説明しています。(※矢野和男さんは、データサイエンスを活用してウェルビーイングを向上させる手法の第一人者であり、日立製作所の特別研究員(フェロー)です。)
予測不能な変化に立ち向かうには人も組織も変わらなければならない。〔中略〕未知の変化に前向きに向き合い続けるのに、〔中略〕データに基づく科学的な知見が生きる。
〔中略〕データに基づく新たな企業やマネジメントの姿をより具体的に論じたい。それがここで論じる「人的資本の定量化」と「ウェルビーイングケア」である。
〔中略〕人の「前向きな心」や「信頼できる関係」は、従来の企業評価では考慮されてこなかった。これまで企業の評価には、専ら財務的な指標が使われてきた。
20世紀には、標準的なプロダクトやサービスを一律に広く安く展開することが幅広い分野で行われた。その中心が生産工場である。この生産工場という産業のエンジンに資本を投下し、それが有形の資産となり、有形資産が大量のプロダクトを生産することで、利益というリターンを生んだ。
ところが今や、価値を生む主体が大きく変化した。GAFA(グーグル/アマゾン/フェイスブック/アップル)などの21世紀を象徴する企業では、価値を生み出しているのは人であり、その知的生産力である。
にもかかわらず、今も企業評価の際には、20世紀型のモデルに沿って、専ら有形資産(モノ)として数値化できる範囲のものについて、どれだけの利益を生み出すかを評価対象にしている。実態としては、人が価値を生み出しているのに、有形資産の価値を前提に評価することしかできず、そのため、実態との乖離が大きくなっている。実際に優良企業ではPBR(株価純資産倍率)が基準となる1を大きく上回っていることが多くなっている。一方で、本来の価値を生み出している「人の価値」が評価できないために、人に対し、適切な投資ができない歪みも生じているという現実もある。
今、価値を生んでいるのは、人という資本である。すなわち「人的資本」だ。人という資本に適切に投資し、企業評価に反映させることは、21世紀の企業と資本主義に求められる重要な要件である。特に、変化する中で新たな価値を生み出せるかどうかは、常に人にかかっているし、それを阻むのも常に人である。
(出典:『予測不能の時代 : データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』、矢野和男、草思社、2021年。「第5章 変化に向き合うマネジメント」の章内の、「今や人こそが企業の価値の源泉」の項目より)
ESG(環境、社会、企業統治)
ESGも、投資家や経営者が、これからの新しい時代に成長する会社のあり方を考えるうえでの、重要な指標になっています。
ESGとは、「環境、社会、企業統治(エンバイロメント、ソーシャル、ガバナンス)」という3つの言葉の頭文字です。ESG投資とは、それらの3つの要素を重視して行われる投資です。具体的には、環境や社会に配慮したビジネスを営み、優れたガバナンス(企業統治)を実践している企業に対して投資を行います。
「ESG(環境、社会、企業統治)を重視した経営をすることで、会社の業績が向上した」という事例はたくさんあります。
たとえば、メルカリの会長である小泉文明さんは、ESGの重要性について、下の動画の「18:50~19:40」のところで語っています。具体的には、ESGの観点から、「循環型社会(サーキュラーエコノミー、循環経済)を実現する」という目標を本気で追い求めていて、そのことが、会社の収益の増加に貢献している、と語っています。また、そうした「世界観」に共感した人たちが集まってきてくれることで、人材採用の面でも良い効果が出ている、という話もしています。
また、スマートニュースの鈴木健さんは、下の動画の「38:28~40:08」のところで、「ミッションを示すことがすごく重要だ」という話をしています。(※鈴木健さん:スマートニュース(SmartNews)共同創業者、取締役会長。『なめらかな社会とその敵 : PICSY・分人民主主義・構成的社会契約論』の著者としても有名。)
▼ 18:50~19:40 小泉文明さん(メルカリ 会長)▼ 38:28~40:08 鈴木健さん(スマートニュース 会長)
ハーバード・ビジネス・スクールの教授で、ESG投資の世界的な権威である、ジョージ・セラフェイムさんは、「ESGを重視する会社は業績も良い」ということについて、次のように述べています。
過去10年の我々の学術論文を見ていただければわかる通り、ESGの必須項目で実績値を改善してきたパーパス主導型の企業は、競合他社より年3%以上も高い株式リターンを毎年達成している。一例に過ぎないが、例えば新型コロナウイルス感染症の大流行時に確固たる取り組みで対応し、顧客・社員・サプライヤーを守ってきた企業は、2020年3月の株式市場大暴落を含む1カ月間だけで、競合他社を2%上回る株式リターンを達成した。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「序論」より)
また、ジョージ・セラフェイムさんは、「投資家や、若い世代の人たちは、積極的にESG投資を選んでいる」ということについて、次のように述べています。
ある調査によれば、投資家のほぼ4分の3はサステナブル投資に関心があり、ミレニアル世代が意識的にESGファンドを選ぶ確率は投資家層全体の2倍になるという。投資判断にESG問題も組み込むよう(投資先企業に)求める年金基金やファミリーオフィスはますます増えており、その点を契約書に明記することまで求めるファンドも、少数とはいえそれなりの数になる。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第7章 変化を後押しする投資家の役割」の章内の、「「囚人のジレンマ」からの脱却」の項目より)
年金を運用するGPIFは、ESG投資で市場平均を上回る収益をあげている
さきほど紹介した、ジョージ・セラフェイムさんの言葉にもあったように、投資先の企業を選ぶときに、「ESGを重視しているかどうか」を、投資判断の基準にしている年金基金や投資家もいます。
たとえば、日本の年金を運用している年金基金である、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、ESG指数を判断基準にした投資もおこなっています。(※GPIFは、250兆円を超える運用資産額をほこる、世界最大級の機関投資家として知られています(2024年度第1四半期末時点))。
GPIFが運用しているESG投資についての紹介ページによると、GPIFのESG投資の運用資産額の合計は、約12.5兆円にのぼります(2022年度末時点)。また、同ページでは、下記のような投資方針が示されています。
GPIFは「長期的な投資収益の拡大には、投資先及び市場全体の持続的成長が必要」との投資原則の考え方に沿って、その運用プロセス全体を通じ、ESGを考慮した投資を推進しています。
下のGPIFの公式動画では、「GPIFが運用しているESG投資」について解説しています。
▼ 0:00~2:44また、下のGPIFの公式動画では、「GPIFが行っているESG投資は、投資パフォーマンスが高い」ということが語られています(7:51~8:41)。
8:12
国内株ESG指数の過去5年間の年率の投資収益は、市場平均であるTOPIX並み、もしくは、それを上回る投資収益を確保しています。
GPIFの投資においては、ESGを考慮しない投資よりもESG投資の方がパフォーマンスが良かったということです。
8:35
外国株のESG指数についても、同様な傾向が確認されています。
渋沢栄一と、ドラッカーと、ESGの関係
一橋大学の一橋ビジネススクール特任教授で、競争戦略の専門家である、楠木建さんは、下の動画で、「長期利益を追求することとESGの関係」について、次のように述べています(43:56~58:13)。
▼楠木建さん:一橋大学 一橋ビジネススクール 特任教授
43:56
シンプルに考える
勝利条件(=長期利益)が明確
「長いこと儲かるためには……」さえ考えておけばだいたいのことがうまくいく
44:05
- Environmental〔環境〕
- Social〔社会〕
- Governance〔企業統治〕
ESG〔環境、社会、企業統治〕が大切なのは、当たり前のことです。
44:14
渋沢栄一は、『論語と算盤』で、「道徳的な商売が一番儲かる」と言っています。
44:47
長期利益=ESG
長期利益経営はほぼ自動的にESG条件を満足させる
なぜなら、企業は社会的な存在だからです。
- E〔環境〕がダメだと、いずれ顧客に選ばれなくなる=儲からない
- S〔社会〕がダメだと、いずれ働き手に選ばれなくなる=儲からない
- G〔統治〕がダメだと、いずれ株主に選ばれなくなる=儲からない
45:08
経営者が、本当に長期利益を追求すれば、それは必然的に、ESGの条件を満たすことになる。
〔ESG / CSV / サステナビリティは、競争市場での〕実需です。
〔中略〕
50:20
すべては、時間軸の取り方に帰結する。
〔短期利益志向だと、経営者、従業員、株主の三者の利害が対立してしまう。〕
〔長期的視点に立つと、経営者、従業員、株主の、三者の利害が一致する。〕
53:50
経営者が対話するべきなのは、長期エンゲージメント株主。
上の動画で、楠木建さんが語っておられる、「渋沢栄一は、『論語と算盤』のなかで、「道徳的な商売が一番儲かる」と言っている」というのは、おそらく、『論語と算盤』の「第4章〔仁義と富貴〕」の章内の、「本当に正しく経済活動を行う方法」というテーマについての記述のあたりのことを指しているのだろうと思います。下記の引用文は、『論語と算盤』のなかの、その部分の現代語訳です。
本当の経済活動は、社会のためになる道徳に基づかないと、決して長く続くものではないと考えている。
このようにいうと、とかく「利益を少なくして、欲望を去る」とか、「世の常に逆らう」といった考えに悪くすると走りがちだが、そうではないのだ。強い思いやりを持って、世の中の利益を考えることは、もちろんよいことだ。しかし同時に、自分の利益が欲しいという気持ちで働くのも、世間一般の当たり前の姿である。そのなかで、社会のためになる道徳を持たないと、世の中の仕事というのは、少しずつ衰えてしまう、ということなのだ。
〔中略〕
利益を得ようとすることと、社会正義のための道徳にのっとるということは、両者バランスよく並び立ってこそ、初めて国家も健全に成長するようになる。個人もちょうどよい塩梅で、富を築いていくのである。
〔中略〕
自分さえ都合がよければと思っていたら、たとえば鉄道の改札を通り抜けるにも、狭い場所で我先にとみながひしめくことになる。これでは誰も通れなくなって困ってしまうのだ。身近な例で考えても、自分さえよければいいという考え方が結局自分の利益にならないのは、この一事を見てもわかると思う。
だから、わたしが常に希望しているのは、
「物事を進展させたい」
「モノの豊かさを実現したい」
という欲望を、まず人は心に抱き続ける一方で、その欲望を実践に移していくために道理を持って欲しいということなのだ。その道理とは、社会の基本的な道徳をバランスよく推し進めていくことに外ならない。
〔中略〕
幸いにして世間一般の進歩とともに金銭に対する観方も随分まともになり、利殖とも道徳とも離れまいとする傾向が高まっている。特に欧米では、
「まっとうな富は、正しい活動によって手に入れるべきものである」
という考え方が、着々と実行されてきている。わが国の若いみなさんも、深くこの点に注意して、金銭のマイナス面に足をとられず、道義と一緒にする形で金銭の本当の価値を利用していくよう努力して欲しい、と望むのである。
(出典:『論語と算盤 : 現代語訳 (ちくま新書)』、渋沢栄一、筑摩書房、2014年。「第4章 仁義と富貴」の章より)
余談ですが、「経営学の父」や、「マネジメントの権威」、「ビジネス・コンサルタントの創始者」などと呼ばれる、ピーター・ドラッカーは、「渋沢栄一は、マネジメントの本質を見抜いていた」として、次のように述べています。
マネジメントというものが、所有権、階級、権力から独立した存在でなければならないことも明らかである。マネジメントとは、成果に対する責任に由来する客観的な機能である。したがって、マネジメントとはプロフェッショナルのものである。それは体系、機能、仕事である。この体系を実践し、この機能を遂行し、この仕事を実行する者が経営陣としてのマネジメントである。もはやマネジメントがオーナーであるかどうかは、重要なことではない。
日本の渋沢栄一が明治の頃に描いた、プロフェッショナルとしての経営陣という儒教的な理想像が現実のものとなった(第2章参照)。マネジメントの本質は、富でも地位でもなく、責任であるとの渋沢の洞察が実現された。
(出典:『マネジメント : 課題、責任、実践 上 (ドラッカー名著 ; 13)』、ピーター・ドラッカー、ダイヤモンド社、2008年。「第1章 マネジメントの登場」の章内の、「マネジメントとはプロフェッショナルの仕事」の項目より)
上記のように、ピーター・ドラッカーが『マネジメント』のなかで、渋沢栄一に言及していることについては、石川善樹さんが、下の動画の「53:13~54:10」のところで述べています。
▼ 53:13~54:10さきほどの動画で、競争戦略の専門家である楠木建さんが語っていた、渋沢栄一さんの『論語と算盤』と長期利益の話や、ESGと利益の両立の話、などについては、下の動画も参考になるかと思います(0:40~8:44)。(以下は、下の動画の内容の抜粋です)。
▼楠木建さん:一橋大学 一橋ビジネススクール 特任教授
0:40
会社にとって重要なのは、長期利益。
1:17
長期的に利益を出し続けるために、どうすればいいかを徹底的に考える。
2:18
渋沢栄一さんの『論語と算盤』
3:35
渋沢栄一さんは、「道徳的であることが一番儲かる」と言っている。
4:10
時間軸の取り方を変えて、長期的視点に立つことで、ESGや、サステナビリティと、利益が、両立するようになる。
5:03
競争戦略の分野の開祖であり、ゴリゴリの資本主義者である、マイケル・ポーターさんは、「〔社会的な価値を重視する〕CSVが一番儲かる」と言っていた。
〔※CSV(共有価値の創造、Creating Shared Value):企業が、社会的な価値と、経済的価値の創出を両立させること。〕
6:37
あらゆる商売は問題解決。今、一番大きな問題は、社会的な問題。大きな問題を解決するほど、儲けも大きい。
6:55
ユニクロも、サステナビリティにかなり投資している。
ペットボトルを再生した糸で作ったポロシャツが売れている。
7:42
今は、ふつうの若者が「そっちのほうが、カッコいいから」という理由で、サステナビリティ関連の商品を買う時代
8:01
つまり、ESG経営論とは、実需です。それは、もう、商売のど真ん中のテーマになっている。
8:38
長期利益を追求すれば、うまくいく。
ちなみに、渋沢栄一さんの玄孫(5世代目の子孫)である、渋澤健さんと、投資家の藤野英人さんの対談を、下の動画で見ることができます(前編、中編、後編)。ご参考までに。
(※渋澤健さんのプロフィール:長期投資家。コモンズ投信株式会社取締役会長、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役。)
▼ 0:00~10:40「会計の終焉」と、無形資産(非財務情報)としてのESG
ESG(環境、社会、企業統治)にまつわる情報の多くは、従来の財務諸表では無視されてきた非財務情報です。そのため、これまでは、ESG情報の多くは、財務諸表の数値に反映されてきませんでした。ですが、現代では、有形資産よりも、無形資産や非財務情報のほうが重要性が高まっています。そのような変化によって、従来の財務諸表は、現実と乖離した役に立たないものになりつつあります。そのような状況に対応するため、ESG情報をはじめとする非財務情報を、財務諸表の数値に反映させようという動きがあります。
伊藤邦雄さんは、「有形資産よりも無形資産のほうが重要性が高まっている」ということの説明を、下の動画の「1:32~3:26」のところでしています。
▼ 1:32~3:26また、柳良平さんも、上の動画の伊藤邦雄さんの説明と同じ主旨のことを、下記のように述べています。(※柳良平さんのプロフィール:製薬会社エーザイ 元CFO。「伊藤レポート」執筆委員。資産運用会社 M&Gインベストメンツジャパン 副社長。早稲田大学大学院 会計研究科 客員教授)。
たとえば、米S&P500企業の市場価値に占める「無形資産 対 有形資産」の比率は、1975年に 2:8 だったのに対して、2015年に 8:2 に逆転したという研究もある〔※下の棒グラフ参照〕。
つまり、企業価値においては、「見えない価値」の重要性が増し、目に見える資本や利益よりも、無形資産の価値が評価されるようになったのだ。
▼ 企業価値の8割を超える「見えない価値」
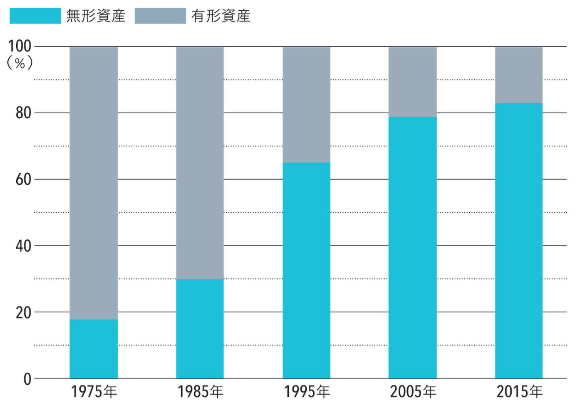
(出典:『エーザイで実証した評価モデルから導く ESGの「見えざる価値」を企業価値につなげる方法 (特集 ESG経営の実践) (ハーバード・ビジネス・レビュー論文)』、柳良平、ダイヤモンド社、2021年1月。「図表2 企業価値の8割を超える「見えない価値」」(一部分)。)
また、「会計の終焉」という言葉で表現されている「財務諸表の企業価値説明力の低下」の問題や、無形資産(ESGについての情報をはじめとする非財務情報)の重要性が高まっていることや、会計情報(財務諸表)に無形資産(非財務情報)を反映させることの必要性などについて、伊藤邦雄さんは、下の動画の「8:54~12:14」のところで説明しています。
▼ 8:54~12:14また、伊藤邦雄さんは、上の動画での無形資産(非財務情報)についての話と同じ主旨のことを、『企業価値経営 第2版』という本のなかで下記のように述べています。また、下記の文中にある「会計の終焉」という言葉は、「財務諸表の企業価値説明力(有用性)の低下」、つまり、「投資家は、重要な判断材料として、無形資産(非財務資本)についての情報を求めているのに、従来の会計では、その要望に応えることができない。そのため、従来の会計は、投資家にとっての有用性を失ってしまった」ということをあらわしています。
企業価値の評価は,それに有用な情報に基づいて行われる。まさに,その有用な情報に大変化が起こっているのである。それは,企業価値の決定因子が有形資産から無形資産へ転換していることである。この事実は国内外のさまざまな文献で実証されている。しかし伝統的なバランスシートには,有形資産に代表される財務情報が記載されている。一方,企業価値の決定因子である無形資産は一部ののれんなどを除けば,ほとんどがオフバランスとなっている。さらに,そうした無形資産は基本的に非財務的性格を持っている。ゆえに伝統的に会計の対象から外されてきたのである。
しかし,企業価値を正しく評価するには,バランスシートに記載されていない無形資産や非財務情報に目を向ける必要がある。
例えば,バルーク・レブ教授は2016年に出版した著書 The End of Accounting (伊藤邦雄監訳『会計の再生』中央経済社,2018年)で膨大な量の実証研究をもとに,過去数十年の間,膨大かつますます複雑となった四半期・年次報告書で伝達される企業の財務情報はその主な利用者である投資家に対する有用性をほとんど失い,従来の財務報告書の企業価値説明力(有用性)がこの半世紀,急速に低下したことを論証している。つまり「有用性喪失」がどんどん進行しているのである。さらに従来の会計モデルは,1世紀にわたって不変であったため,21世紀の資本市場における投資家ニーズに適合しないことを強調している。このことから同教授は「会計の終焉」と喝破した。
まさに企業価値評価に必要な情報が従来の会計情報から無形資産や非財務情報に大きく変化してきているのである。そうした非財務情報の典型がESG情報なのである。機関投資家がESGに強い関心を寄せるのは,こうした地殻変動に照らしてみれば至極当然の行動変容といえる。
(出典:『企業価値経営 第2版』、伊藤邦雄、日経BP、2023年。「第15章 非財務・ESG情報による企業評価」の章内の、「企業価値の決定因子の転換―伝統的会計の限界―」の項目より)
上記の引用文中にあるような「従来の会計」に代わる、「新しい会計」を生み出す動きは、すでに始まっています。
たとえば、「ESG(環境、社会、企業統治)についての取り組みから生まれる「見えない価値」(非財務情報)を、財務諸表の数値に反映させて「見える価値」にする仕組み」としては、下記の2つがとくに有名です。
- インパクト加重会計:ジョージ・セラフェイムさんが提唱。(ESG投資の世界的権威。ハーバード・ビジネス・スクールの教授)。
- 柳モデル:柳良平さんが提唱。(製薬会社エーザイ 元CFO。「伊藤レポート」執筆委員。資産運用会社 M&Gインベストメンツジャパン 副社長。早稲田大学大学院 会計研究科 客員教授)。
インパクト加重会計で、社会と企業が同じ方向を目指す
「ESG(環境、社会、企業統治)についての取り組みから生まれる「見えない価値」を、財務諸表の数値に反映させて「見える価値」にする仕組み」のひとつとして、「インパクト加重会計」というものがあります。
(※ここで言う「見えない価値」とは、これまでは、非財務情報として、財務諸表の数値に反映されてこなかった情報のことです。「インパクト加重会計」によって計測される「見えない価値」(非財務情報)とは、環境や、顧客や、従業員などに与える影響(インパクト)です。)
(※ここで言う「影響(インパクト)」は、「(経済の)外部性」と言い換えることもできます。マイナスの影響(インパクト)を与えている場合は、「負の外部性(外部不経済)」です。プラスの影響(インパクト)を与えている場合は、「正の外部性(外部経済)」です。(参考))
ウェルビーイングの第一人者である石川善樹さんは、「ウェルビーイングを経営に活かす」というテーマの話のなかで、「従業員のウェルビーイングについての情報を財務諸表の数値に反映させるための方法」のひとつとして、「インパクト加重会計」のことを紹介しています。(下の動画の「34:06~36:42」参照)。
(※ちなみに、下の動画の「35:06~36:13」のところでは、会計学とウェルビーイングを組み合わせた分野で、世界的に活躍している日本人として紹介されているスズキトモ(鈴木智英)さんと、彼が提唱している「付加価値分配計算書」(DS:ディストリビューションステートメント)についても、紹介されています。※スズキトモ(鈴木智英)さんのプロフィール:オックスフォード大学博士・元教授、早稲田大学教授、公認会計士、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで社会科学哲学の修士号を取得、オックスフォード大学で会計・経済の哲学の博士号を取得。)
▼ 34:06~36:42「インパクト加重会計」の説明としては、『経営戦略としての人的資本開示』という本で次のように説明されています。
近年注目を浴びているのが、ハーバード大学ビジネススクールのジョージ・セラフェイム教授らが主導している「インパクト加重会計」である。インパクト加重会計とは、利益とインパクトを統合し、企業が社会に与えるインパクトを会計システムに組み込もうと考える新しい手法である。インパクト加重会計は、利益や損失だけでなく、環境、製品(顧客)、雇用(従業員等)の3つのフレームで社会的なインパクトを広範にわたり測定し、貨幣価値換算をすることを試みることで、統合的な業績を示すことを目指しており、投資家や経営者の意思決定に活用されることが期待されている。わが国では、エーザイが初めて雇用(従業員等)インパクトを測定し、価値創造レポートで公表している。
(出典:『経営戦略としての人的資本開示 : HRテクノロジーの活用とデータドリブンHCMの実践』、HRテクノロジーコンソーシアム [編集]、日本能率協会マネジメントセンター、2022年。「第4章」の「第2節」のなかの、「人的資産の測定における会計学アプローチとその特徴」の項目より)
上記の引用文にもあるように、「インパクト加重会計」の第一人者として有名なのは、ESG投資の世界的権威であり、ハーバード・ビジネス・スクールの教授である、ジョージ・セラフェイムさんです。彼は、『パーパス+利益のマネジメント』という本のなかで、「インパクト加重会計」について次のように語っています。下記の文章では、「インパクト加重会計によって、社会と企業が同じ方向を目指して、ともにより良い社会をつくっていくことができる」という考えが示されています。
〔前略〕社会として成功の意味を、いや利益の意味を再定義する必要がある〔中略〕企業の純利益について話すとき、その企業が稼いだ金額だけを考えるのではなく、その企業が世界に与えた(もしくは奪い取った)価値についても必ず考えるようにすべきなのだ。
インパクト加重会計はまさにそれを行う。企業の行ったことをすべて金額に換算するので、我々はその企業の環境へのインパクト、顧客へのインパクト、社員へのインパクト、その他諸々のインパクトを差し引きした後の収益をはじき出せる。財務諸表を見れば真に利益を生み出している企業がわかるようにするため、非財務的指標を財務的指標へと変換するツールを与えてくれるのだ。ちょうど違法薬物を使ったスポーツ選手を我々が称賛しないのと同じように、環境を汚染したり、生活賃金未満の給料しか払わなかったり、顧客の健康を損なう中毒性の高い商品を売ったりして利益をあげている企業も、称賛すべきではない。本物のビジネスリーダーとは、利益を出すと同時に社会にプラスのインパクトを生み出せる人だ。そしてそれは、インパクト加重したEPS(1株当たり利益)を計算することで間違いなく見えてくる。
まとめよう。仮に企業の目的(パーパス)が短期的な利益の最大化であるなら、業績を判断するには収益その他の主要な財務指標を見るだけで問題ない。だが、実際はそうではない。それゆえ、財務指標だけを見て判断すると、極めてゆがんだインセンテイブをつくり出してしまう。企業に財務数値の最大化だけを追いかけてほしくない、と口では言いながらも、結局は財務数値だけで企業を判断しているようでは、望む結果はとうてい得られない。
〔中略〕
会社によって数字がプラスに働くかマイナスに働くかが異なる。結局はそこがポイントだ。インパクト加重会計で分析すると、会社ごとの違いが赤裸々に見える。そして、インパクトの数値がプラス方向に最も大きく加算されるような企業こそ、みんなで注目し、称賛し、真似すべきなのだ。一例としてインテルを見てみよう。同社は、育児休暇や傷病休暇など福利厚生の充実した高収入の仕事を、失業率の高い地域まで含めて提供したことで、ざっと4億ドルのプラスのインパクトを生み出した。もしインテルの職場で真のダイバーシティが実現したら、すなわち地域の人口構成比と同じ比率を職場で再現し、さらに経営幹部層の多様性が平社員のそれと等しくなったら、この数値はさらに大きくなるだろう。
企業はこうした数字の善し悪しを見て、その数値を上下に動かせるレバーがどこにあるかを理解することで、ある意思決定の本当のインパクトを見定めることができる。例えば、自社工場の労働環境の改善策をさらに進めるかどうか判断に迷っているならインパクト加重会計を使うことで、その改善策が最終的にいくらの価値を生み出すか把握できる。
評価のモノサシがあれば、大きなことも考えられる。例えば、政府がインパクト加重会計というモノサシを使い、企業のなした害悪に課税したり、逆にプラスのインパクトに対して直接的な経済的インセンティブを与えたりすることも想像できる。またインパクト加重会計は投資家・消費者・就業者としての我々に、究極の比較ポイントを与えてくれる。投資先・購入先・就職先の企業を選ぶ際、それらの数値から総合的に判断すればいい。
現在のところ、いくつかの業界で(企業の)環境破壊と株価低迷には有意な相関関係があることが明らかになっている。そうした相関関係が見られない業界も、マテリアリティ〔重要課題。社会課題の解決のために会社が取り組むべきテーマ〕の欠如というよりは、評価・計測の手段がないことが理由だろう。透明性――とりわけインパクト加重会計が提供するような、分析に適した形式での透明性――こそが、今後より多くのサステナビリティ要素をより多くの業界でマテリアルな指標にしていくためのカギとなる。インパクト加重会計は、企業の善行を加速させる分析手法として、社会と企業が同じ方向を目指すための究極のゲームチェンジャーになり得る。
〔中略〕
政府がインパクト加重会計の公表を義務づけ、企業と投資家に対して気候変動や不平等などの問題解決の取り組みに加わるよう求めるのが早ければ早いほど、我々の社会はより良くなるだろう。〔中略〕
〔中略〕インパクト透明性は、まさに資本主義をつくり直す可能性を秘めている。利潤追求が問題を生むのではなく、それが世界に問題解決をもたらすように変えていけば、我々は成功の意味を再定義し、おカネだけではなく、人が一生の間に生み出したプラスのインパクトを成功のモノサシにすることができる。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第3章 透明性と結果責任 : もはや隠し事は不可能」の章内の、「未来に影響を与える」の項目、「インパクト加重会計がゲームチェンジャーとなる」の項目、「次のステップは何か」の項目より)
「インパクト加重会計によって、企業価値が向上するのか?」という疑問に対する回答としては、金融庁金融研究センターが出している論文「インパクト加重会計の現状と展望 : 半世紀にわたる外部性の貨幣価値換算の試行を踏まえた一考察」が参考になるかと思います。
その論文の内容については、金融庁金融研究センターの「ディスカッションペーパー」のページに、下記のような要約文が記載されています。
本稿は、「企業によるインパクト創出と企業価値向上は両立するのか」「企業がインパクト創出を目指すことは、企業価値向上との間でトレードオフを引き起こすのではないか」といった疑問や感覚が、企業経営の現場や投資の実務家の間で少なからず存在することを念頭に置きつつ、インパクト創出と企業価値向上の関係についての究明を試みるものである。本稿では、企業によるインパクト創出の源泉として、「パイの拡大」と「パイの分配の見直し」を区別するという捉え方を引用する。これにより、環境問題や社会問題の解決に資する事業の規模拡大という「パイの拡大」を通じてインパクト創出を目指す場合、本質的にはそこにトレードオフは存在しないことが示唆される。他方、利益という企業の取り分を減らすかわりに、社会の構成員の取り分を増やすという「パイの分配の見直し」によってインパクト創出を目指す場合、そこには本質的にトレードオフが存在することが示唆されるわけであるが、実際の企業事例調査からは、そのトレードオフを乗り越えようとする企業努力や、トレードオフの解消に繋がる規制環境等の変化といった好機を捉えることで、最終的にはインパクト創出と企業価値向上を同時に実現している企業の存在が明らかとなった。さらに、日本企業のパーパスに着目した実証分析を通じて、インパクト志向の強い企業のほうが、財務パフォーマンスも上回る傾向にあることも明らかとなった。これらの分析・考察により、インパクト創出と企業価値向上の同時実現は、常に可能というわけではないものの、状況次第では十分に可能であることが示唆される。
柳モデルが、人件費が投資であることを実証
さきほど紹介したインパクト加重会計と同じように、「ESG(環境、社会、企業統治)についての取り組みから生まれる「見えない価値」を、財務諸表の数値に反映させて「見える価値」にする仕組み」のひとつとして、「柳モデル」というものがあります。「柳モデル」は、「ESGを重視した経営をすることで、企業価値が高まる」ということを実証した理論です。柳良平さんという人が生みの親なので、「柳モデル」と呼ばれています。
(※柳良平さんのプロフィール:製薬会社エーザイ 元CFO(最高財務責任者)。「伊藤レポート」執筆委員。資産運用会社 M&Gインベストメンツジャパン 副社長。早稲田大学大学院 会計研究科 客員教授。)
柳良平さんが、「ESGを重視した経営をすることで、企業価値が高まる」ということを実証したエーザイの実例は、下の動画の「19:33~23:18」のところで紹介されています。(下記の「エーザイのESGと企業価値の実証研究」のところの文章をご参照ください)。
(※下の動画は、前半の「柳良平さんの講演」と、後半の「柳良平さんと渋澤健さんの対談」の2部構成になっています。柳良平さんと渋澤健さんの関係については、柳さんがエーザイのCFOを務めていたときに、長期投資をしている機関投資家の代表である渋澤さんと、「投資される側と、投資する側」として付き合いが始まり、その後も協力して仕事をされているそうです。)
(※渋澤健さんのプロフィール:長期投資家。コモンズ投信株式会社取締役会長、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役。渋沢栄一さんの玄孫(5世代目の子孫)。)
19:30
▼柳良平さんのスライド資料
エーザイのESGと企業価値の実証研究
感応度分析(信頼区間95%における平均値試算)
- 人件費投入を1割増やすと5年後のPBRが13.8%向上する
- 研究開発投資を1割増やすと10年超でPBRが8.2%向上する
- 女性管理職比率を1割改善(例:8%から8.8%)すると7年後のPBRが2.4%向上する
- 育児短時間勤務制度利用者を1割増やすと9年後のPBRが3.3%向上する
↓
エーザイのESGのKPIが各々5~10年の遅延浸透効果で
企業価値500億円から3,000億円レベルを創造することを示唆
(※話がわかりやすくなるように、あえて単純化すると、ここでの文脈において、柳良平さんは、PBR(株価純資産倍率)を「どのくらい企業価値を生み出しているか」を示す指標として利用しています。PBRは、株価を1株当たり純資産で割った数値です。PBRが1倍を上回る場合は、「企業価値を生み出している」(企業の持つ純資産価値を上回る評価が市場でなされている)ということを意味します。逆に、PBRが1倍を下回っている場合は、「企業価値を生み出していない」と判断されます。)
柳良平さんは、PBRの数値のなかの、1倍を超える部分を「非財務資本」と呼んでいます。ここで言う「非財務資本」とは、「知的資本、製造資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本」の5つです。具体的には、インフラや、知的財産、人材の能力や経験、外部とのネットワーク、環境資源などのことです。下の動画での、柳良平さんや渋澤健さんの話に出てくる「見えない価値」とは、この「非財務資本」のことです。
▼ 19:33~23:18上記の「エーザイのESGと企業価値の実証研究」のスライドで示されている実証研究結果のデータは、下記の「エーザイの実証研究結果」の表でもご覧いただけます。
▼ エーザイの実証研究結果
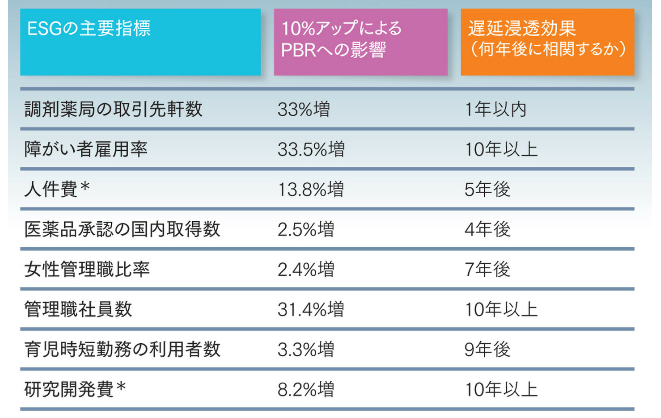
(出典:『エーザイで実証した評価モデルから導く ESGの「見えざる価値」を企業価値につなげる方法 (特集 ESG経営の実践) (ハーバード・ビジネス・レビュー論文)』、柳良平、ダイヤモンド社、2021年1月。「図表5 エーザイの実証研究結果」より(一部分)。)
また、上の動画の「23:18~25:23」のところでは、「ESG EBIT(ESGイービット)」(ESGの営業利益)についても語られています。「ESG EBIT(ESGイービット)」は、「長期的に見ると、人件費や研究開発費は先行投資となって、のちに企業価値を向上させる」という実証結果を損益計算書に反映させるための指標です。
(※ESG EBIT(ESGの営業利益)=営業利益+研究開発費(知的資本)+生産活動・営業活動に関わる人件費(人的資本))
「ESG EBIT」(ESGの営業利益)の詳細については、柳良平さんの論文『エーザイで実証した評価モデルから導く ESGの「見えざる価値」を企業価値につなげる方法』のなかで、下記のように説明されています。
これまで述べてきたように、人件費やR&D費〔研究開発費〕は、「費用」というよりも、将来の価値につながる非財務資本を築くための「投資」だと考えることもできるだろう。その場合、財務諸表はどうなるのか。
筆者は、「ESG EBIT」(ESGの営業利益)としてESGに基づく損益計算書を統合報告書で開示した。ここでは人件費やR&D費を営業利益に足し戻してESG EBITとして計算している。そう言うと「インチキではないか」という声も聞こえてくるかもしれないが、先に述べたように、エーザイの人件費とR&D費が5年後、10年後の企業価値につながることはすでに実証済みだ。実証研究の証拠の提示とともに、東京海上アセットマネジメントの菊地勝也氏、三菱UFJ信託銀行の兵庫真一郎氏など、エーザイと直接対話を行う長期投資家からこの考え方は支持されている。
なぜこのような提案をするのかといえば、短期的な投資で利益を求めるショートターミズムへの反発心があったからだ。短期的な投資家が「人件費とR&D費をもっと切って足元の利益を上げろ」と言った時に、「いや、これは費用じゃない。投資だ」と言い返す証拠として提示するのだ。
〔中略〕
ESGを実践するには、このような証拠を積み上げて、見えない価値を投資家に啓発しなければならない。企業価値とESGのつながりを示す取り組みは、今後も活発化していくだろうし、我々の研究も発展途上である。各企業において、ぜひ見えない価値を見える化し、「真の利益」を追求してもらいたい。
そうすれば、日本企業の平均PBRは国力から言ってもおのずと英国並みの2倍に届き、仮説として日経平均株価は4万円になるだろう。時価総額の増大により、日本企業によるいっそうの投資や雇用が拡大し、国内の年金運用ファンド等の運用益も高まり、長期的に国富が増大し、より豊かな社会を実現できる。
企業がESGの取り組みを企業価値につなげることで、日本社会を豊かにできる一翼を担えるのだ。
(出典:『エーザイで実証した評価モデルから導く ESGの「見えざる価値」を企業価値につなげる方法 (特集 ESG経営の実践) (ハーバード・ビジネス・レビュー論文)』、柳良平、ダイヤモンド社、2021年1月。)
下の動画でも、柳良平さんが「柳モデル」について語っています。上の動画の内容と重複するところもありますが、ご参考までに。
▼ 0:00~36:02サステナビリティ(持続可能性)で資産を増やした事例集
ESG(環境、社会、企業統治)に関する重要なキーワードのひとつに、「サステナビリティ(持続可能性)」という言葉があります。
ちなみに、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)という言葉もあります。「SX」は、「社会や自社のサステナビリティ(持続可能性)を重視した経営をすることで、長期的に企業価値を向上させていこう」という活動を指す言葉です。
(※「SX」に似ている言葉として、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉があります。「DX」は、「データやデジタル技術を活用して、ビジネスを成長させよう」という活動を指す言葉です。「SX」は、「DX」のサステナビリティ版のようなものです。)
ジョージ・セラフェイムさんは、「サステナビリティを重視した経営をすることで、業績が向上する」というような意味のことを語っています。そのことについては、ジョージ・セラフェイムさんの著書『パーパス+利益のマネジメント』のなかで、下記のように語られています。(※ジョージ・セラフェイムさんは、ハーバード・ビジネス・スクールの教授であり、ESG投資の世界的な権威です。)
ここまでくると、サステナビリティのとてつもない好循環と、本書の中核をなす議論が見えてくる。すなわち、パーパス主導型企業は業績が向上するのだ。その理由の一端は、サステナビリティ要素を事業の牽引役として活用する素晴らしい方法がいくつもあるからであり、また別の理由として、こうしたテーマを重視する企業では同じ価値観の社員が奮起し、より熱心に働くようになるからだ。一方で、個人がミッションとパーパスにすべてをかけようとすると、犠牲が大きくなるケースもよくある。前述したレイニール・インダールがその典型だ。業績絶好調の企業を辞め、取る必要のなかったリスクを取ることになった。だが、それによって得られる見返りが変わるのだ。自分が誇れるもののために日々貢献していると感じられるなら、個人が得る見返りははるかに大きくなる。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第1章 何のためにビジネスをするのか」の章内の、「結果が証明している」の項目より)
また、ジョージ・セラフェイムさんは、上記と同じ本のなかで、「サステナビリティを重視した投資をすることで大きく資産を増やした複数の事例」を、下記のように紹介しています。
デイビッド・ブラッドは、元米国副大統領アル・ゴアが会長を務める投資会社ジェネレーション・インベストメント・マネジメントの共同創業者兼シニアパートナーである。同社は、(投資先の)長期的なサステナビリティ実績を重視するため、サステナビリティ分析を投資判断の中核に組み込むと宣言した初めての投資会社の1つである。2004年に運用資産1億ドルでスタートし、今では300億ドル〔約4兆3000億円〕に迫ろうとしている。2020年には、過去1年間で最も成績が良かったファンド(169社のグローバル株式ファンドの中で)としてランキング1位を獲得している。長期的な投資判断におけるサステナビリティ要因の重要性に関し、同ファンドに長年にわたり協力してきた私としては、この成功に驚きはなかった。
過去5年間のジェネレーションの歩みを振り返るとき、私は10年ほど前のロサンゼルスでの講演を思い出す。ファミリーオフィス(裕福な一族の資産管理会社)や比較的小規模な投資ファンドの運用担当者に向けたものだった。聴衆の雰囲気は冷たく、ほとんどの人はESG投資に極めて懐疑的で、投資リターンを犠牲にして行うものだと信じていた。私が示したデータもなかなか信じてもらえなかった。
講演が終わりに近づいた頃、聴衆の1人が私に向かって次のような発言をした。自分はずっと懐疑的だったが、ジェネレーションと出会って考えを変えた。多少は善行になるだろうと思って、資金の一部を何のリターンも期待せずにジェネレーションに投資したところ、すべての投資先の中で1番の投資リターンをもたらしてくれた。もっと多くの資金を同ファンドに投資しておけばよかったと強く後悔している――。彼の予想は、現実に起きていたこととまったく調和していなかったのである。
第1章に登場したレイニール・インダールを覚えているだろうか。ESG問題に特化したプライベート・エクイティ・ファーム、サマ・エクイティを立ち上げ、今や10億ドル超を投資している人物だ。彼はハーバード・ビジネス・スクールの私のクラスで登壇し、会社のあらゆる判断においてサステナビリティを考慮に入れることがいかに大変か、そしていかに見返りが大きいかについて話してくれた。サマは他のファンドと姿勢や行動が違うことは有名なので、時には最高値を提示しなくても企業を買収できることもある。サマは起業家たちから、自分の会社のパーパスを維持・強化してくれる信頼できるパートナーであり、他の投資家にはできない付加価値を与えてくれると見られている。
こうした例は上記2つだけでなく、いくらでも挙げることができる。サステナブルかつ責任ある投資を重視するカルバート・リサーチ・アンド・マネジメントのCEOにジョン・ストイアーが就任した2015年から、私は彼に協力している。カルバートは社会的責任投資の投資商品を最初期につくった1社である。同社はこの分野で30年以上の経験があったが、それでも自社の考え方を説明すると(顧客の)ポートフォリオマネジャーに反発されることがあった。データを十分に理解してもらえず、同社のミッションは財務的根拠のある賢明な投資と両立しないと思われ、離れていく顧客もいた。わずか数年で何億ドルもの運用資産を失った時期もある。
ジョンと私は、サステナブルな企業を成功に導く要因をさらに深く理解するため努力を重ね(結局それはマテリアリティ〔重要課題。社会課題の解決のために会社が取り組むべきテーマ〕と確固たるデータだった)、最後には顧客に我々のビジョンを受け入れてもらえるようになった。ジョンはカルバートの業績を反転させた。運用資産はほぼ3倍に増え、2020年には300億ドル〔約4兆3000億円〕を超え、調査研究に裏打ちされた賢明でサステナブルな投資によるリターンを手にしている。
他にもまだいくつか実例を挙げたい。
世界最大級のプライベート・エクイティ・ファームであるカーライル・グループは、サステナビリティを巨大な差別化要因だと考えている。同社は2018年に次のように述べている。「投資家の財産を預かる管理人としてカーライルが請け負う責務は、賢明な投資と価値の創造である。この10年、我々は受託者としての能力を高める方法の1つとしてサステナビリティへの取り組みを強化してきた。極めて簡単に言えば、健全なESG関連の取り組みは我々の投資プロセスと投資結果を向上させる」
モルガン・スタンレーは2013年に「サステナブル投資研究所」を設立し、5年以内にサステナブル投資やインパクト投資のための投資資金100億ドル〔約1兆4000億円〕を集めることを目標とした。彼らはその目標を大幅に上回り、現在250億ドル〔約3兆5000億円〕の資産を運用している。モルガン・スタンレーのCSO(最高サステナビリティ責任者)オードリー・チョイは、私が企画して350人が出席した会議に登壇し、最初は多くの人が同研究所に懐疑的で、まさかこれほど成長するとは誰も思っていなかった、と話した。その見方が間違いだったと彼らは証明したのだ。
〔中略〕
彼〔レイニール〕は間違いなく、ただ世界に貢献するだけでなく、リスクを減らしてリターンを増やし、業界に破壊的創造をもたらし、しかもサプライチェーンその他も改善できるような方向に投資先企業を変えつつある。トレンドの方向性は明らかだ。確かに誰もがレイニールと同じように全身全霊で取り組んではいないかもしれないが、現時点で“投資にサステナビリティは重要だ”と考えていない人を探すほうが難しい。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第7章 変化を後押しする投資家の役割」の章内の、「ニューアラインメントを受け入れる投資家たち」の項目より)
ちなみに、上記の引用文のなかに出てきた「インパクト投資」の説明については、鎌田恭幸さんが、下記のように述べています。(※鎌田恭幸さんは、「社会をよくする投資」というテーマを掲げて、社会性を重視した投資を行っていることで有名な、鎌倉投信という投資信託の運用会社の社長です。)
「社会をよくする投資」の流れの1つに「ソーシャル(社会的)・インパクト投資」がある。〔中略〕
ソーシャル・インパクト投資とは、社会性と経済性を二項対立でとらえるのではなく、
特定の社会課題を改善させる事業や会社を後押しすることを目的とした投資のことを言う。社会課題とは、たとえば、脱炭素や森林保全、食や農業、医療・福祉、貧困層への融資(マイクロファイナンス)などだ。〔中略〕
ESG投資を広くとらえ、その一部として見られることもある。しかし、ESG投資が社会的な視点を持ちながらも「会社の持続的価値、最終的には株価を高めるための投資手法」として位置づけられているのに対し、ソーシャル・インパクト投資は、まずは解決すべき社会課題領域を明確に定義するところから始まる。そして、社会、環境にプラスのインパクトを生み出すことを事業や投資の目的としたうえで、一定のリターンを狙う投資手法をいう。
(出典:『社会をよくする投資入門:経済的リターンと社会的インパクトの両立』、鎌田恭幸、ニューズピックス、2024年。「第5章 投資の「新しい選択肢」」の章内の、「②ソーシャル・インパクト投資」の項目より)
ダイベストメントで社会を改善する
ESG(環境、社会、企業統治)を軽視する会社には、ダイベストメント(投資資金の引き揚げ)というかたちで「罰」を与えることで、ESGを促進するというやり方もあります。
たとえば、ジョージ・セラフェイムさんは、機関投資家(年金基金)がESGを重視している企業に投資するようにうながすために、ダイベストメントの手法を利用した例を紹介しています。ジョージ・セラフェイムさんの著書『パーパス+利益のマネジメント』のなかでは、下記のような例が紹介されています。(※ジョージ・セラフェイムさんは、ハーバード・ビジネス・スクールの教授であり、ESG投資の世界的な権威です。)
ダイベストメント(投資資金の引き揚げ)という方法を選べば話は簡単だった。よく使われる政治的手法であり、この手法を勧めるメールを諮問委員全員が多数受け取っていた。だが、同基金は我々委員の助言に従い、多面的戦略を採ることにした。すなわち、投資先企業の全社に対して最低水準の目標値を設定し、それをクリアできたら引き続き株主を続けるが、クリアできなければ投資資金を引き揚げる(ダイベスト)。さらに同基金は、気候変動問題の解決策となりそうな投資先に数十億ドルの資金を投じた。これは、データを実際に活用し、貧弱なESG実績のリスクを浮き彫りにする素晴らしい実例だった。今後もニューヨーク州退職年金基金に株主でいてほしいと思う企業は、地球のことを念頭に置いて行動する必要がある。
年金基金はこうしたテーマを、おそらく他の大半の投資主体よりも重要に考えている。なぜなら年金基金は投資期間が超長期に及び、責任を果たしていくには100年後も世界に健全な姿でいてもらう必要があることを自覚しているからだ。化石燃料への投資が年金基金にとって極めて危険なのはこのためだ。もし化石燃料ビジネスが消え去れば――その原因が規制にせよ、彼らの生み出す気候変動リスクの強制的な内部化にせよ――そうした危険な投資もゼロになるだろう。ダイベストメントが世間一般の方針となっても、それだけで問題解決にはならないが、人々がこうした問題を深刻にとらえていると示す効果はある。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第7章 変化を後押しする投資家の役割」の章内の、「結果に表れてきたサステナビリティ」の項目より)
また、ジョージ・セラフェイムさんは、ダイベストメントについての話のなかで、日本のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の以前の最高投資責任者であった、水野弘道さんが語ったESG的な投資理念を、下記のように紹介しています。
ヒロ・ミズノ(水野弘道)は、運用資産1.6兆ドルの日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)で前の最高投資責任者を務め、現在はテスラの取締役でもある。私はハーバード・ビジネス・スクールのクラスに定期的に彼を招待し、登壇してもらっている。彼によると、年金基金の運用というのは、目前の四半期や1年ではなく100年単位で物事を考える仕事だという。GPIFは株式公開している世界中の大企業のほぼ全社について1%以上を所有している(日本の大企業はほぼ全社について5%以上所有)。したがって、ヒロはビジネスリーダーに対してとてつもない影響力を持っていた。
数年前、彼ははっとするような気づきを得た。それは、巨大な投資機関の持つ力について、我々に考え方を変えるよう迫る気づきだった。彼はこう考えたのだ。投資マネジャーとは、適切なポートフォリオを組んで市場平均をわずかに上回る投資成績を残せば、それで仕事をしたといえる。誰にも文句は言われない。だが、別の考え方もできる。ファンドがあまりに巨大でほぼ市場すべてに投資しているような場合、市場が10%下落したのに自分のファンドは9%の下落だったからといって大成功とはいえない。下落相場で自分だけ市場平均をわずかに上回って満足するのではなく、そもそも市場全体が10%の下落をしないように、投資マネジャーとして何かできることがあるのではないか――。
ヒロは、古典的な投資マネジャーの評価方法に疑問を抱くようになった経緯を私のクラスで話した。市場に勝つことだけを目標とするのではなく、彼とそのチームは“全体の所有者”という概念を考え出したのだ。「我々は市場全体を所有しているので、市場と競争して勝つということができないのです」。彼は市場に勝とうとするのではなく、市場全体をよりサステナブルにするために力を注ぐようになった。
ヒロは、自分のポートフォリオだけをより良くするのではなく、世界をより良くしようと決心したのである。2021年の春、彼は私のクラスで次のように話した。
「ある年金基金の投資マネジャーは『我々の仕事はおカネを大事にすることであって、地球を大事にすることではない』と言いました。別の人には、私の言っていることが金融の専門家というよりも宗教の教祖みたいだと言われました。受託者責任を果たしていない、とも言われました。みな、あらゆる道理を述べて私に考え直すよう迫りました。そこで私は問い返しました。『我々の孫が外で遊ぶことさえできなくなったら、年金を満額受け取ることにどんな意味がありますか?』と――」
ヒロの考え方は大胆不敵である。誰もがすぐに理解してくれるわけでもない。それでも彼の話は、巨大な投資機関がその気になれば世界を変える大きな力を持てるということをよく表している。もちろん、我々みんなが水野弘道ではないし、巨大な年金基金の責任者でもない。だが、ここで話はぐるりと一周して、本章冒頭の問いかけに戻る。個人としての我々は、この種の取り組みを後押しするために何ができるだろうか――。
間違いなくできることがある。自分の年金資金を預けている投資マネジャーに圧力をかけるという手だ。私はニューヨーク州退職年金基金の仕事を通して確信したが、このやり方は間違いなく大きな効果がある。英国には、誰でも参加できるさらに公的な仕組みがある。それは「メイク・マイ・マネー・マター」(私のおカネにモノを言わせる)という新しい取り組みで、普通の市民が自分の年金資金を調べ、自分のおカネがどこに投資されているかを知ることのできる仕組みだ。メイク・マイ・マネー・マターのウェブサイトには次のように書かれている。
「英国の年金基金にはざっと3兆ポンドの投資資金があります。そして多くの資金が、化石燃料やタバコ、兵器といった有害な産業に投資されています。この状況を改善するよう要求することが我々の役目です。害ではなく益をなす投資をしてもらい、また我々の年金パワーを使って投資先企業にも同じ行動をしてもらいます」
まず最初に必要なのは透明性だ。透明性があれば、我々は行動の改善を要求できる。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第7章 変化を後押しする投資家の役割」の章内の、「結果に表れてきたサステナビリティ」の項目より)
社会にとって良いことをしよう
近年、ESG、CSR、CSV、SDGsなどの、社会性を重視する考え方が、ますます注目をあびています。これらのキーワードは、かんたんに言うと、「社会にとって良いことをしよう」「社会にとって悪いことを無くそう」ということだと言えるでしょう。
こうした「社会性を重視する経営」について、下の動画の登壇者である、髙島宏平さんと、キャシー松井さんの言葉を紹介します。
▼お二人のプロフィール
- 髙島宏平さん:「Oisix(オイシックス)」や、「らでぃっしゅぼーや」などを運営している、自然派食品宅配の最大手である、オイシックス・ラ・大地株式会社の社長。元マッキンゼーのコンサルタント。
- キャシー松井さん:日本初のESG重視型グローバル・ベンチャーキャピタルファンドである、MPower Partners Fund L.P. (Mパワー・パートナーズファンド L.P. )のゼネラル・パートナー。ゴールドマン・サックスの元日本副会長。
(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
36:04~36:56
▼髙島宏平さん:オイシックス・ラ・大地 社長
会社の若いエンジニアやデザイナーさんたちに、「なぜ、ここで働いているの?」と聞くと、「地球のため」「人類のため」と言う。
地球や社会にとってマイナスになる会社には、優秀な人材が集まらなくなる。「地球や社会にとってプラスになる会社で働きたい」という人が増えている。日本でも、そうしたことを重視しない会社は、若い人を採用できなくなる。
37:00~39:12
▼キャシー松井さん:MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー
優秀な人材に来てもらい、長く働いてもらうためには、「なんのために、毎日職場に来て働くのか?」「どのように社会に貢献しているのか?」という質問に答える必要がある。
(そうでなければ、若い人は集まらないし、離職率も高くなってしまう。)
BLM(ブラック・ライヴズ・マター)運動や、MeToo(ミートゥー)運動などの、社会運動や社会問題に対して、自社がどのような対応をするのかを示す必要がある。そうしないと、若い人たちの反感を買ってしまい、退職してしまう人が増えたり、不買運動が起こってしまったりする。
スタートアップ企業は人材がすべてなので、そうしたことを重視する必要がある。
上の動画で、キャシー松井さんが語っている、「社会問題に対する志を持たない会社は、お客さんの反感を買ってしまう」という話の実例として、下記の「消費者アクティビズム」の話を紹介します。(下記の文章は、ESG投資の世界的な権威であるジョージ・セラフェイムさんの著書『パーパス+利益のマネジメント』からの引用です。)
〔前略〕消費者や社員による意思表示として「アクティビズム」(社会に訴える積極的な行動)が激増しているのだ。
〔中略〕
消費者によるアクティビズムの話も似たようなものだ。2017年のウーバーに対するボイコット運動(#DeleteUber)が好例だろう。当時のドナルド・トランプ大統領が複数の国をテロ活動と結び付け、米国への入国禁止令を出すと、タクシー運転手による抗議のストライキが広がった。ウーバーはこれを商機と捉えて積極的な宣伝を行ったことで、消費者から厳しく批判され、何十万人もの消費者がウーバーの利用をやめた。さらに同社を舞台とするセクハラ問題が表面化すると、いっそう多くの人が利用をやめた。元社員のスーザン・ファウラーが同社のセクハラ文化や性差別について公開質問状を突きつけ、CEOのトラビス・カラニックは自身のスキャンダルもあって辞任に追い込まれた。
米VOXメディアは消費者アクティビズムを取り上げ、「問題意識を持つ消費者運動とは、自分が同意できるブランドから購入し、そうでないブランドからは購入しない、という人が増えること」と解説した。消費者アクティビズムは若者中心に広がっているが、決して若者だけの動きではない(ある調査によると、ミレニアル世代が購入を決める第1の要因はブランドの世評だ。「エネルギー消費量を削減した企業は選好される確率が32%上がり、慈善活動に寄付した企業は30%上がり、大衆の声を聞く企業は20%上がる」という)。VOXは、コーネル大学の歴史学者ローレンス・グリックマンの言葉を引用し、消費者の3分の2は少なくとも年に1度は不買運動に参加していると伝えた。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第2章 “インパクト世代”のインパクト」の章内の、「意思表示:消費者と社員のパワー」の項目より)
ちなみに、投資家の藤野英人さんは、上の動画に出演しているキャシー松井さんのことを高く評価しているようです。藤野さんが、キャシー松井さんについて語っている様子は、下の動画の「9:58~12:20」のところで見ることができます。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
9:58
▼加藤貞顕さん:note株式会社CEO
関美和さんと、キャシー松井さん、村上美香さんというすごい3人の女性が、ESGを重視して投資をするベンチャーキャピタルファンドの、MPower Partners Fund(Mパワー・パートナーズファンド)を立ち上げられました。
そして、すでに 160億円を集めて、日米の3社に投資されています。
〔中略〕
11:06
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
この3人の方々が、新しいESGのファンドを作ったことは、金融業界では、けっこうな事件だったんです。
キャシー松井さんのことは、彼女がゴールドマン・サックスにいた頃にお会いすることが何度もあったので、よく知っています。
その頃から、キャシー松井さんは、グローバルで活躍されていました。当時の彼女は「殿上人」でした〔かなり上位の役職に就いておられました〕。
キャシー松井さんのすごいところは、ぜんぜん偉そうにしないところ。好奇心も旺盛。視座が高いのに、上から目線ではない。
だから、金融業界でキャシー松井さんの悪口を言う人はいません。彼女は、尊敬されています。
そのキャシー松井さんが、〔ゴールドマン・サックスを辞めたということも事件でしたが、〕この3人のメンバーで新しくファンドを立ち上げたということが事件でした。
ソーシャル・ネイティブな若者たちが、社会の主流派になる
ユーグレナの社長の出雲充さんは、「サステナビリティ・ファーストじゃないと、優秀な人材が来てくれなくなる」と語っています(下の動画の 34:24~36:07 参照)。出雲さんは、株式会社ユーグレナの「哲学」として、「持続可能性」を最重要視する「サステナビリティ・ファースト」という考えを打ち出しています。
▼ 34:24~36:07ユーグレナの社長の出雲充さんは、「2025年には、ソーシャル・ネイティブな若者たち(生まれながらに社会性を重視する若い世代の人たち)が、社会の主流派になるので、そこで社会全体の意識が、サステナビリティ(持続可能性)を重視する方向へ大きく変わる」というような意味のことを語っています。その話は、『サステナブルビジネス : 「持続可能性」で判断し、行動する会社へ』という本のなかで、下記のように語られています。(※ミレニアル世代:2000年代に成年期を迎えた世代。デジタルネイティブの最初の世代)。
私は、ミレニアル世代が世界の生産年齢人口の過半数を占める2025年までに、これまでの資本主義のビジネスから、ソーシャルビジネスやサステナブルビジネスが主流となる持続可能な社会へと世界は大きく変化すると考えています。
〔中略〕
2025年にミレニアル世代が過半数になれば、政治が変わり、消費者の商品やサービスを選ぶ基準が変わります。それに対応するため企業の商品づくりやサービス内容も変わります。働き方も変わり、生活の仕方も大きく変わるでしょう。
すべてのこと、あらゆることを、「それは持続可能か(サステナブルか)」というモノサシで判断する時代が到来するのです。
(『サステナブルビジネス : 「持続可能性」で判断し、行動する会社へ』「6章 ミレニアル世代の価値観が世界を変える」より)
出雲さんは、上記と同様のことを、下の動画でも語っています。また、下の動画では、CFO(最高未来責任者)という、独創的な取り組みについても語られています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです。)
32:01~35:35
▼出雲充さん:株式会社ユーグレナ社長
2025年に、パラダイムシフトが起こる。その年を境に、サステナビリティ〔持続可能性〕を重視しない企業は、優秀な人材を採用できなくなり、商品を買ってもらえなくなる。
その年に、生産年齢人口の半数がミレニアル世代になる。〔※その年から、ミレニアル世代が、社会の主流派になる。〕
ミレニアル世代は、ソーシャルネイティブ〔社会的な価値を重視する〕です。
なので、サステナビリティ〔持続可能性〕を重視しない企業は、社会の主流派であるミレニアル世代に相手にされなくなってしまう。
だからこそ、2025年になる前に、サステナビリティ〔持続可能性〕を重視する会社へと変化する必要がある。
35:40~36:58
▼出雲充さん
未来を正確に予測することには価値がない〔※正確な未来予測は不可能であり、未来予測はハズレるから〕。
未来を予測する代わりに、未来の世代の人から、意見をもらうようにした。
そのために、CFO(最高未来責任者、チーフ・フューチャー・オフィサー)という役職をつくった。
現在、15歳の高校生に、CFOの役職に就いてもらっている。
〔※彼女が、会社のナンバースリー。CFOの役職は、会社で上から3番目の地位にある〕。
若い世代の彼女の目から見て、自社や、自社の商品・サービスが、若い人たちから支持されるものになっているかどうか、チェックしてもらっている。
小学5年生が、生成AIでアプリを作る時代
上の動画では、ユーグレナの社長の出雲充さんが、「CFO(最高未来責任者)」について、「高校生に会社の重役になってもらうことで、若い人の意見を事業に活かしている」というような話をされていました。
もしかすると、その話を聞いて、「子どもの意見を事業に活かすことなんてできるの?」「子どもの意見を、大の大人が真に受けて大丈夫なの?」と思われたかもしれません。
それについては、下の話をご覧いただければ、「子どもや若い人たちの力」を実感していただけるかと思います。
この下の Xのポスト(旧Twitterのツイート)では、プログラミングのプロであるエンジニアの人が、プログラミングコンテストで小学生の子どもたちがつくったアプリを見て、そのレベルの高さに驚いています。
下の Xのポストの1枚目の画像のスライドを見ると、そのコンテストの受賞者の一人である小学5年生の人が、さまざまなテクノロジーを組み合わせてアプリを作っていることがわかります。具体的には、ChatGPTで使用されている生成AIモデルのGPTや、Amazonの音声合成技術、ユーザーインターフェースのテンプレートなどを組み合わせて、独自のアプリを作っています。
この事例を見ていただければ、ChatGPTなどの生成AIをはじめとした、さまざまなテクノロジーの力を活用することで、「たとえ、未成年の子どもであっても、大人と同じか、それ以上の能力を発揮することができる」ということがおわかりいただけるかと思います。そして、今後は、こうした「子どもや若い人たちの力」を実感するできごとが、もっと日常的に起こるようになるでしょう。
この事例からもわかるように、AI時代には、「子どもや若い人たちの力」が、社会的にますます重要なものになっていくでしょう。
最近のプログラミングしてる小学生のレベル高すぎて草
— とくゆー@Progaku (@tokuyuuuuuu) March 1, 2024
現役エンジニアのワイ涙目なんだが😭
後10年もしたらこういう子達と仕事するかも知れないのかぁ。。。https://t.co/lau5jPwd8x pic.twitter.com/vjQ0pWOrC8
上記の「小学5年生」の人が作ったアプリについては、下の動画の「2:06:46~2:17:20」のところで、本人がそのアプリを紹介している映像を見ることができます。また、下の動画の「2:10:33」のところで、上の Xのポストで紹介されている、「このアプリを作るために使用した技術」の一覧リストのスライドを見ることができます。
▼ 2:10:33~2:17:20マッキンゼー「利益だけでなく、社会性を重視するべき」
もしかすると、ここまでお話してきた「利益だけでなく、社会性を重視する」という話のなかに、「きれいごとじゃないの?」と思われるところがあったかもしれません。
ですが、そうではないのです。
マッキンゼーという、有名な経営コンサルティング会社があります。マッキンゼーのコンサルタントの方々は、資本主義のど真ん中で、大企業とともに世界中の経済を動かしてきた、いわば「資本主義のプロ中のプロ」です。(※この記事のなかで紹介している、大前研一さんや、安宅和人さんや、篠田真貴子さんや、髙島宏平さんも、元マッキンゼーのコンサルタントです)。
その「資本主義のプロ中のプロ」であるマッキンゼーが、今の世の中の流れの変化を踏まえて、「これからは、利益だけでなく、社会性を重視するべき」と、はっきり言い切っています。
下の画像は、そのマッキンゼーの宣言を、短くまとめて箇条書きにしたものです。(この話については、くわしく解説されている記事を、マッキンゼーのウェブサイトで見ることができます。こちらのリンクで、その記事の日本語訳の文章を読むことができます(Google翻訳を使用)。(原文はこちら)
下記の文章は、その下の画像の「マッキンゼーの宣言」の英文を意訳したものです。(※上記リンクの「マッキンゼーのウェブサイト」のページの内容を踏まえた意訳にしています)。
下記の「マッキンゼーの宣言」の第1番目の「重視すること」の項目に、「利益 →影響」と、はっきり書かれています。これは、「自社の利益」だけでなく、「社会に良い影響を与えること」を重視するべき、ということです。マッキンゼーは、「資本主義のプロ中のプロ」です。そのマッキンゼーが、今の世の中の流れの変化を踏まえて、「自社の利益を追求するだけではダメで、社会性を重視するべき」と言っている、ということです。これを見ていただくと、ここまでお話してきた「利益だけでなく、社会性を重視する」という話が、「きれいごと」ではなく、とても重要な「経営指標」であるということが、おわかりいただけるかと思います。
新時代の組織を繁栄へ導く新たなリーダーシップ
現代のリーダーに求められる、考え方と働き方についての5つの重要な変化
-
1 重視すること:利益を追求する → 良い影響を与える
ビジョナリー〔将来を予測する先見の明を持つ人〕として、可能性を信じて、すべてのステークホルダー〔従業員・社会・自然環境などの幅広い関係者〕に対して、全体的な良い影響を与える。 -
2 価値を創造する方法:競争する → 共創する
設計者〔事業を構築する役割をする人〕として、「利用できる機会や資源は豊富にある」という考え方のもとに、自社の収益構造や他社との共存関係を新しく設計し直して、供給業者や競合他社と協力して、ともに新たな価値を創造する。 -
3 組織を運営する方法:命令する → 協働する
触媒〔変化をうながす役割をする人〕として、人々に権限を与えて、自律的に働く人たちが、部門間の壁を超えてつながり合うネットワークをつくることで、協力して働けるようにする。 -
4 仕事の進め方:管理する → 進化する
コーチ〔学びをうながす役割をする人〕として、探求や実験や学習をすばやくおこなえるように人々を導き、イノベーションの種を見つけて、継続的に進化しつづける。 -
5 振る舞い方:自分だけで成果を出す → 全員で成果を出す
一人の人間として、弱みも含めた「ありのままの自分」をさらけ出す勇気を持つことで、職場の心理的安全性をはぐくみ、人々の潜在能力を最大限に発揮してもらう。
What skills do executives need to lead thriving organizations today? Our article explores crucial leadership shifts in depth and shares real-world examples of companies that have moved beyond current norms to evolved leadership ambitions.
— McKinsey & Company (@McKinsey) February 25, 2024
Find out more: https://t.co/JYJt5KcpdB pic.twitter.com/HLdtbZKOsR
また、上記の内容に関連する情報として、マッキンゼーの各種の記事やレポートでは、下記のことも指摘されています。
実際には、従業員に権限を与えるということは、より実践的なリーダーシップのアプローチを取ることを意味する場合があります。リーダーから意思決定の権限を与えられた従業員は、組織に委任された意思決定が迅速かつ高品質であったと答える可能性が 3倍以上高くなります。
(出典:マッキンゼー「リーダーシップとは何でしょうか?」(Google翻訳を使用)(原文))
マッキンゼー・グローバル・インスティテュートが15カ国、さまざまな業界の大企業1,800社を対象に行った調査によると、財務実績に加えて人材開発に重点を置いた企業は、平均的な企業に比べて長期にわたって高い業績を維持する可能性が約1.5倍高く、収益の変動性も約半分に抑えられているという。実際、COVID-19パンデミックが発生したとき、これらの企業は収益性を維持し、主に財務実績に焦点を当てた企業よりも2倍の速さで収益を増加させました。
(出典:マッキンゼー「「内側から外側へ」のリーダーシップの旅: 個人の成長が成功への道を切り開く方法」(Google翻訳を使用)(原文))
▼ おわりに
「長期」ってどのくらい?
ここまで、「長期的な視点をもった長期志向がたいせつ」という話をしてきました。ですが、「長期って、具体的にはどのくらいなの?」という疑問が湧いてくるかもしれません。そのことを考えるにあたって、参考になりそうな考え方をいくつか紹介したいと思います。
投資家の藤野英人さんは、ここまで紹介した話に何度かあらわれているように、「10年先の未来を見据えて投資をする」ということを重要視しています。たとえば、下の動画の「5:14~7:59」のとこで藤野英人さんが語っている下記の話も、そういった「10年先」についての話の一例です。
▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者
「未来志向の投資とは」
5:14
まず一番大事なのは意志です。
「僕らは、未来を作ろうとする集団なんだ」という強い意志を持つことがとても大事なことだと思っています。〔中略〕
会社全体として、「僕らは未来を作る集団なんだ」というふうに思わなければいけない。
〔中略〕
6:02
「短期的な目線」は捨てよう。それは、もういらない。僕らは常に、10年後のことを語ります。
7:23
「〔長期的な目線をもった〕投資家と、10年後の話をしたい」という会社経営者は、けっこういると思います。そうした未来の話をした時に、目を輝かせる会社の人たちとともに歩んでいきたいなと思っています。
投資をするときに、長い目線で、会社とのパートナーシップを考えて、「未来をともに作っていく仲間なんだ」という旗を掲げて、僕らの存在感も高めたい。
経済産業省が立ち上げた「SX研究会」(サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会)は、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に基づく経営に必要な要素として、次の3つを挙げています。
- 存在意義(パーパス)
- 重要課題(マテリアリティ)
- 長期ビジョン
このなかの「長期ビジョン」については、下記のように説明されています。(下記の文章は、『戦略的人的資本の開示 運用の実務』という本からの引用です)。
経済産業省が2021年5月に立ち上げたサステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(略称:SX研究会)によれば、SXに基づく経営には、
- 存在意義(パーパス)
- 重要課題(マテリアリティ)
- 長期ビジョン
の3つの要素を明確にすることで企業のあるべき姿が定まるとしている。
〔中略〕
長期ビジョンとは、パーパス〔会社の存在意義〕やマテリアリティ〔重要課題。社会課題の解決のために会社が取り組むべきテーマ〕を踏まえて特定した長期の期間経過後に想定される、企業のあるべき姿と社会のあるべき姿を、自社の競争優位性・強みから描き出す「目指すべき姿」である。
なぜ長期ビジョンが必要かというと、たとえば次年度の価値創造(経済的・社会的なインパクトの創出)を2倍にするだけならば、簡単ではないが難しくはない。しかし10年後に企業価値を10倍にするとなれば、1~3年の戦略は意味を持たず、10年先のゴールを設定し、逆算して10年後の価値創造が最大化される道筋を作らなければならない。
また、既存のビジネスモデルを多少改良したところでゴールに辿り着けないので、まさにSX〔サステナビリティ・トランスフォーメーション〕による変革を起こさなければならない。
このときの「長期」とは、事業環境、社会全体の潮流、投資家の投資目線等を総合的に勘案して各企業が自社の経営事情に即して特定する。そのため、一律に10年という長さが適切であるとは限らない。
(出典:『戦略的人的資本の開示 運用の実務 : 必須知識の体系的整理と実戦的戦略策定ガイド』、HRテクノロジーコンソーシアム [編集]、日本能率協会マネジメントセンター、2022年。「第2章 投資に活用されるためのESG情報開示」の章内の、「1 ESG情報開示の趨勢」の節内の、「情報開示とSX」の項目より)
(※バックキャスト:上記の引用文で言及されているような、「将来のあるべき姿や目標を設定して、そこから逆算して、現在なにをするべきかを考える」という思考方法(計画方法)のことを、「バックキャスト」という言葉で言いあらわすこともあります。)
安宅和人さんは、『シン・ニホン』という本のなかで、未来を考えるときの考え方のひとつとして、「イニシアチブ・ポートフォリオ」というものを提案しています(下図参照)。
(※安宅和人さんのプロフィール:Zホールディングス シニアストラテジスト。慶應義塾大学 SFC 環境情報学部 教授。元マッキンゼーの経営コンサルタント。イェール大学で脳神経科学の博士号取得。データサイエンティスト協会理事。)
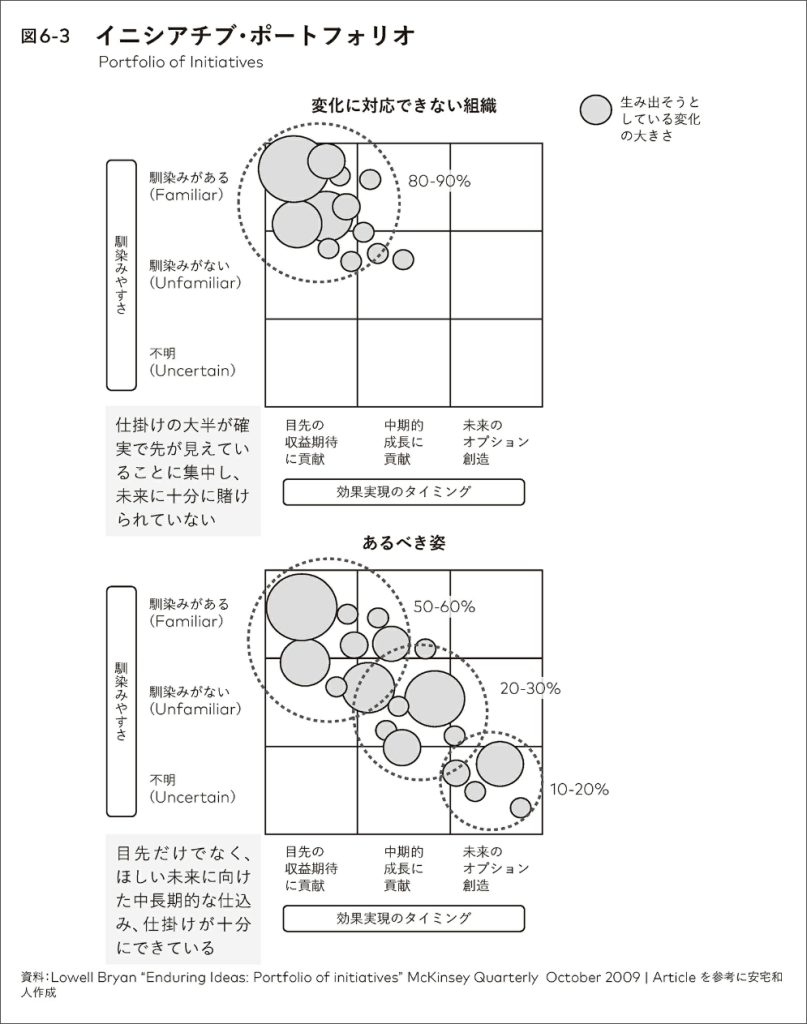
(図の出典:『シン・ニホン : AI×データ時代における日本の再生と人材育成』、安宅和人、ニューズピックス、2020年。第6章の第1節内の「イニシアチブ・ポートフォリオという考え方」の項目より)
また、安宅和人さんは、「(今のような変化の速い時代には、)15年以上の未来について考えることには、ほとんど意味が無い」というようなことを、下の動画の「31:29~32:17」のところで語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。
31:29
▼講演の参加者からの質問
AI時代の未来を考えるうえで、どれくらいの時間軸を設定するべきでしょうか?
〔中略〕
32:00
▼安宅和人さん:ヤフー株式会社 CSO(最高戦略責任者)
15年以上の未来について考えることには、ほとんど意味が無い。なぜなら、新しい技術が登場して、前提条件が変わってしまう可能性が高いから。
ユーグレナの社長の出雲充さんは、「未来に対応する方法」として、CFO(最高未来責任者)という、独創的な取り組みをされています。そのことについて、出雲さんは、「未来を予測することは不可能です。だから、未来を予測するかわりに、若い世代の人から意見をもらうようにしています」というようなことを、下の動画で語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです。)
35:36~36:58
▼出雲充さん:株式会社ユーグレナ社長
未来を正確に予測することには価値がない〔※正確な未来予測は不可能であり、未来予測はハズレるから〕。
未来を予測する代わりに、未来の世代の人から、意見をもらうようにした。
そのために、CFO(最高未来責任者、チーフ・フューチャー・オフィサー)という役職をつくった。
現在、15歳の高校生に、CFOの役職に就いてもらっている。
〔※彼女が、会社のナンバースリー。CFOの役職は、会社で上から3番目の地位にある〕。
若い世代の彼女の目から見て、自社や、自社の商品・サービスが、若い人たちから支持されるものになっているかどうか、チェックしてもらっている。
鵜呑みにすることの危険性について
ここまで、いろいろな企業や組織の人たちが、動画や本などで語っている言葉やキーワード(用語)などを紹介してきました。ですが、この記事で紹介している人物や組織や企業、キーワード(用語)、考え方のほとんどには、賛同の声がある一方で、批判の声や問題点もあります。ですので、たとえ、有名な人や企業や組織が発信している情報であったとしても、それらの言葉を、無批判に信じ込むのは、危険です。
また、この記事で紹介しているキーワード(用語)は、良くも悪くも、「マーケティング用語」であるという側面があります(これらの言葉自体が、一種の「商品」になっています)。ですので、それらのキーワード(用語)を、金科玉条のように、無批判に良いものだと信じ込むことには危険がともなうのでご注意ください。
また、この記事で紹介している情報は、できるだけ正確を期すように努力してはいるのですが、どこかに誤りが含まれている可能性も無いとは言えません。
ですので、この記事で紹介している人物や、キーワード(用語)や、考え方を、無批判に信じ込んだり、鵜呑みにしたりすることは、危険ですので、ご注意ください。
以下では、そうした注意点についての一例として、この記事で紹介している人物や、キーワード(用語)などに対する批判の声を、いくつか紹介します。この記事で紹介している人物や、キーワード(用語)には、賛同の声がある一方で、下記のような批判の声もある、ということを、頭のすみに置きながら、この記事をお読みいただければと思います。
▼短期投資家についての注意点
ここまで、長期志向の重要性をお伝えしてきました。ですが、長期投資だけが重要で、短期投資は不要なのかというと、必ずしもそうではありません。
「短期投資家の必要性」については、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の理事、兼、CIO(最高投資責任者)の、水野弘道さんが、下の動画の「24:58~25:57」のところで述べておられます。(※上記の肩書きは、下の動画の撮影当時のものです)。下記の引用文にあるように、水野弘道さんは、「金融市場が、長期的に効率的であるためには、短期の投資家、長期の投資家、逆張り投資家、順張り投資家など、いろいろな投資家がいることが必要である」という意味のことを述べておられます。
▼水野弘道さん:GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の理事、兼、CIO(最高投資責任者)(※撮影当時の肩書き)
24:58
短期の投資家の話について。
「伊藤レポート」の中でもう1つ提案されたのが、「経営者・投資家フォーラム」(マネジメント・インベスター・フォーラム)の創設です。
私もそのメンバーとして参加させてもらっています。その中で、「短期の投資家をどうするか?」という議論が出ます。
私は、長期的な市場効率性の信奉者です。
ですので、長期的にマーケットが効率的であるためには、「短期で儲ける人」も必要であるということは、皆さんにも分かっていただきたいと思います。
25:44
市場というのは、短期の人、長期の人、逆張りする人、順張りする人など、いろいろな人がいることで、はじめて効率性が保たれます。
そういう意味では、不要に短期の投資家を排除することは、健全ではないと思います。
「金融市場が健全に機能するために、短期の投機家が必要である理由」については、下記の引用文も参考になるかと思います。下記の引用文は、資産運用会社スパークス・アセット・マネジメントのファンドマネージャー、兼、上席研究員である、水田孝信さんのレポート「なぜ株式市場は存在するのか?」からの引用です。
また、下の動画で、下記の引用文を映像化した動画を視聴できます。
(※下記の引用文のなかの「分秒の数字」は、下の動画内の各時点をあらわしています。)
なぜ株式市場は存在するのか?
〔中略〕
〔0:10~0:34〕
なぜ株式市場が存在するのか私なりに考えたことを、わかりやすさを重視して書きました。これを考えることにより、例えば、なぜ株式は毎日売買できる必要があるのか、なぜ短期の投機家を排除してはいけないのか、もっと言えば、そもそも株式投資とは何なのか、といったことへの理解が深まります。
〔中略〕
〔9:26~10:27〕
投機家がいることによって、投資をやめたい投資家と始めたい投資家は、この企業の投資家をスムーズに交代できるわけです。ようは株式の売買が容易になるわけです。この株式の売買の容易さを”流動性“とよびます。投機家による流動性の供給があるからこそ、投資を始めたりやめたりするのが容易なのです。
そして、もし2次市場に流動性がなければ、投資家は1次市場での投資を躊躇してしまいます。1次市場で投資した株式が2次市場で容易に売却できるからこそ、投資資金の回収が容易であり、不確実性の高い事業にも投資できるのです。もし投機家が少なく2次市場の流動性が低ければ、1次市場での投資を躊躇する投資家が増え事業資金が集まらず、人類が起こすイノベーションは減ってしまうでしょう。流動性はイノベーションを起こすのに必要なものなのです。
〔中略〕
古本屋は本の中身に興味がない、でも「けしからん」とはならない
〔10:29~10:56〕
「投機は社会の役にたっていない」、「投機はただのギャンブルだ」といった批判がときどきあります。これらの批判の延長として「高頻度取引(HFT = High Frequency Trading)は悪だ」といったことまで言う人がまれにいます。ここまで読んだ皆様ならこれらの批判が見当違いであることはおわかりかと思います。投機はひとつの職業として成り立っていると思います。
このことを、古本屋を例にとって考えて見ましょう。〔中略〕
〔12:03~12:38〕
〔中略〕古本屋は本を読むために本を買っているわけではありません。90円で買った本が95円で売れれば、中身はどうでも良いわけです。古本屋は本の流動性を供給していますが、本を読んでいません。投機家に相当する振る舞いです。
しかし、古本屋は「社会の役にたっていない」とか「ただのギャンブルだ」とか「職業として認められない」といったことになるでしょうか?古本屋が職業として認められるなら、投機家も職業として当然認められるべきだと思います。
〔中略〕
(*6) 投資家と投機家は厳密に区別することはできません。事業内容をまったく考えずに値上がりしそうという理由だけで何年も保有する投機もありえるでしょうし、事業内容を良く考えて買った株式が1日も経たずに売りたい価格に達して売却することもあるでしょう。両者が混じったような売買も考えられます。株式を買うときにどのような考えで買ったかという主観でしか区別できず、客観的に両者を厳密に区別することは不可能ですし、それを試みることに意味はないと思います。
(出典:水田孝信「なぜ株式市場は存在するのか? | レポート | スパークス・アセット・マネジメント」のページより)
上記の引用文を映像化したものが、下の動画で視聴できます(9:27~10:27)。
▼ 9:27~10:27▼ESGについての注意点
この記事では、ESGについての情報も紹介しました。ですが、ESGについては、批判の声もあります。
たとえば、下記のような、「グリーンウォッシュ」(環境に配慮しているように見せかける偽装行為)に対する批判も、ESGに対する批判のひとつです。
誰もがこのようなやり方をしている、と言うつもりはない。レイニール〔ESG投資家〕は、多くのプライベート・エクイティ・ファーム〔未上場企業投資会社〕がマーケティング用の“グリーンウォッシュ”(環境に配慮しているよう見せかける欺瞞)に手を染めているといつも話している。口では正しいことを言っているが、必ずしも行動が伴っているとは限らない。
(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第7章 変化を後押しする投資家の役割」の章内の、「ニューアラインメントを受け入れる投資家たち」の項目より)
「社会をよくする投資」というテーマを掲げて、社会性を重視した投資を行っていることで有名な、鎌倉投信という投資信託の運用会社があります。その鎌倉投信の社長である鎌田恭幸さんは、「ESG投資が乗り越えるべき課題」として、次の4つを挙げています。
- 画一的な評価基準からの脱却
- グリーンウォッシュ
- 運用会社と投資家との共感構築
- ESGの目的化
上記の4つの課題について、鎌田恭幸さんは、下記のように述べています。
〔前略〕ESG投資がこれから乗り越えて行きたいハードルが4つある。
1. 画一的な評価基準からの脱却
数多くの会社を共通基準で測ろうとすると、どうしても多くの評価項目を、アンケートや公開情報をもとに点数をつけてスコア化する方法がとられる。そうなると、形式的で網羅的な見方に留まってしまい、会社の本気度や本業を通じた社会価値創造の実態、さらに最も重要な「会社の個性」を評価することが難しくなる。
一次スクリーニングとしてはよいかもしれないが、根本にある思想を見定め、長い視点でしっかりと支援する投資を行いたい。
2. グリーンウォッシュ
以前から存在している投資信託を、販売目的で名前だけ「ESG投資」に衣替えするケースがある。環境への貢献を表面的に装いながら、実態を伴わない投資商品も多く見られ、「グリーンウォッシュ」と呼ばれ問題となっている。
ESGを謳う投資商品をアピールしながらも、その一方でお金を増やすことだけを目的とした多様な投資商品やファイナンス商品を運用、販売するケースもある。銀行による「グリーン融資」なども同様で、まさにダブルスタンダードだ。
「ESG投資」を謳うのであれば、いうまでもなくESGの目的と無関係な投資や融資は止めるべきだ。
3. 運用会社と投資家との共感構築
「社会をよくする」視点を持った投資は、投資信託などの投資商品をつくる運用会社と、そこにお金を預ける年金基金や個人投資家との「価値観の共有」が重要となる。大元の投資家が短期目線だと、投資信託などを運用する会社も、投資先それぞれの企業へ求める利益や株価上昇のプレッシャーが短期的になりがちだからだ。
社会によい取り組みに挑戦する会社の事業は、総じて難易度が高く、時間がかかる挑戦も多いため、必ずしも短期的な株価とは連動しない。むしろ、短期的に見れば株価にマイナスの影響を与えることもありえるし、場合によっては環境負荷をかけないための投資を増やすぶん、株式の将来リターンが下がることもあるだろう。
投資信託やファンドにお金を預ける投資家は、そうしたことを理解したうえで、長期で会社の活動を支える後ろ盾になることが大切となる。しかしそれはけっして容易なことではない。「社会に目を向けた投資」に対する投資家の関心がけっして高いといえない現状のなか、投資の意図を投資家と共有していくためには、それを実践する運用会社に信念がなくてはならない。さらに、その信念に基づく投資方針や投資先の活動、リターンを含めた投資の成果を投資家に訴求し、共感につなげるプロセスは、地味で粘り強さが求められる。それができる運用会社や販売会社は少ない。
ESGを謳う投資信託の運用を開始してから短期間で1兆円ものお金を集めたものもあるが、そのなかにESGの理念を理解して投資をはじめた投資家がどれほどいるだろうか。
リスクとリターンのみで金融商品の価値を測る投資家が多いなか、共感性を築くことは容易ではないが、ESG投資の運用会社は、その努力を怠るわけにはいかない。
4. ESGの目的化
ESG投資には、ESG評価や情報開示、それらに付随するコンサルティング、二酸化炭素の排出権取引のように自然を商品化した取引市場などの周辺ビジネスが生まれ、多くの人がそこに関与する。こうして新たな投資領域でビジネスが生まれること自体は問題ないが、ESGを謳い文句にビジネス化することを目的にすることには疑問が残る。
ESG投資に関わるすべてのステークホルダーにとっての共通目的は、投資家のリターンや会社の利益を犠牲にすることなく、社会にいいお金の循環を生み出すことだ。けっしてお金で自然や社会をコントロールできるものではなく、その根底には、自然や地球環境、人の命のつながりである社会に対する畏敬がなくてはならないと僕は思う。「社会をよくする投資」には、それに関わる人の誠実さが求められる。
(出典:『社会をよくする投資入門:経済的リターンと社会的インパクトの両立』、鎌田恭幸、ニューズピックス、2024年。「第5章 投資の「新しい選択肢」」の章内の、「可能性:ESG投資が乗り越えるべき4つのハードル」の項目より)
山崎元さん(楽天証券経済研究所 客員研究員)は、「「ESG投資」を警戒する理由」というテーマで、ESG投資の問題点を指摘しています。その話は、下の動画の「6:45~18:40」のところで語られています。(※上記の肩書きは、下の動画の撮影当時のものです)。
▼ 6:45~18:40▼ステークホルダー資本主義についての注意点
この記事では、ステークホルダー資本主義についての情報も紹介しました。ですが、ステークホルダー資本主義については、批判の声もあります。たとえば、下記の引用文で指摘されているように、「ESGを謳っている団体のほとんどが、それを実践していない」という批判もあります。
(※下記の文章中の「ビジネス・ラウンドテーブル(BRT)」とは、アメリカの主要な大企業のCEO(最高経営責任者)で構成されている、影響力の大きい経済団体です。BRTは、2019年に、「企業の目的(パーパス)に関する声明」を公表して、ステークホルダー資本主義を提唱しました。)
ハーバード・ロースクールのルシアン・ベブチャック教授は,その論文の中で「ビジネス・ラウンドテーブルの提言に名を連ねている企業は多いものの,定款や報酬・統治システムを変更したケースは皆無であり,ステークホルダー資本主義は幻想であり,メディアや世論に対する言い訳に過ぎない」と手厳しい。
(出典:『企業価値経営 第2版』、伊藤邦雄、日経BP、2023年。「第15章 非財務・ESG情報による企業評価」の章内の、「資本主義の見直し : 株主資本主義対ステークホルダー資本主義」の項目より)
また、「ステークホルダー資本主義」という概念を積極的に提唱してきたことで有名な人物として、世界経済フォーラム(通称、ダボス会議)の創設者であり、元会長であるクラウス・シュワブさんという人がいます。クラウス・シュワブさんは、この記事で、情報の出典のひとつとして紹介した『ステークホルダー資本主義』という本の著者でもあります。ですが、(「ステークホルダー資本主義」に対する直接的な批判ではないものの、)クラウス・シュワブさんについては、彼の振る舞いの一部に対する批判もあります。(彼に対する批判の詳細は、後述します)。
▼ウェルビーイングと、ポジティブ心理学についての注意点
この記事では、ウェルビーイングについての情報も紹介しました。ですが、ウェルビーイングの理論的根拠となっているポジティブ心理学については、批判もあります。
たとえば、ヨーロッパにおける、ウェルビーイングや、ポジティブ心理学の第一人者である、イローナ・ボニウェルさんは、著書のなかで、下記のような、ポジティブ心理学の問題点を指摘しています。
ポジティブ心理学にはすばらしいところがたくさんありますが、正しいといえないところや、まちがいにつながりそうなところも多くあります。
〔中略〕
たくさんの関連する先行研究を持ちながら、ポジティブ心理学は驚くべきことに、取り扱っているトピックの数千年の歴史ある研究成果を無視してしまっています。
〔中略〕
現在のところ、ポジティブ心理学で研究するすべてのトピックをまとめることができるような、包括的な理論が存在していません。ポジティブ心理学ではあまりに多くの事柄を改善しようとしていて、それらの事柄の間にどのような関連があるのか明確にわかっていません。トピックの選び方そのものでさえ、時に恣意的に思えます。
〔中略〕
主流の「科学的な考え方を採用しながらも、ポジティブ心理学は安っぽい、簡単な手法に頼ることが多くあります。この分野で行われている研究の半分以上は、いわゆる「相関研究」です。相関研究とは、1つの事柄が別の事柄と確実に関連していることを証明する研究です。
しかし、相関研究は、1つの要素が別のものを引き起こす、いわゆる因果関係までは示してくれません。たとえば、運動をする人は、そのおかげで健康を享受しているのかもしれませんが、健康な人ほど運動に取り組む活力があるのだと考えることもできます。心理学者たちも、相関関係は因果関係を意味するわけではないとよく承知していますが、それをあたかも因果関係を示しているように解釈し、あることが別のことにつながるような印象を与えていることもよくあるのです〔中略〕
〔中略〕
過去の心理学がネガティブなものにばかり目を向けるという大きなまちがいを犯し、ポジティブな要素をないがしろにしてきたとすれば、ポジティブ心理学も、振り子を逆方向に振りすぎることによって同じまちがいを起こしてはいないでしょうか。ポジティブ心理学の支持者たちが、過去60年間の心理学は不完全だったと主張するのは結構ですが、それが過去の心理学をシャットアウトする結果につながってはいけません。ポジティブ心理学は、人生におけるバランスのとれた視野をもたらすというより、ネガティブな要素やどちらでもない要素を排除することで繁栄をめざそうとする危険に陥っています〔中略〕
〔中略〕
ポジティブ心理学は、一般大衆に積極的に売り込みをかけているなかで、いまだにできるだけ目新しく独特なイメージを与えようと奮闘しているようにみえます。
(出典:『ポジティブ心理学が1冊でわかる本』、イローナ・ボニウェル、国書刊行会、2015年。「第15章 ポジティブ心理学の未来」の章内の、「ポジティブ心理学の問題点」の節(318~327ページ)より)
▼世界経済フォーラム(ダボス会議)と、クラウス・シュワブさんについての注意点
この記事では、世界経済フォーラム(WEF。通称、ダボス会議)が発信している情報や、その創設者であり、元会長であるクラウス・シュワブさんの本で語られていることも紹介しました。ですが、その世界経済フォーラムは、いろいろな批判を受けています。
そうした批判を象徴するような出来事のひとつとして、世界経済フォーラムの創設者であり、50年以上もこの組織の運営を担ってきたクラウス・シュワブ会長や、同組織の管理職による、「セクハラや人種差別疑惑」が問題になっています。
クラウス・シュワブ会長については、「数十年にわたるシュワブ氏の監督下で、女性や黒人に敵対的な職場のムードがWEFをむしばんでいた」とされています。世界経済フォーラムは、「クラウス・シュワブ会長が2025年1月までに同フォーラムの会長職を退任すると発表」しましたが、それでも、彼は、「退任後も非業務執行の理事長職としてとどまる」としています。こうした、クラウス・シュワブさんの言動に、世界経済フォーラムという組織が抱えている問題の一端があらわれているのかもしれません。(参考文献:ウォール・ストリート・ジャーナルの記事と、日本経済新聞の記事)。なお、クラウス・シュワブ会長は、2025年4月21日に辞任して、その翌日に、彼が不正行為をしていたとする内部告発を受けて、調査対象となっています。(参考文献:ロイターの記事)。
ちなみに、世界経済フォーラムにかぎらず、大きな影響力のある国際機関や、公的・準公的な役割を担っている国際的な機関は、多かれ少なかれ、各主体が自分の利益のために権力闘争をおこなう場である、という側面ももっています。ですので、たとえ、世界的に有名な国際機関や、公的とされている国際機関であっても、その機関が発信している情報を、盲信したり、鵜呑みにすることは危険です。
▼ジョセフ・スティグリッツさんについての注意点
この記事では、世界経済フォーラムのウェブサイトに掲載されている、ジョセフ・E・スティグリッツさんの発言も紹介しました。ですが、そのジョセフ・スティグリッツさんに対する批判の声もあります。
たとえば、不確実性とリスクについての理論である「ブラックスワン理論」や、「反脆弱性」などについての著書で有名な、ナシーム・ニコラス・タレブさんも、ジョセフ・スティグリッツさんを批判している人物の一人です。ナシーム・ニコラス・タレブさんは、ジョセフ・スティグリッツさんのことを、「行動を誘発しておきながら、自分の発言の責任をまったく取らない連中」の代表的な人物であるとして、批判しています。また、ナシーム・ニコラス・タレブさんは、ジョセフ・スティグリッツさんが起こしている問題と同じ問題を起こしている人たちのことを、「スティグリッツ症候群」という言葉で表現しています(くわしくは、下記の引用文をご参照ください)。
ジョセフ・スティグリッツさんは、ノーベル経済学賞の受賞者であり、世界的に有名な経済学者です。ですが、そのような、世界的な名声と実績のある人であっても、ある面では、批判されるような行いをしている側面がある場合もあります。ですので、世界的に有名な人や、大きな実績のある人であっても、その人の言葉を、盲信したり、鵜呑みにすることは危険です。
下記の引用文は、ナシーム・ニコラス・タレブさんが、『反脆弱性』という本のなかで、「スティグリッツ症候群」について語っている部分です。
トーマス・フリードマンの問題よりももっと深刻な問題がある。一般化すれば、行動を誘発しておきながら、自分の発言の責任をまったく取らない連中と言うことができる。
私は次のような現象を、いわゆる“知的な”部類に入る経済学者、ジョセフ・スティグリッツにちなんで「スティグリッツ症候群」と呼んでいる。
〔中略〕2008年、予想どおりファニー・メイは破綻し、アメリカの納税者は数千億ドルの負担を負った(その負担はいまだに膨らみつつある)。同じようなリスクを抱えていた金融システム全般が崩壊した。銀行業界全体も同じようなエクスポージャーを抱えていた。
ところが、ちょうど同じ時期、ジョセフ・スティグリッツと同僚のオルザグ兄弟(ピーターとジョナサン)は、まったく同じファニー・メイを評価し、「過去の経験から見て、GSE債の潜在的なデフォルトによって政府が影響を受けるリスクはゼロに近い」と報告した。〔中略〕
極めつけは、スティグリッツが2010年に書いた「ほうら言ったじゃないか」的な本だ。ご大層にも、彼は2007~2008年に始まった危機を。“予測”していたとおっしゃる。
〔中略〕
学者というのは、何のリスクも冒さないものだから、自分自身の意見を覚えておくようにはできていないのだ。
〔中略〕
問題を起こした張本人の経済学者が、危機を後言し、挙げ句の果てには起きた出来事に関する理論家になったりする。こんなことでは、もっと大きな危機が起きても不思議じゃない。
要点はこうだ。もしスティグリッツがビジネスマンで、身銭を切っていたら、彼は吹っ飛び、終わっていただろう。〔中略〕私が吐き気を覚えたのは、政府がスティグリッツの共同執筆者のひとりを雇ったということだ。
〔中略〕
私はスティグリッツの誠実さを疑っているわけではない。少なくとも、嘘はついていないと思っている。彼は自分が金融危機を予言していたと本心から信じているようだ。だから、問題をこう言い換えたい。害のリスクを背負わない連中の問題点とは、矛盾しあう過去の発言の中から、好きなようにいいとこ取りできることだ。そしてしまいには、自分の知的洞察力は優れていると信じこんだまま、ダボスの世界経済フォーラムに向かうのだ。
(出典:『反脆弱性 : 不確実な世界を生き延びる唯一の考え方 下』、ナシーム・ニコラス・タレブ、ダイヤモンド社、2017年。「第23章 身銭を切る : 他人の犠牲と引き換えに得る反脆さとオプション性」の章内の、「アンフェア化する世界 : おしゃべり屋の無料オプション」の節のなかの、「スティグリッツ症候群」の項目より)
ここまでお伝えしてきたように、この記事で紹介している人物や組織や企業、キーワード(用語)、考え方のほとんどには、賛同の声がある一方で、批判の声や問題点もあります。ですので、反対側の意見や、いろいろな角度からの意見にも目を向けることをせずに、ひとつの視点からの意見だけを鵜呑みにしてしまうことは危険です。この記事で紹介している人物や組織や企業、キーワード(用語)、考え方のなかには、説明のための参考情報として紹介しているものもあるので、それらのすべてを推奨しているかというと、そういうわけではありません。(上で挙げたことがら以外のことがらについても、いろいろな批判の声や問題点があります。ですが、ここではそれらのすべてをくわしく説明させていただくことができませんので、割愛させていただきます。もし気になることや興味があることがあれば、そのことについての情報を集めてみていただくのもいいかもしれません)。
また、この記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の商品への投資を勧誘するものではありません。また、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する決定をする際は、リスクをご承知の上、ご自身の判断において行っていただきますようお願いいたします。
未来志向でいこう!
ここまで、長期志向(未来志向)のたいせつさについて、お話してきました。その締めくくりとして、次のお二人の言葉を紹介したいと思います。
- 伊藤邦雄さん:一橋大学CFO教育研究センター長。経済産業省が主催する各種プロジェクトの座長として、「伊藤レポート」や「人材版伊藤レポート」を発表。日本経済新聞社が主催する、日本版ウェルビーイングイニシアチブの、経営委員会の座長。人的資本経営コンソーシアム会長。
- 篠田謙一さん:東京・上野公園の国立科学博物館の館長。
伊藤邦雄さんは、サステナビリティを考えるときにたいせつなことについて、下の動画の「43:50~47:43」のところで語っています。そのなかで、下記のような、視野偏狭的で、短期志向的な、「たんきゅうしん」ではダメだ、ということが語られています。
- 単求心:単一の答えを求める心
- 短求心:短い時間軸で答えを求める心
上記のような「たんきゅうしん」ではなく、未来の世代まで視野に入れた、独創的な探求心(探究心)が必要だと、伊藤邦雄さんは語っています。
▼ 43:50~47:43最後に、東京・上野公園の国立科学博物館の館長である、篠田謙一さんの言葉を紹介したいと思います。(下記の引用文参照)。
博物館には長期的な使命があります。そのため、博物館の運営は、常に長期的視点に立って行われています。その館長である篠田謙一さんのお言葉には、「いまを生きる子どもたち」だけでなく、「これから生まれ育つ子どもたち」まで含んだ、遠い未来の世代に対するまなざしがあります。
博物館の研究者は、100年、200年とモノを集めたら、200年先の人間が教科書を書き替えるような発見をしてくれるという可能性を信じています。今の時代だと、その瞬間に稼げるお金に対しての必要経費という見方をするので、稼げない分野に関しては経費をかけるのをやめましょう、という話になってしまいます。長い目で考えるには、体力も知力も財力も必要なのです。それを必要経費と見るかどうか。人生100年時代において、長い目で物事を考えるか、短期的な投機を繰り返すのか。今は社会的なレジームチェンジが必要な時期なのだと感じます。今生まれたばかりの子どもや、これから生まれ育つ子どもは22世紀の世界を見ることになります。彼らが目の当たりにする世界をどう形作っていくか、今の私たちが考えて後世に伝えていかなければなりません。
(出典:『科博と科学 : 地球の宝を守る (ハヤカワ新書)』、篠田謙一、早川書房、2024年。「PART3」内の、「3 科博史上最大の挑戦 クラウドファンディングへの道①」の章内の、「地球の宝を守れ」の節より)
篠田謙一さんご自身が、上記と同じ主旨の話をされている映像は、下の動画の「6:11~7:42」のところで見ることができます。
▼ 6:11~7:426:11~7:42
▼篠田謙一さん:国立科学博物館館長
我々のやっている活動は、短期的にお金になる話ではないんですよね。「皆さんの社会が豊かになりますよ」という、非常に抽象的な部分を目的としてるわけですよね。ですから、それは今の人ではなくて、もっとずっと先の人たちのために活動している、という部分があります。
「科学」って言われると、「それ儲かるんですか?」「これ実用化したら社会が便利になるんですか?」ということを言われるんですけども、そういう部分でない科学のところを、我々は下支えしているようなところがあるんですね。「こういうのは国がやることだ」というふうに突き放すよりは、皆さんがサポートしてくれているということが、我々にとって重要だと思っています。
変な言い方なんですけども、こういうお金にならないことって、社会の皆さんにサポートされていないと、やがて根っこが枯れて倒れてしまうと思います。ですから、社会の皆さんと一緒に、私たちはこの「地球の宝」を守り続けていこうという活動を、今後とも続けていきたいと思って、マンスリーサポーターという形をとらせていただいています。
今日は、最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。
私たち国立科学博物館の研究員みんなで、この収蔵庫に新たな「地球の宝」を蓄えていきたいと思っています。そのための努力をいたしますので、ぜひご注目ください。